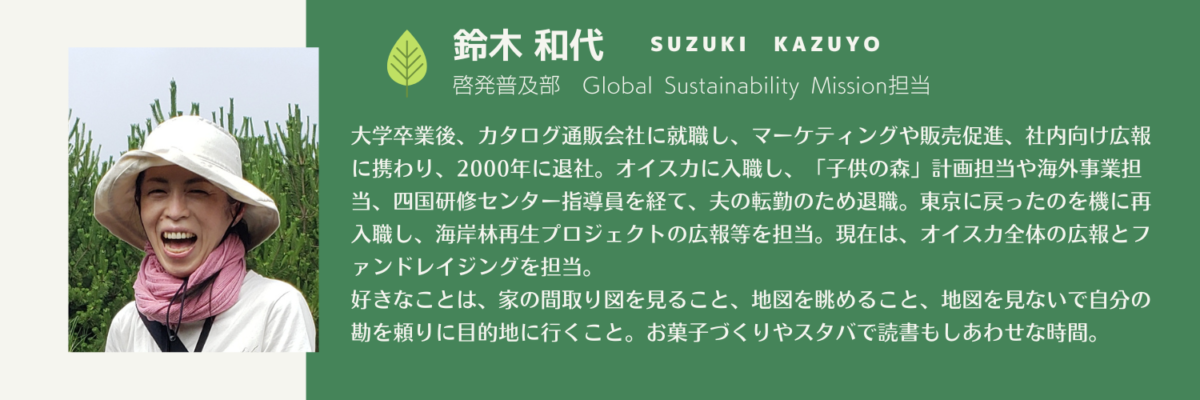啓発普及部の鈴木です。
今期は、「職員みんなでオイスカを盛り上げていこう」という趣旨で、職員向けにいろいろな分野の勉強会・報告会・説明会を開催しています。
勉強会・報告会・説明会というのが長ったらしいので、「オイスカアカデミー」と称して、これまで19回開催しました。(以前のブログで紹介したインドネシアOBの活躍も、アカデミーの一環です!)
3月12日に開催した第19回は、パプアニューギニアに赴任して32年になるパプアニューギニア駐在代表の荏原美知勝さんによる『パプアニューギニア オイスカラバウル研修センター 持続可能有機農業「腐葉土農法」』でした。
途上国の開発の現場で30年以上も農業指導を実践してこられた荏原さんの経験が凝縮された内容で、農業分野に疎い私も聞き入ってしまいました。内容の一部を紹介します。
荏原さんが最初に行った開発の現場はパラオ。オイスカはパラオに1982年に研修センターを設置し農業指導をしてきました。荏原さんがパラオに渡ったのは1983年。毎日、畑の土や作物を観察するうち、「有機で育てた野菜の苗と化学肥料で育てた野菜の苗の違いがはっきり分かるようになった」といいます。
 スイカ畑で@パラオ (右端が荏原さん)
スイカ畑で@パラオ (右端が荏原さん)
かつての荏原少年は、自然の雄大さや厳しさの中で動植物が生きる営みをテレビなどで見聞きしたり、植物や虫を観察したりするのが大好き。「化学肥料や農薬を使う慣行農法は野菜栽培には害となる虫を殺すことで成り立っています。どんな命も大切にしたかった。人間から見たら害となる虫さえも殺したくなかった」と語る。少年時代の自然を愛する純粋な心が有機農業に転換するきっかけだった。
以来、有機農業を探求したいと考えるようになり、色々な農業の勉強もし、「より安定した高収穫で持続可能、高品質な野菜の栽培をするには、現状に更に何かをプラスすることで実現できる」と考えていたそう。
プラスすることばかり考えているうち、最も大事にしなければならない開発現場でのコンセプトから、いつしかかけ離れているのに気付きました。「1.省力 2.省コスト 3.安定した収穫 4.省知識」。
そこで、180度方向転換し、何かをプラスするのでなく、マイナスしていく方法で、試行錯誤の末にたどり着いたのが「腐葉土農法」だったそう。
 堆肥づくり@パラオ(左が荏原さん)
堆肥づくり@パラオ(左が荏原さん)
 研修生たちとビーチにて@パラオ (前列右から3番目が荏原さん)
研修生たちとビーチにて@パラオ (前列右から3番目が荏原さん)
オイスカのパプアニューギニアでの農村開発の始まりは1986年にさかのぼります。当時の鳥谷部次男初代団長がコシヒカリの試験栽培を始めました。当時、パプアニューギニアでは「米の栽培はできない」と喧伝され、パプアニューギニアの人々はそう思い込んでいました。他でもないオーストラリアが自国の米の輸出先とするためでした。そのような事情の中、鳥谷部団長がコシヒカリを収穫し、当時のパプアニューギニア首相の視察を受けるほど、最高レベルの評価を受けました。
しかし、農薬と化学肥料に依存した慣行農業を継続していたため、トビイロウンカ(以下、ウンカ)の繁殖による被害も年々増えていきました。
1992年頃からは連日、日曜日も例外なく農薬散布をしましたが、ほとんどウンカの防除効果がなくなっていました。
 ウンカ対策のため農薬を散布(1991年当時)
ウンカ対策のため農薬を散布(1991年当時)
パラオでの10年間の駐在を終え、荏原さんがパプアニューギニアのラバウル・エコテック研修センターに赴任した当初の1993年5~8月頃は、まさに、ウンカとの闘いの日々だったといいます。
赴任早々、5ヵ所ほどの日本の農業試験場にウンカの対処法を問い合わせたところ、回答はすべてウンカに抗体のある品種を植えることという返事だったそう。
そのような中、「堆肥をたくさん田んぼに入れなさい」とアドバイスしたのが、インド、スリランカ、タイ、マレーシア、バングラデシュで活躍された福岡県の篤農家の高宮和三先生だったといいます。
現在、オイスカは有機循環型農業の実践を基本としていますが、途上国で農業指導を始めた1960年代から1990年代中ごろまでは農薬や化学肥料を使用する慣行農法での農業指導でした。
「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える」という考えは、今でこそ開発分野の基本となっていますが、オイスカは、海外で農村開発を始めた1960年代から篤農家を途上国に派遣して、一緒に田んぼや畑に入り、実技を通じて魚の釣り方を指導してきました。
オイスカ内で有機農業への転換の機運が高まったのは1990年代中ごろ。ブラジルのリオで地球サミットが開催され、環境問題への関心が高まった時代と重なります。
農薬を散布し続けるウンカとの闘いから何とか抜け出したい、高宮先生のアドバイスに賭けてみようと思い、空き地に繁殖していたカヤに米ぬかとヤシの油粕を加えて堆肥にしたものを田圃に散布し続けました。1993年8月にオイスカラバウル研修センター開所5周年記念式典を開催し、9月には「農薬と化学肥料散布放棄」を宣言したのでした。
赴任から9ヵ月、年が明けて1994年。日課にしている田んぼの見回りをしていたとき、「全体が朝日に照らされて、昨日と違う場所にでも来たかのようにキラキラと輝いている田んぼが目に入りました。何だろうと思って田んぼに近づいて観察したら、稲株と稲株をクモの巣が田んぼいっぱいに広がり、朝露に照らされ、それはそれは目を見張るほどの命の回復を見させて頂き深く感動しました。この光景と感動は今でも戦線ではっきり覚えています」と、純粋な少年っぽさを残す荏原さんの顔もまた輝いています。
「しかし、虫見版を使って調べると相変わらず、ウンカは1株に10匹も20匹もいたので、穂が出たらウンカの被害に遭うだろうと思いながらも朝夕の見回りを続けていると、今度は夕方には赤とんぼの群れ田んぼの上を舞う様子が観察されるようになりました。ひょっとしたらこのまま有機でコシヒカリが収穫できるかもしれないとの期待が心に沸いてきました。」そして、忘れもしない1994年4月7日、無農薬無化学肥料の有機栽培で初めての米の収穫ができました。この日のことを荏原さんは「忘れたことがない」と言います。開発の道に進み43年、この日のこの出来事が「私の原点」と、決して偉ぶらない柔和な笑顔で語ります。
 奇跡のコシヒカリ
奇跡のコシヒカリ
 2002年ごろの稲作
2002年ごろの稲作
以来、有機農業に魅せられ、安定した収穫ができる有機農法が確立できないものかと、30年以上も試行錯誤の連続。
ここにたどり着くまでに「EM菌」も試したといいますが、工場で培養されたEM菌より、パプアニューギニアのラバウルにいる何億年と命を繋いできた土着微生物の活用に勝るものはないとの事実に気づき、EM菌を使うのはやめたそうです。
雑草を使った野菜栽培も上手くいきましたが、土の乾燥を防ぐためのマルチとして使う草はすぐ土に返ってしまい、毎月、雑草が生えるため草を加えなければならず大変なことがわかり、これもこの土地で農業普及をするには不向きだった。
オイスカが目指すのは大規模なプランテーション農業ではありません。自然とともにある程度の収入を得ながら幸せに暮らしていけるよう家族や地域単位での小規模農業です。このような農業を普及するには、
1.農業知識があまり要らない 2.お金がかからない 3.細かい農業技術が要らない 4.重労働でない 5.毎日の管理時間は平均1~2時間程度
でなければ普及は難しいと荏原さんは言います。
「今も国土の約70%が森林に覆われて、活用されていない土地が多く、豊富な有機物を含む肥沃な土壌があり、豊かな降雨がある気候などを考えると、パプアニューギニアの農村が豊かになる可能性は十二分にある。バニラ栽培、沈香栽培などの高収入になる作物も取り入れながら、腐葉土農法を普及していきたい。」と力を込めました。
さらに、「『パプアニューギニアは将来世界に穀物を輸出する国になる』と、創立者の中野総裁が語っていました。世界を見渡すと穀倉地帯の農地が荒れ、気候変動や地域紛争で作物の生産が不安定になり、食糧不足が現実のものになりつつあります。パプアニューギニアが世界の危機に貢献する時が近づいてきているように思い、益々農業を通しての人づくりに邁進したいと気を引き締めています。」と語る荏原さんの目に輝きが帯びていました。
一時期、受入を停止していた10ヵ月間の農業研修コースが3月10日に再開し、ラバウル・エコテック研修センターは 65人の研修生を迎え、活気に溢れ出しました。
未知の可能性を秘めた国、パプアニューギニアにこれからも注目していきたいと思います。
関連動画