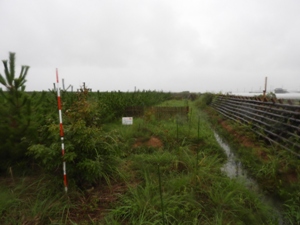7月は過去8年最少、8月は過去8年最多の降水量、お盆明けから連日雨の名取。
海岸林北端、広浦沿いでは、林野庁発注の静砂垣設置の建設会社約10人、
南端、北釜ゲート前では、名取市発注の旧宅地の基礎撤去工事数人。
今日は建設会社の杭打ちを見学しながら、ドリルで穴掘りする手応え、
杭打ちの感触など、多くの従業員からじっくり盛土の情報収集。
「14工区北側が固いね。南半分と穴開け方法変えたよ。石交じりだけどドリルなら砕ける。
マツなら大丈夫だと思うね」(社長)
「雨がたくさん降った後だから、杭が水に跳ね返される。反発だね」(職人さん)
滞水改善についても、現場代理人さんや、協力会社の社長さんに僕の意見を聞いてもらった。
「ずっと温めてたんだけど、まだジャストアイデアだから、統括と相談してからにします」(吉田)
中央部北寄りでは、森林組合の若いT兄弟が黙々と下草刈り。2人は4月以降ほぼ毎日名取。
「ハチに刺されてない?」(吉田)
「スズメバチに初めて刺されました~ 別の現場ですけど」(兄)
お茶を飲みながら、作業指示と、ボランティアの進捗状況の確認。
「刈り高は力枝の下だからね。丁寧過ぎて赤字にならないようにな。
誤伐すれすれで、幹周りを攻め過ぎるなョ(笑) 草も蔵王おろし対策になるから友達だよ。
いっつも言うけど、防風柵周りは、刃はこの部分だけ使うんだぞ。キックバックわかるよね。
(刈払い機による重大災害防止のために)」(吉田)
ゲートを閉めて戻る時、お揃いの水色Tシャツを着て虫取り網を振る2人を発見。
「息子が珍しいトンボを探していて・・・ここにいるって言うんで・・・」(父)
「なんって名前ですか?どんな色ですか?」(吉田)
「〇トンボ・〇トンボ・〇イトトンボです。色は・・・」(息子さん)
http://tombozukan.net/ym-marutanyanma.htm
http://tombozukan.net/ym-madara.htm
http://www.tombozukan.net/ito-kobaneaoito.htm
「それ、ここで見たかも!こんな綺麗な色のトンボ見たことないと思ったですよ」(吉田)
「ほんとですか?!どのへんでしたか?!」(父)
「うちの息子、3歳のころからトンボ好きで、50種類ぐらい確認してるんです」(父)
「イトトンボもいろいろいますよ。よく見るのはココです」(吉田)
「入っても大丈夫ですか?」(父)
「歩いてはいる分なら大丈夫ですよ。何か困ったら連絡してくださいね。
トンボ、僕も注目してるんだ。教えてほしいなあ。さすがにこれは分からないんで」(吉田)
名刺を息子さんに。
いい親子だな・・・惚れ惚れしました。虫取り網、本気で買おうかなぁ。
お盆挟んで、統括とも菅野さんとも会うのは1ヵ月ぶり。
「福島大学理工学部、今年は9月に4回植生調査するそうです。私いませんが」
今日の情報交換は多岐。雨、風、土、水のことも、先枯れ病(今週ちゃんと調べます)や
生き物のことも。短時間で結構な広範囲の話題を一気に。
今日の統括の生き物系各種コメント
「ミサゴ・・・これがいるってすごいんだぞ」(チヨウゲンボウも今朝見ました)
「広葉樹・・・やっぱりここじゃ難しいよな。2mに育っても枯れる。よそで大きな声で言ってくれ」
「キツネの巣穴・・・鳥の卵は随分食われただろうな」
「ちゃんと森林整備して50年単位でちゃんと植生を見れば、すごいことがわかる。
生物も多様化、植生も豊かになる。こういうことを証明したいな」
広葉樹にとっては過酷な土壌に加え、例年以上に過酷な条件が加わりました。
でも、今年は過去8年で一番少ない降水量。急がなきゃ葉が全て落ちてしまう・・・
9月2日、広葉樹生育「予備調査」的に、671本すべて見てきました。
多い順からコナラ・ケヤキ・ヤマザクラ・ウワミズザクラ・オオシマサクラの5種が全数の9割。
これまでの経緯を記した海岸林ブログ内カテゴリー「広葉樹」はコチラ
http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?cat=18
5月の開葉確認では極めて好成績だったが、葉の状態が非常に悪く、例年以上に6・7月を乗り切れない。
充実した溝切りを経て環境が良くなったクロマツが、真横で青々としているのに対し、
広葉樹は蒸散量を減らすために葉の周りから枯れ、樹種によっては7月に落葉も始まった。
粘土質で多湿の市有林の201本は、葉の変色が酷いものの、枯損は少ない。
2016年10月の最終補植木の生育率は90%以上だろう。
ただ、去年のような上方生長はない。根元径は太くて希望が持てるが。
砂質壌土、排水溝にガマが育つ国有林の470本は、強いはずのサクラ3種が予想以上に枯損。
サクラほどひどくないがケヤキも厳しい。辛うじて・・・という感じ。
この少雨を旺盛に生き抜いたのはコナラ。ただ、去年の上部が枯れて萌芽更新を経たため、
ハイマツのように低く横ばいに伸びている。とても見栄えが悪い。
エノキ50本は全数生存しているものの、2年間上方生長の気配なし、太くもならず。
2016年10月の最終補植木の生育率は、生長不良のものを入れると80%程度。
夕飯の定番、ラーメン「ねぎっこ」で今日を振り返って、
今秋の保育と現場管理を10種類、来春の仕事2種類を考えました。
一人じゃ大変だな。松島森林総合に手伝ってもらおう。
植えて2年は辛抱というのが定番。来年こそ「おがる」といいのだが。
とにかく、この場所で広葉樹は厳しいのは明白。
8月31日、東北電力労組5回目のボランティア実施前日、
研修会で1時間以上説明させていただき、翌日、公募ボランティアの日に参加。
前日から質問がビシバシ。リアクション付き自己紹介する人も多数。
今年も士気が高い。懇親会では息子と同い年の20歳の社員さんが隣に座ってくれた。
思えば、溝切り(排水路づくり)は、植栽が始まった2014年、宮城中央森林組合の現場代理人、
佐々木秀義君と、水溜まりを前にたまたま二人とも鍬を持っていたので、少し空いた時間で
半分遊びで始めました。ニセアカシアの薬剤枯殺も、どこにどう薬剤を塗るといいか、
遊びから始めたものです。
2015年9月、大雨警報が出て宮城で大きな被害があった翌日、力持ちの東北電力労組だから、
一度防風柵を持ち上げてもらうか!と思って始めました。
私にとっても記憶に残る日です。
あの場所に行くたびに「あの時の東北電力労組」と思い出します。
当時はまだSサイズの溝。あれから今に至っては、場所に合わせ、LL、M、Sの三種類を駆使。
苦労した場所がどうなったか、お見せできました。2年半がかりで1haの応急処置を完了。
森林法違反のいわくつき、粘土ばかりの土。長い間多くのボランティアが奮闘。
(余力があれば、まだやりたいことがあるが・・・)
今年取り組んでいるのは、名取市海岸林5㎞の中央部2016年植栽地の一部。楽天スタジアム全体1個分。
先週28日の86㎜の雨で、今年8月は過去8年で最多降水量223㎜に跳ね上がった。今日も小雨まじり。
植栽地の「貯水」は十分。
「今回は豪快な通水式ができるなあ」(しめしめ)
狙ってました。僕なりのこれまでの御礼。
東北電力労組チームは、去年は1m高の草に突入しての下草刈り。
2014年、2016年はその夏で一番暑い日に当たった。
それでも頑張った。さすが地元企業。
仙台トヨペットや、兵庫県庁から宮城県庁森林整備課に出向している方などを加えて約50名。
防風垣50基以上どけ、排水口めざしLLサイズの溝を補修80mと、一部石まじりの場所に新設30m。
指示通り防風垣内のフタモンアシナガバチの巣探し、一つ発見。即、薬剤処理。
硬い土があったけど仙台トヨペットの若い社員たちも頑張った。
掘り下げられず、うまく流れないか・・・と思っているうちに底力を見せた。
雷の音が聞こえ始めた。別チーム40名を率いるオイスカ職員からも電話が入る。
10㎞圏内だな。こちらもバスを移動させ、最短距離で退避の態勢をとった。
雷次第で、時間切れになるかもなあ・・・
午前中から約40名で下刈10m×750m(3,825本分)をやり切り、
夕方の一番疲れているときに、前夜からリアクション力のある東北電力新潟チームが
底抜けに明るい声出し。自然に出てくる声を聞くと仕事冥利に尽きます。
頑張った。間に合った。
声を合図にせきを切ったのは電力の団長さん。事前の段取りがいい。
ガンガン流れてくる。排水口は滝のよう。
みなさんお見事!
みんなどう思ったかな?
下刈を終えた場所を見るのと同様、私はこういう時、快感というか痛快です。
2年後、見違えるような生長を見せるはず。
9月1日ボランティアの日レポート
こんにちは、国際協力ボランティアの中川です。
今日は、9月1日に行われたボランティアの日についてお伝えしたいと思います。
9月1日の天候は雨。そのような中でも約80名のボランティアの方々が参加をしてくださいました。
それでは、1日を振り返ります。参加してくださった方は「あ~そうだったなぁ」と一緒に振り返りましょう。また、今後ボランティアに参加予定の方は「そのようなことをするのか~」と参考にして頂ければ、と思います。
朝9時に全員が集合し、企業・団体紹介と1日の流れの説明が行われました。
ボランティアさんの中には、佐渡から来てくださっている方もいて、驚きました。
その後、激しい雨のためすぐに作業に移るのではなくて、育苗場と海岸林見学を先にすることに。
育苗場は名取事務所より少し内陸側にあります。
ボランティアさんは初めて見るマツの苗に興味深そうなご様子でした。
実際に触ってみたり、吉田さんに積極的に質問したりしている姿が印象的でした。
雨が弱まってきた午前10時30分ごろに作業が始まりました。
今回は吉田チームと浅野チームに分かれて、ツルマメ除去と草刈りの作業。ひとりひとり鎌をもって行いました。
最初は「ツルマメってどこ?全然見つけられない」と思いましたが、何度もボランティアに参加してくださっている
リピーターさんが積極的にとっている姿を見ながら、私も一生懸命探しました。
ちなみにあとから聞いた話なのですが、ツルマメは上に引っ張るようにとるのではなく、横にさっと流すように(?)すると、上手に取れるらしいです。これは、次回の私の課題ですね笑。
お昼休憩をして午後の作業開始。
午前中の作業の続きだけではなく、つぼ刈りと溝切りも行われました。今回は残念ながら、
雷のため15時半ごろに作業終了となってしまいました。悪天候の中での作業だったにも関わらず、
ボランティアさんからは文句もなく、最後の片付けまで積極的に行ってくださいました。
そのおかげもあり、ケガ人がでることもなく、円滑に終了することができました。
皆様の積極的なご協力、本当にありがとうございました。
私は、初めてボランティアの日に参加したのですが、大勢のボランティアさんのご協力があるからこそ、
活動ができているのだな、と改めて実感しました。
次回参加するときは、今回よりも積極的にボランティアさんとお話ができるように心がけたいです。
今回は本当にありがとうございました。また、再来週お会いできることを楽しみにしています。
ちなみに今回の除草面積は…
浅野チーム:2.0ha、クロマツ12,000本分
吉田チーム:0.75ha(10m×750m)、クロマツ3,825本分と
溝切りは約50人でLLサイズ溝 110mでした。
将来のマツの可能性
こんにちは、国際協力ボランティアの中川です。
先日、吉田さんからある課題を指示されました。
それは、、マツの落ち葉・枝などの事例を整理してほしい、というものでした。
なぜなら、現在すくすく育っている名取市のマツが成長し、たくさんの落ち葉が落ちた時、間伐材が発生した時、そのまま林内据置にしてしまうと土壌が富栄養化してしまうことが考えられるからです。そこで現在の利活用の現状を調べるという試みなのです!「一部地域ではバイオマス発電に利用されている。たばこ農家の苗床や、川の浄化に少量使われている。燃料としては早く燃え尽きてしまい、堆肥としても使いづらく、事業規模では成立していない」と聞きました。
調べてみると、、思っていた以上に事例だけはたくさんありました!!
昔は主に燃料として活用されていたそうですが、現在は燃料としてだけではなく、松野菜・松酒・松葉茶・サイダーといった食料・飲料品からシャンプー・薬といった日用品にまで本当に幅広く活用されているのです。他にも松脂(マツヤニ)の成分から、粘着剤、香料、滑り止め、紙の添加物にまで使用されています。
ちなみに、松野菜は和歌山県美浜町で作られているもので、マツの枯れ葉と籾殻が発酵されてできた、松堆肥から栽培されたトマト、キュウリ、イチゴなどのことを指しています。このように、一部地域ではマツは堆肥としても活用されているのですね。一方、松葉茶やサイダーは、マツを香料として使用されています。
驚いたことに、海外でもいろいろな国で使われているのです。例えば、韓国の松餅(ソンピョン)と言われる、マツの香りのついた蒸し餅は、お盆の時期に食べる風習のあるお菓子だそうです。他にも、フランスではマツヤニ入りのキャンディーが販売されています。フランスでは昔から、マツヤニには肺の浄化作用がある事が知られているそうです。
このように、マツは様々な面をもっており、マツの特徴を活かすことで有効活用の可能性はぐんと広がるように思いました。
そして、意外と(?)マツは私たちの生活に身近な存在なことがわかりました。
さっそく吉田さんに整理して報告しなくては笑!
本数調整伐までやってこそ及第点
本数調整伐遅れの海岸林は、まったく珍しくありません。
慣習がないことも、予算がないことも大きな要因です。
しかし今や、「本数調整伐は当然実施すべき」というのが潮流だと考えています。
伐り焦ってもいけない。しかし伐り時を逃して遅れると、あとは悪循環が待っている。
一方、「今こそ、または、今こそ伐り時」という現場情報を探し当てること、
訪ねることは、我々の限られた時間では限界があるのが、正直なところです。
しかし、それでも見る目を訓練しようとコツコツ探してきました。
副次的に、植えて数年で松くい虫被害に会った場所にも出くわしました。
本数調整伐は歴史的蓄積がない技術。
試験は元より、事業規模の実践事例は極めて稀。
宮城県では前例もなく、今後の基本方針も検討途上です。
伐ったら伐ったで、その膨大な材ををどう処分するのか。
我々だけで出来ない大仕事が将来待っています。
それでも我々は、色々な人の協力を得ながら、やってのけなければならない立場。
名取ではいつ頃、伐ることになるのか、薄っすらしか見えません。しかし案外早いはず。
本数調整伐まで辿り着いて初めて、このプロジェクトに及第点を出すつもりです。
同じ手掛けるなら、最強の海岸防災林を作るのが我々のミッション。
全国にも地元にも知己は増え、アドバンテージはありますが、
関係者一同、一層研鑽に努めなければなりません。
石川県のなが~い海岸林
7月末の休日、福井出張のため、仙台をIBEX機で出て小松空港へ。
着陸前、長ーい加賀海岸全体を俯瞰。
海岸林は存在感は保っているが、林帯幅がやや狭く見えた。
かつての海岸林は、工場や高速道に代わった場所もある。
海岸浸食は上から見ても明らか。浜と生活圏の距離は十分とは言えない。
空港からは、寄り道をひたすら繰り返しながら北上。
木製ではない防風柵すら、朽ちて破られる冬の突風。
防風林・砂防林としてクロマツ純林を前方に構える意義は高い。
大雑把に言って、海側最前列は県有林、内陸側は共有・市有林と見えた。
松くい虫の大きな被害を受けた爪痕が残っている。
海岸線の距離・海岸林面積に比べ、植付は小規模ながらも堅実に進められ、
植付後の活着率は高い。石川ならでは?の間伐材保湿用パットを見ました。
据え付け作業も簡易で、コストも高いはずはなく、海砂上の造林には極めて有効かと。
九十九里や遠州灘と同様、全長100㎞以上に匹敵する日本有数の長距離海岸林。
宮城南部の倍以上の距離。気が遠くなる。全体を目配せ、管理するのは容易ではない。
以前、ブログを読んだ石川県庁の方から、松の意義を記すための看板について
問い合わせをいただいた。住民・市民とはどんな関係ができているのだろう。
地元理解がほとんどない浅野さんと私の限られた眼で、
案内人なしの付焼刃的視察、いわばドライブでは誤解する可能性もあり、
かえって見ない方がイイのではと思うこともある。
それでも折角の機会。見ずにはいられなかった。
9月のボランティア作業予告
8月25・26日、小雨は降るし、気まぐれで日が出て湿度が高いなか、
60余名のボランティアが奮闘して下さいました。
最近、微妙に地元率が増えた感。嬉しい。
地元紙「河北新報」に、高田松原の草との闘いの現状が報道されました。
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201808/20180826_33009.html
場所は違えども、同じ目的。シンパシーを強く感じます。
我々の現場には、2社の林業プロチームのほか、400名以上のボランティアが、
70ha・35万本のマツを守るため、復興のために来訪予定。
慣れた人も多いけど、初めての方が半数。
(もちろん名取市海岸林再生の会のプロチームも、10万本の育苗で頑張っています)
9月20日前後が、下草刈り完了の大目標。
上半期順調であったことと、今年の名取は雑草にも厳しいほどの少雨だったことから、
例年よりも多少気楽。あまりの草に笑ってしまうのが例年のお盆休み明け。
そうは言っても、やはり我々の目の色が変わる9月です。
9月の作業予告とすれば、これまでブログで何度も紹介し、お察しの通り
1.ツルマメの抜き取り
正確に言えば、この時期は根の張りが旺盛になっているので、
抜き取りというより、草刈り鎌で土ごと根ごと刈り取る。
また、状況・場所次第では、他の草も含めた「つぼ刈り」も。
(マツの一定周囲、必要な範囲限定で草刈り。×全面刈り)
2.溝切り
多湿改善のための、排水溝づくり。(冬でも続けたいぐらい)
詳しくは、過去のブログをご参照ください。
プロ、ボランティア、全員が安全に乗り切れるよう、精一杯頑張ります。
海岸浸食 ~石川県羽咋市千里浜~
少し遅くなりましたが・・・
7月28日、「学校の森」全国子どもサミットで福井に向かう前に
この機会を活かして10年ぶりの加賀海岸を浅野さんと見学。
仙台空港からIBEX機で小松空港へ。機窓から俯瞰。
日本全国の沿岸は、海岸浸食の時代となって久しい。
1年で1m波打ち際が後退しているというのが大雑把な日本の姿。
加賀海岸はその分かりやすい一例。
千里浜には全国唯一、海を車で走れる砂浜がある。
海岸林を仕事で担うことになるなど思っていなかった10年前、
家族でここをドライブをした。その写真は自宅の洗面所に今も貼ってある。
悠々と運転出来た砂浜が、いまは気を使いながら車とすれ違う。
かつての砂丘は、いまや波浪で削られ、小さな崖になっている。
将来、ドライブは禁止され、海岸林が波に削られる時代も来るかもしれない。
名取の海岸線は閖上漁港の突堤の影響で大きな後退を見せていないし、
被災地全体の居住地区は海から遠くに移転して安全を確保しているが、
実は岩沼市以南は、復旧された防潮堤の裾近くまで波が迫る浸食の影響を受けている。
太田猛彦先生の著書「森林飽和」を思い出す。海と山はつながっている。
海岸浸食の原因は、その地その地の複数の要素も絡み、対策は一筋縄ではいかない。
10年前の砂浜とあまりに違う姿にショックだった。
大都会の海岸林 ~千葉稲毛海岸~
7月の休日、一度行きたいと思っていた千葉市稲毛海岸にフラッと。気楽に。
海水浴場、ヨットハーバーがあり、ウインドサーフィンのメッカ。
いい公園。いい憩いの場です。初めて来た海辺を楽しみましたが、
やっぱりオタクはオタク・・・
モナコ公国に続いて造られ、日本では初、総延長4.3㎞の3つの人工海浜。
初めて知りました。その是非に関する意見は今もいろいろです。
地元首長の発表では、アメリカ西海岸のサンタモニカ、サンフランシスコのような
商業施設と一体化した海辺の利活用をイメージしているようです。
「海辺とまちが調和するアーバンビーチ」
「都市の海辺で過ごす新しいライフスタイルの提案」
気楽と言っても、松林に関して少しは調べたのですが、資料が少ない。
という事は、ここは海岸防災林ではなく公園緑地かな?
行って驚いたことが2つ。
海岸浸食されて、人工浜の海水浴場は一つを残して閉鎖になったようです。
ですが、残る一つの海水浴場も風前の灯。最前線のマツは生きていくのは難しいでしょう。
松林と浜の近さに驚きました。憩いの場がなくならないよう祈るばかり。
海辺のマツの枝打ち・・・初めて見ました。なんで?
「道路から海が見えない」という理由だそうです。
湘南海岸防災林と同様、ここの松林は、公園内人工浜の砂が、春先の強い南風によって
飛砂とならぬよう、食い止めてきたはずですが、砂がない今は用済みなのか。
たとえ保安林ではなくても、人知れず防風林・防災林の役目をしていたことは、
残念ながら、各種の発表でも顧みられていない。公園緑地と防災林は扱われ方が大きく違う。
しかし、それにしても人工〇〇というのは難しい。
人間の思うようにはならない。