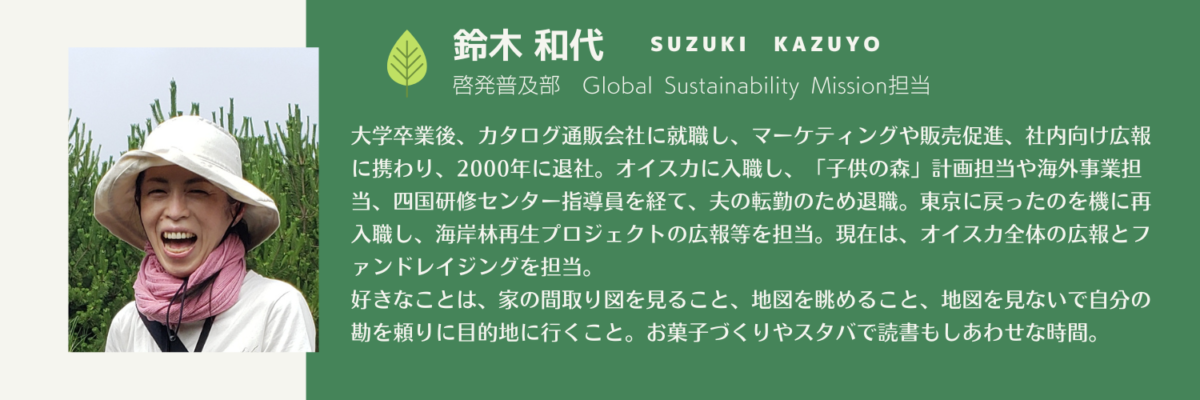啓発普及部の鈴木です。
3月28日に発生したミャンマー大地震。
オイスカ関係者の無事は確認できていますが、現地の研修センター修了生の安否は現在も確認中です。
いまだに被害の全貌がわからず、亡くなった方は日に日に増えている状況。
この2週間は、通常業務をほぼ停止して、ミャンマーを支援するためのクラウドファンディングの立ち上げなどをしてきました。発災3日後から共有された現地からの報告では、連日、数十枚の写真が届き、とにかく、今、できることをスタッフ全員で協力して必死で支援にあたっていることが伝わってきました。自分たちが疲れていることも忘れ、被災者のためにとにかくできることをしているようでした。そして、報告の最後には必ず「がんばります」の言葉。
そんなミャンマーのスタッフたちを応援したい。その先にいる被災した何千、何万人もの人たちを支援したい。そんな気持ちでブログを綴っています。
 瓦礫撤去をするオイスカスタッフ(3月31日)
瓦礫撤去をするオイスカスタッフ(3月31日)
「ミャンマー」「震災支援」で思い出すのが、ミャンマーの人々からいただいた東日本大震災支援のための寄附のこと。「東日本大震災の時に、オイスカが支援した台風災害の被災者たちが、みんなで出し合った募金を遠く離れたオイスカの研修センターまで、わざわざ持ってきてくれたんだよね。この時は本当にびっくりしたし嬉しかった」と、ミャンマー事業担当の藤井さんが語っていたこと。
その時のことを綴ったブログがありましたので、紹介します。
<2013年7月8日 「海岸林再生プロジェクト」サイトのブログより(執筆者:吉田俊通)>
ミャンマーから非常に大きな支援をいただきました。
世界最貧国と言われることもある国からの支援で、現地の貨幣価値として、100万円を越える大金です。
金額もさることながら、この協力の背景をご紹介させていただきます。
1995年に着工したミャンマー農村開発研修センターに、当時私は経団連自然保護協議会ミッションの随行員としてヤンゴンから丸2日かけてたどり着きました。一面の「土漠」でした。
国柄・人柄がとてもよく、すぐに「ビルきち」(ビルマが大好きな人)になりました。
あの国からと思うと、心から嬉しく。
駐在代表の藤井啓介氏(東京農大卒、駐在歴7年)からのメール、 ほぼ原文を使用しました。
彼の文末の言葉、とくに読んでいただきたいと思います。
オイスカミャンマー農村開発研修センターで長い時間をかけて集めた寄附金を、レートが良くなった今、訪日する農業研修生4名に託し、受け取りました。 ここに至った経緯を紹介します。
(*以下、駐在代表の藤井啓介氏(ミャンマー駐在歴7年)からのメールのほぼ原文を掲載)
寄附に協力してくれたのは、センタースタッフ、研修センター卒業生、イェサジョ郡の村々からの寄附(普段オイスカ・ミャンマーが事業で対象としている村々の人達)、パコックやイェサジョの市街地にあるオイスカの商品を扱っている商店、政府関係者等からでした。そして、今回の寄附金を集めるのに最も重要な役割を果たしたのは、他でも無い我々のセンターのスタッフでした。
 後列右から4人目が藤井
後列右から4人目が藤井
3月11日のニュースは、ミャンマーでも発生直後から大きく取り上げられ、自分も日本人だからという事で、スタッフや地元の知り合い等から、自分の家族や知り合い、そしてオイスカ関係者の安否を心配する声を連日掛けられました。
その後、私自身も日本人として胸が張り裂けそうな思いでいる時、あるスタッフが私に今回の災害に対して何か自分達にもできないだろうかという話をしてきました。
その日の夜の定例ミーティングの場で私は彼らに以下の様な話をしました。
「今、日本で大変な災害が起きた事は皆さんも承知していると思います。今回は、自然災害の多い日本でも未曽有の大災害と言える規模になるのは確実でしょう。皆さんの第2のふるさととも言える日本の事だから皆さんが心配してくれているのは私もとても有り難く思います。そして、皆さんはあの2008年のサイクロン・ナルギスの被害で多くの善意を日本からも受け取ったのを覚えていると思います。その時の恩返しという意味で、今回の災害に対して皆さんが何ができるかと私は聞かれたが、私からは具体的に何をしなさいという指示はしたくないです。ただ、皆さんの想いが、そして何らかの行動が被害に遭われた多くの日本人を必ず励ます事になると思います。被害に遭われた方々にとって、今必要な支援は多岐に渡ると思われます。その方達の緊急、そして復興に確実に活かされる支援であれば、その額や量が多い少ないは問題では無いのです。何ができるかと考えているよりも、皆さんの想いを今からすぐに行動に繋げたらどうだろうか」
その後、彼らが自分達で自主的に寄附を集めはじめました。
スタッフ自身からの寄附のみならず、普段私達が支援をしている周辺の村にも支援を呼びかけていったのです。普段は支援される側の村人達が、スタッフの呼びかけに応じそれぞれが少ないながらも善意の寄附をしてくれました。
そして、村人以外の普段オイスカと関係のある人達、そして今はセンター外に住んでいる研修生OB達も続々と寄附の呼びかけに応じてくれました。
また、2008年に私達がサイクロン支援活動をした地域の人がわざわざ遠いセンターまで寄附金を持って来てくれた事もありました。
「あの時にオイスカ、そして日本の方から受けた恩を忘れた事は今まで無い。
今回は自分達に支援を届けてくれた日本が大変だと聞いて、どうしても届けたいと思って持ってきたんだ」
と言って、皆で集めた寄附金を大事に持って来てくれました。
上記の様な額が、それも他国の災害に対する寄附金として集まったというのは、ここミャンマーでも恐らく異例の事だと思います。
今回の出来事を通じ、これまでの私達の活動の意義が実はここにあるのではという思いを強くしました。
つまり、私達が取り組んでいる国際協力活動とは、一方通行のやり取りでは無く、双方向の絆を深めるのに大事な役割があるのだと思ったのです。すぐに目に見える成果と言えないかもしれないが、もっと大事な精神的な繋がり、お互いを思いやる関係を私達オイスカとミャンマーの人達はこれまでの取り組みを通じて築いてこれたのだと思いました。
これからも、私達オイスカ・ミャンマー事業はこの大事な絆をより多くのミャンマー人と築き、そして深めていく事ができればと思っています。
言葉は通じなくてもまごころは通じる。私たちNGOができる国際協力の事業規模はODAに比べれば微々たるもの。でも、NGOにしかできない国際協力が「人」と「人」をあたたかな気持ちでつなぐこと。
このミャンマーからの寄付は、そんなことを思わせてくれるあたたかなエピソードです。
ミャンマーが支援を必要としている今、今度は私たちがお返しする番です。