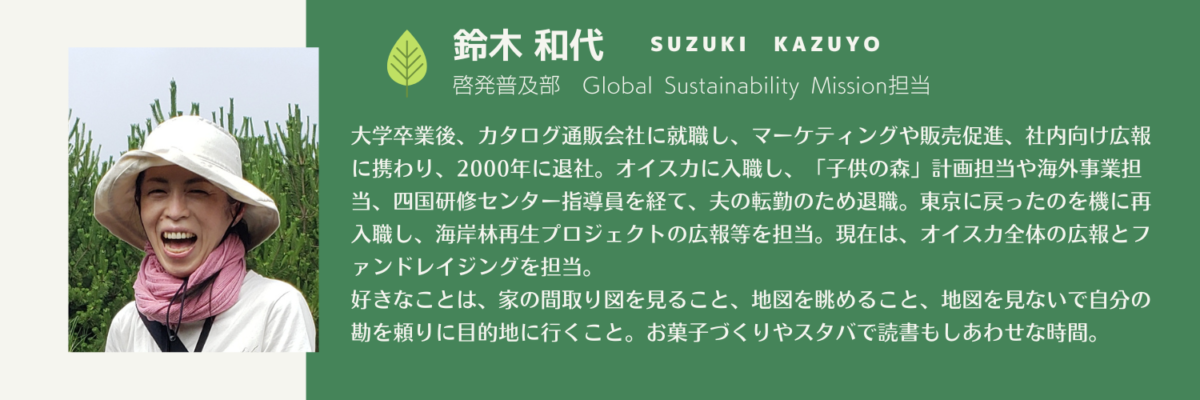啓発普及部の鈴木です。
1月があっという間に過ぎ去り、もう2月も半ば。
「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」とはその通り。
長年お世話になっている森林環境学、森林水文学、治山・砂防学が専門の東京大学名誉教授 太田猛彦先生の講演会「気候変動と防災になぜ森林? -国内外の森林保全・再生の意義を深く考える-」
を1月21日(火)に開催しました。
オンライン参加をメインに、会場参加とあわせて121人もご参加いただき、昨今の環境の変化に対する森林への注目の高さを感じました。
講演会前日、先生から送られてきた講演用パワーポイントのスライドは269枚!先生の熱意と森林に対するひとかたならぬ思いを感じました。
83歳という年齢を感じさせない90分間のご講演、単なる「森林」に留まらない地球スケールの3億6千年前からの悠久の歴史、地球温暖化を引き起こす原因についての持論など、目の前の「木」や「森」に留まらない展開に、ただただ感心しました。
正直なところ当日は司会役もしていたため、時間管理、質問内容の把握などの運営にも気をとられ、ご講演の詳細が頭に入らず、整理しきれていませんでした。ホームぺージに掲載するレポートを作成するためもあり、あらためて当日の録画を聴き、パワーポイントのスライドを見比べながら、自分のペースで理解を深めてみました。
当日、聴いていたより、話の展開や根拠としていることがさらに興味深く、おもしろい!
講演のポイントをいくつか紹介します。
○3億6千万年前に森林が誕生した地球の歴史からひもとく
地球の環境は3億6千万年前に誕生した森林がつくりあげてきた。大陸の沿岸部分にしかなかった森林が、植物の進化により乾燥に強い種子植物が生まれ、大陸内部に拡大。植物の蒸散作用により大陸内部にも雨を降らせ、気候を安定させてきた。森林が炭素を固定し、地下に閉じ込めてきた。
産業革命後、森林を縮小させ、化石燃料や地下資源を再び地上に戻し、地球表面に二酸化炭素と廃棄物が蓄積。地球の進化の方向に逆行している。
○生活に必要な「燃料」からひもとく
かつての自給自足の農耕社会は地上資源を活用し、廃棄物はすべて自然界の中で処理され、健全な炭素循環が維持されてきた。人口増加によって維持が難しくなった。
現代の工業化社会は、地下資源を利用することで人間活動が拡大したが、二酸化炭素やプラスチックゴミなどの廃棄物が地球環境そのものに影響を与え始めた。地下資源を使えば無限の成長が可能かと思われたが、大気中に二酸化炭素が蓄積して地球温暖化という問題が発生。地球の容量の壁にぶつかった。
地下資源を使うことがいいのかどうか考え直す必要がある。
○日本の森林についての法律からひもとく
江戸時代の日本の人口3000万人(これは世界人口の20分の1~30分の1)の生活を支える資材や資源は「木」。江戸時代に人口が爆発的に増加する以前もやはり「木」に支えられての生活。人口爆発によってさらに山に木がなくなり、人家に近い里山ははげ山ばかり。森林荒廃がピークに達し、雨が降れば山崩れ。このような背景があり、明治時代中期の1897年「森林法」が制定。主な目的は「治山治水」。戦前、戦中、戦後と里山から奥山まで「拡大造林」が続いた。
高度経済成長期を迎え、日本人がだんだんと森から離れ、木を使わなくなり、資源は地下資源に頼るように生活が変化したのに伴い、林業が徐々に衰退。林業の振興と、都市住民からの要望を意識して、水源林の確保や保健・休養、山地災害防止などの森林の「公益的機能」を盛り込んだ「林業基本法」が1964年に制定。
昭和後期から平成にかけて環境問題が顕在化し、林業基本法では対応できなくなり、2001年に「森林・林業基本法」が制定。「森林・林業基本法」は木材生産や地球環境保全機能、生物多様性保全機能なと8つの機能を含む森林の多面的機能を重視している。
このような変遷をたどってきたが、「林業基本法」が都市住民の要望を汲み、水源涵養などの公益的機能を盛り込んだように、世界の森林のない島しょ国も乾燥地の国も豊かな森林が育つ日本に対して森林の適性な管理を要望すべきではないか
まだまだ書ききれませんので、興味を持たれた方は、ぜひ講演内容のレポートをご覧ください。
2025年2月13日
講演会「気候変動と防災になぜ森林? -国内外の森林保全・再生の意義を深く考える-」【1/21実施レポート】
講演はアーカイブ視聴ができます。こちらからご覧ください。
今回の講演は、太田先生のご著書『森林飽和』(NHKブックス)をベースに構成されています。ご興味のある方は本もご覧ください。
狩猟採集をしていた縄文時代までは、日本人は森とともに暮らしていました。獲物は森に棲んでいるのですから・・・ 稲作文化が定着した弥生時代から、人間は森から出て生活するようになり、特に現代は都市部で生活する人々は森から離れ、わざわざ出かけていかなければ森と親しむことはなくなりました。日本は豊かな森林が育つ、世界でも稀有な国であると、先生のお話の中にありました。温暖化防止や世界の気候の安定、生物多様性を守るためには、適切に管理された森林の木を積極的に使い、循環させていくこと。さらに、世界中でもともと木のあった場所には木を植え戻すこと。
今、日本に生きる私たちは、世界の気候の安定と生物多様性保全のために重要なポジションにいるのです。
まず、個人で身近にできることは、「FSC認証」のついた製品を使うことでしょうか。そして、オイスカとして、世界各地の地元住民の暮らしを守るだけでなく、世界の環境を守るために森づくりを積極的に進めていく重要性と緊急性を感じています。
「若い人を含めて、国民全体で森林について考えて欲しい。勉強して欲しいと願っています」と結ばれた先生のお言葉の重みを実感しています。