海岸林再生プロジェクト担当の吉田です。
「世間の想像以上に、災害はアジアに集中している」
林野庁の方との情報交換での、この言葉が印象に残りました。
この秋、海外現場スタッフのECO-DRR研修を受け持つことになり、
準備に入りました。数ヵ国の入国を成田で受け止めながら、
日帰り温泉で休憩したあと、早速、空港周辺から視察を考えています。
千葉県は農業生産高が国内3位ですが、成田空港から30分の場所に、
数百年の洪水と水防のまちづくりの歴史がありました。
中でも布鎌(千葉県栄町の布鎌地区)輪中は、全長約5㎞×最大幅約2㎞の規模。
「輪中※1」は意図的に作られたものなのかどうかや、
堤内の世帯数、面積など調べてもはっきりしませんでしたが、
その存在を知った次の日は休日。即行ってみました。
 川下側から撮影されている布鎌輪中の様子。右上は利根川。(リンク:千葉の県立博物館デジタルミュージアム 空からみた千葉県)
川下側から撮影されている布鎌輪中の様子。右上は利根川。(リンク:千葉の県立博物館デジタルミュージアム 空からみた千葉県)
ここは古代にさかのぼると陸地ではなく、古鬼怒湾(こきぬわん)という入り江。
1,000年前は万葉集で「香取の海」と詠われました。
徳川の世になると、江戸を含む南関東の水運、新田開発、水害対策を
兼ねた「利根川東遷」事業が関東代官伊奈忠次から3代で行われ、
さらに、田沼意次で有名な印旛沼※2干拓があった場所。
「日光が大雨なら利根川下流は洪水」
と言われるほど洪水被害の大きな地域でした。
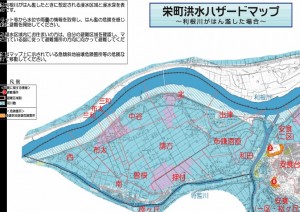 栄町洪水ハザードマップ 「布鎌輪中」拡大図より。近年は揚・排水施設の充実もあり、洪水はなくなっているようです。ただ最悪の場合、ほぼ全域がかつてのように2~5m水没。紫色は5m以上。
栄町洪水ハザードマップ 「布鎌輪中」拡大図より。近年は揚・排水施設の充実もあり、洪水はなくなっているようです。ただ最悪の場合、ほぼ全域がかつてのように2~5m水没。紫色は5m以上。
利根川河口が東京湾から銚子に換わり、もともとW状だった巨大な沼は、
印旛沼として3分の1になった干拓・新田開発でしたが、低湿地帯ゆえ、
昭和30年代まで、利根川から印旛沼に「逆流」する大小の洪水を繰り返しました。
「日光水」といい、周辺で雨が降ってないのに、村祭りの途中から突然押し寄せ、
天井裏まで浸水。数週間引かず。腰まで水に浸かって稲刈り。
「飲み水」に一番困った…という記録もあります。
まず、印旛沼と接する集落に行こうとすると、滞水頻度の高さゆえ、
4m幅の農道が細く、荒れ気味の舗装も多かったため、
軽自動車で来なかったことを後悔しました。
「利根川東遷」以降昭和にかけて行われてきた治水事業が実り、
新しい家やアパートも増えたと見えましたが、
印旛沼と利根川を結ぶ長門川沿いは、葦区画と、
盛土した宅地がモザイク状に点在していました。
布鎌輪中では、自然堤防の上や下と道を変え、車でほぼ3周し、
帰ってからもう一度調べた結果、最初から意図的に輪中として作ったのではなく、
自然堤防を活かし、補強しつつ、結果的にそうなったのではないかと理解しました。
古くから住む世帯は、自然堤防に寄り添うように盛土も加えて母屋を建て、
防風と洪水の勢いを緩和するために屋敷林で囲っています。生垣はマキ。
自然堤防両側の水防林も屋敷林も、やはり竹が目立ちます。
 自然堤防の上。左は将監川に面した水防林としての竹林、右は屋敷林兼水防林と見えた。
自然堤防の上。左は将監川に面した水防林としての竹林、右は屋敷林兼水防林と見えた。
このほか、ケヤキ、エノキ、シイ、カシなどが、洪水と風の方向に配置。
さらに高い盛土の上に貴重品や食料の備蓄場所の「水塚※3」(みづか)を作り、
避難用の舟を保管している様子も見てとれました。
 手前の池を掘り上げた土で盛土にしている。池の位置は洪水の水流方向を意識し、屋敷林の木々は、風と洪水を意識して配置するらしい。
手前の池を掘り上げた土で盛土にしている。池の位置は洪水の水流方向を意識し、屋敷林の木々は、風と洪水を意識して配置するらしい。  左の建物は「水塚」。近年は洪水の可能性が減ったことや、維持できないことなどから取り壊され、昔からのものは70軒程度しか現存しない。
左の建物は「水塚」。近年は洪水の可能性が減ったことや、維持できないことなどから取り壊され、昔からのものは70軒程度しか現存しない。
一方、すぐ横には、水がなくて困った下総台地があり、台地上には古墳が多数。
帰宅してから知ったのですが、栄町の台地上には、揚水して四方に農業用水を
配分する「円筒分水工」がひっそり機能していることも知りました。
国際協力をやっている人なら多くが知っている「上総掘り」も千葉県発祥。
これから私が相対する海外の現場は、なにがどう参考になるのかわかりませんが、
まず私自身は、日本のこともどんどん吸収したいと思います。
※1 輪中(わじゅう)…江戸時代、水災を防ぐため一個もしくは数個の村落が堤防で囲まれ、水防協同体が形成されたもの〔広辞苑〕
※2 印旛沼(いんばぬま)…千葉県北部にある湖沼。もとはひとつの巨大な沼だったが、干拓により北印旛沼、西印旛沼に分かれた
※3 水塚…洪水の際に避難するために屋敷内にあらかじめ築き上げた高地。関東地方低地部にある。〔広辞苑〕

