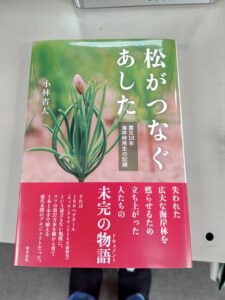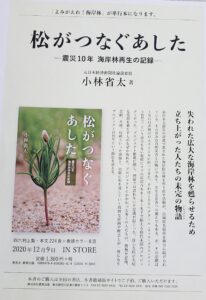書籍「松がつなぐあした」PV(3分)など、動画4本一気に公開!
コロナ禍で名取に行きたくても行けない多くの方たちに、見ていただきたい! よかったら、お知り合いにご紹介ください!
①書籍「松がつなぐあした」紹介動画 (3分)
*東京本部、鈴木さん・浅野さんの手づくり!! 最後の一言と表情が、日頃の小林さんらしい・・・
②海岸林これまでとこれから (13分半)
*10年を記録してくれたプロカメラマン塚本公雄さんの手で、次の10年を念頭に置いて作成しました。オイスカ緑化技術参事の清藤城宏先生が語っている「10年前の調査で根周りが小さかった」と話す場面などが、これから延々続く「本数調整伐」をする理由と考えてください。最強の海岸防災林めざし、数10年かけて5,000本/haを約1,000本/haに減らします。
③ある日の海岸林ボランティア(9分)
*同じく塚本さんの制作です。コロナ禍のなか再開した9月~10月の様子を中心に撮影しました。
④ドローン撮影「2020年9月 名取市海岸林復旧状況」(8分)
*建設業の三立重建さんの協力で制作。今年11月の各年度植栽地の生長モニタリング調査速報値などを紹介しています。
吉田です。オイスカタイのブログによると、向こうは南部ラノーン県のマングローブのモニタリング調査ををやっていました。インドネシアもジャワ島北岸各地で、同じことをやっているはずですが、名取でも。
こちらは、名取の2014年初植栽以降の調査報告集 (*2020年度は報告書作成中。来年3月頃公開)
オイスカ緑化技術参事の清藤城宏先生は、海のこっちで調査結果をもとにCO2固定量の算出をサポートしています。今回はタイでは初めての調査。海岸林よりも先に、2008年からタイ南部のマングローブを支援いただいている住友化学・労組の植栽地(合計250ha以上だったと思います)をサンプルに、試験的に調査を実施しました。「初めてだから不慣れだし、すごく人手がかかることがわかったけど、もっとしっかり調査したい」と駐在代表の春日さん。
オイスカタイブログ:「マングローブ植林地で計測 ~どこでも樹高計測器~」(10月22日)
いつかGIS(地理情報システム)ですべてわかるようになるのでしょうけど、昔、足で稼いだ計測は、重要であり続けるはずです。過去は計測できないでしょうから。
吉田です。そもそも海岸林ブログは、嫌々始めたというのが正直なところでした。
書き始めたのは、オイスカの元同僚で、その後、今治FCの運営にも参加し、スポーツによる地域振興などを専門とする大阪成蹊大学教授の菅文彦さんのアドバイスで始めました。今日で震災から3,564日。ブログは2,358回目。半信半疑で始めましたが、支援者の皆さんへの状況報告に有効だとつくづく思うので、これからも続けます。
オイスカでもっと続けているのが、オイスカタイ駐在代表の春日智実さん。私の社会人人生の最初の後輩です。
オイスカタイブログ:「タイの田舎やタイ人の暮らし、どうでもいい日常のつれづれまで」
彼女は東京本部、四国研修センター、青年海外協力隊でスリランカ駐在ののち、2002年に、私が上野動物園に寄贈される2頭のゾウの調整で出張する同じ日にタイに着任しました。以来18年、駐在代表として「天才としか思えない」(タイ政府天然自然環境省ラノーン県・パンガー県マングローブ責任者)と言われる働き。もちろん、名取にはタイのスタッフを伴い、何度も来てくれてます。東京本部海岸林チームの林久美子さん、鈴木和代さんとも、20年以上の同僚です。
春日さんとはLINEでも繋がっているし、彼女のブログはずっと読んできました。オイスカタイと我々は共通点が多い。見習いたいことばかり。励みにして頑張りたいと思います。タイはマングローブだけで2,000ha以上再生させたんですよ。
「口下手な漁師と生きるための釣り」(1999年のマングローブ再生開始前を知る村人への、最近のインタビュー)
ここまでのコロナ禍の影響
吉田です。今週は在宅勤務で、あっという間に毎日が過ぎてゆきます。
タイトルに対する結論として、今年必ずやると計画したことはやり終え、今年も結果を出せたと考えています。東京本部が動けなくても、名取事務所の佐々木統括を筆頭に、盤石の体制で雇用を維持し、名取市海岸林再生の会、宮城中央森林組合、松島森林総合の実行力が炸裂したと思います。そして、追加工事分を含め、海岸林再生プロジェクトとしての植栽は完全に終了し、確実な育林作業を継続しています。
残念だったのは、ボランティアの受け入れが例年比の15%程しか出来なかったこと。再開した後、今まで1度に100人以上受け入れるなどしていましたが、定員50人に減らしました。雨にも祟られ、初の雨天中止もありました。残念そうに帰っていく女子高校生のことが、忘れられません。
今年は明らかに少雨でした。上半期のボランティアが中止となっても、その少雨のせいか、ツルマメの生長が異常に遅く助けられました。最高レベルのツルマメ繁茂500m×10mの集中地帯を引き抜きに行ったのは、ボランティアを再開していた10月上旬でした。まだ来年、予断を許しませんが、これまでのボランティアの努力でツルマメを駆逐しつつあるのかもしれません。
もし、コロナがなければ、排水溝LLサイズ(上100㎝×下50㎝×深70㎝)を最低でも1,500mは掘っていたことでしょう。11月のボランティアで50m、香川県立高松北高校の生徒さんで250mは掘りましたが。こればかりはやり残した感があります。でも、また来年やればいい。
これまで10年で270回、約35,000人に聞いていただいた活動報告会のチャンスも相当失いました。ですが、マルエツ労組60名や、オイスカ高校50名をはじめ、林野庁主催の第58回治山シンポジウムで話題提供の機会ををいただき、700名の専門家に情報をお届けできたのは光栄でした。
そもそも10年前、このプロジェクトを立ち上げた直後、様々な方にアドバイスを求めて歩きました。その中で、今もオイスカ本部でボランティアをして下さっている河野さん(元国際協力銀行理事)から、「吉田さんにとって、このプロジェクトの危機って何ですか?」と聞かれました。「考えられる危機を念頭に置いて、仕事を進めてゆくのがよい」と助言いただきました。その時考えた4パターンを常に忘れず、危険の芽は未然に防ぐのが私の仕事でもあったと思います。4パターンとは、①吉田の不祥事・不測の事態、求心力喪失など吉田ネタ、②チームの空中分解・仲違い、③オイスカそのものの危機、④火山噴火やまた津波が来るなどの天変地異。かなり、重要なアドバイスですから、かなり真剣に受け止めました。
その一環で、私がいなくなることもあり得るということを前提に防御網を敷きました。つまりは人材育成です。私の後釜という「点」だけでなく、取り巻く外部の皆さんを「面」的に考えて実行してきました。気が付いたら、多士済々、想像以上の大きなチームになっていました。
さすがに、ウイルスなどイメージできませんでしたが、当初から危機管理を「面的」にも考えたのは良かったと思っています。つまり、私がいなくても仕事は進むということです。また、とくに支援者など、関わる皆様にとって「オーナーシップ」を感じられること、つまり「自分事」と考えてもらえるよう工夫し、一同で努力しました。
今年はさすがに、収入も落ち込み、補正予算を組まねばならないか・・・とこの前まで思っていました。ですが、その必要はないかもしれません。総じて言うと、今のところ、影響を最低限に食い止めることが出来ていると思います。多くの皆様にあらためて御礼を申し上げます。引き続き、抜かりなく頑張ります。
第2次10ヵ年計画では「本数調整伐」という未知の難関が待っています。ですから、第1次の達成感や感慨は一切ありません。
『松がつなぐあした』 読書レポート
本部・広報室の林です。
昨日、吉田が報告していた通り、小林さんが上梓された本
『松がつなぐあした』が届きました。私も吉田同様、
編集段階で一切目にしていませんでした。
老眼鏡がないと本が読めなくなってから、
平日の夜に自宅で読書をすることはほぼありません。
それでも週末まで待てず、早速読んでみることに。
週末の引っ越しに備え、机や椅子、ライトなどは
他の部屋にまとめてしまっていたのですが、
何となくちゃんと机に向かって読みたく、
椅子とライトだけ部屋に戻し、空になった押し入れを
机がわりにして読書スタート。
手元には本にも登場する「名取市海岸林再生の会」会長
鈴木英二さんからいただいた赤ワインを置いて。
本に親しんでいないからか、頭の悪さか、
人や数字、聞いたことがない言葉がたくさん出てきたり、
時系列でないストーリー展開だったりすると
何度もページを行ったり来たりしてしまう私ですが、
この本は、ワインが半分減ったあたりで読了。
自分も関わってきた現場の話だし、
本のベースになっている「よみがえれ! 海岸林」を読んでいたこともあり
私にとっては「復習」で、すらすらと読み進めることができました。
もちろん「よみがえれ! 海岸林」にはなかった部分も
大きく加筆されていて、「あの人からこんな話も聞いていたんだ~」という
おもしろさもたくさんありましたし、
付録部分の松くい虫に関する解説もあらためて勉強になりました。
学生時代、オイスカの現場の取材にきた新聞記者から
「事実ではなく真実を伝えるのが仕事」と聞き、
事実と真実は何がどう違うのかがよく分からなかったけれど
当時の私にとって、とても印象に残る言葉でした。
ふと、そのことを思い出しました。
この本に綴られていることが真実で、
そしてそこにたどり着くには、人の感情や心情を理解しながら
(あるいはしようと努めながら)その人たちの話を聞くという
とてつもない膨大な作業があったことを、私は小林さんを見て知っていたし、
それをこの本から感じ取ったからだと思います。
まったくプロジェクトのこと、名取市のことを知らない人は
どのように感じるのだろうかというのが気になります。
そして、プロジェクトに関わってきた方々がどう感じたのかも聞いてみたい。
早く書店に並び、多くの人が読んでくれることを期待しています。
とうとう、書籍「松がつなぐあした」が届いた
吉田です。
元日本経済新聞論説委員兼編集委員の小林省太さんが、2018年から全国のオイスカ会員や海岸林寄付者に13回に分けてお届けしてきた、おなじみ「よみがえれ!海岸林」のリメイク、バージョンアップ版が、12月7日14時33分、とうとう本になって届いたと、本当にうれしい浅野さんからのLINEがありました。
今週末11日から店頭に並び始め、13日からAmazonでも販売が開始されると聞いています。
東京本部海岸林女子の手づくりプロモーションビデオも公開予定です。
本屋にない場合はどうぞご注文ください。出版社は「愛育出版」です。
今日はオイスカ四国支部から「500部」の申し出がありました。支部の皆さん、ありがとうございます!
それを聞いた中部日本研修センターの小杉所長は「すごいな!ならば、愛知が500部以下じゃいかんな。支部会長と事務局長と相談します」「1月24日に小林さんに豊田市で講演をお願いしてるけど、前日か翌日にもう1回お願いできるといいな」と。
四国のおかげで、火が付きました(笑) とにかく、永く一人でも多くの読者に恵まれるよう、全力を注ぎます。
私は「よみがえれ!海岸林」からバージョンアップされる過程の原稿を一切読んでおりません。オイスカの著作でないためでもありますが、本音は一読者として待っていました。じつは・・・今週金曜日まで、在宅勤務。まだ数日読めません。
どこで読もうかな・・・
オイスカ中部日本研修センタースタッフから感想が届きました!
こんにちは、浅野です。
先月の最後のボランティアに参加したオイスカ中部日本研修センターのフィリピン人スタッフ、レニさんより感想が届いたので掲載します。
————————————————————————————————————————————————————————————————————–
こんにちは、オイスカ中部日本研修センターのレニです。
11月12日から14日まで宮城県の海岸林プロジェクトに参加しました。
僕は、海岸林プロジェクトのことを知っていたけど、何の活動をしているのか、何の目的で活動しているのかわかりませんでした。
津波があった時は、まだフィリピンにいてフィリピンでニュースを見たときは本当に怖いと思った。
津波を見る前は、私は釣りが好きだから、海の近くに住みたいと思っていたけど、津波を見た後は海の近くに住みたくないと思った。
津波があった場所を実際に見たら、フィリピンにいた時ニュースで津波をみた時のことを思い出した。津波でなくなった人や、被害にあった人の事を思うと心が痛くなった。
でも、プロジェクトの説明をしてもらい、そのプロジェクトが、地域の人にとってどれだけ大切なのかわかりました。
活動場所に行った時は色んな人がいて、ボランティアの人は大きな会社の社員さんでみなさんすごい人たちばかりで、緊張しましたが、みなさんやさしく、同じ立場で話しかけてきてくれて一緒に作業ができて、良かったです。
海岸林のボランティアに参加させて頂いて本当に良かったです。


JR名取駅で写真展開催中!
こんにちは、浅野です。
吉田さんのブログにもありましたが、1月15日まで名取駅で写真展を行っています!
今回の準備も鈴木和代さんが頑張ってくれました!


こんな感じで、休日に出勤して完成させてくれました。
出来上がりがこちら。ちょっと反射して見づらいところもありますが…。




(クリックすると写真が大きくなります)
宮城県にお住いの方はぜひ名取駅まで足をのばして見に行っていただけると嬉しいです!
2020年度の植栽活着率100%
吉田です。
今年は、空港真東の北釜地区旧宅地と乗馬場跡地への追加工事分3.75haに、最後の植栽として19,350本を植栽しました。結果は、100%活着しています。去年も100%。おととしは99.8%。11月下旬にくまなく歩きましたが、枯れたものは見当たりませんでした。これまでに全長5㎞、協定面積103.05ha、植栽面積72.46haに370,198本を完全に植え終えたことになります。
目下われわれは、今年やるべき大半の現場実務を終え、冬の仕事にあたっています。
この冬は、書籍「松がつなぐあした」(定価1,300円、愛育出版、12月9日発売)の存在を一人でも多くの方に知っていただき、読んでいただくことと、残り4ヵ月の募金期間を充実させることに、全力を尽くしたいと思っています。
私はこのほかに、来年から始まるSDGsの10年と合わせた、オイスカ全体の次期10ヵ年計画作成メンバーとして頑張っています。来年はオイスカ創立60周年でもあります。その議論の様子は、月刊「OISCA」11月号に掲載されています。
広葉樹の生育状況と、バッサ、バッサと剪定作業。
剪定鋏で仕事したんですから、チョッキン、チョッキンでしょうか・・・でも、仕事イメージはバッサ、バッサでした。
広葉樹2ヵ所、10種類、総植栽本数は671本。オイスカはクロマツ37万本と同じように、一生懸命育ててきました。これまでの記録はこちら。松島森林総合のプロ鈴木純子さんも毎年下刈り、葛の除去をしながらかわいがってくれています。でも、波打ち際から400m以上離れた最内陸部でも、厳しいものは厳しい。もはや、世間からの問い合わせはまったくありません。震災直後からの広葉樹vsクロマツ論争はどこへやら(笑)
国有林山砂ゾーンでは2016年植栽のモニタリング調査対象木は、去年より10本以上減り50本中25本に激減してしまいました。今年の少雨の影響でしょう。平均樹高は108㎝、平均根元径は2.6㎝。毎木調査はできませんでしたが、434本中生存は良くて6割か・・・
一方、空港に近い市有林粘土混じりゾーンは50本中46本が生存。平均樹高は140㎝。平均根元径は2.7㎝。2014年~16年の全植栽237本中185本と78%が生存。
なかなか育ってくれない・・・と言ってるうちに、それでも1mを超えるようになりました。250㎝クラスも珍しくありませんが、防風垣を越えているので、冬の間に折れることもあります。いつも行動を共にしてくれている大槻さんも、ずいぶん大きくなったなあと、見るたびに言ってくださります。
12月1日、駅の写真展の飾りつけの後、大槻さんと岩沼産の新そばを食べ、市有林の広葉樹約200本の剪定を二人で。国有林部分は先月終えています。早く太い幹にし、草丈よりも高く育てるならこの時期の剪定が肝要。ようやく安心して切り落とせる大きさになりました。萌芽更新してきたため、根元から4本も5本も株立ちしていたり、ハイマツのようになっていたり。不要な幹、不要な枝を剪定鋏でバッサバッサ。われわれ二人ですから遠慮なし。無駄口たたく暇もなし。
「空港のほうから見えるところにこれだけヤマザクラがあると、将来きれいに見えるだろうな~」と大槻さん。「剪定するとしないとでは全然違うよ」「来年は鋸も要るね」とも。草丈を超えたら、施肥も下草刈りも不要になり、冬に剪定するだけです。年月が経ち、仕事が変わりつつあることを、二人でひっそりと嚙み締めました。