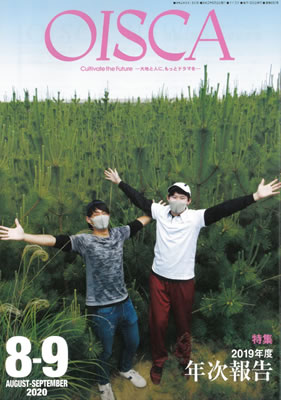まずは、東北在住の方で公募ボランティア再開
吉田です。プロもいつも通り動き始めてます。ボランティアも!
6月19日(土)ボランティア16人とプロ2人オイスカ2人で、今年度の公募ボランティアを再開しました。去年もコロナで3月~5月は実施を見合わせましたが、東北の感染者が減少したと判断基準にして同じ時期に始めました。今年の損保ジャパン環境財団インターンは、去年のこの時期から親友とともに来てくれている東北大学理学部4年生の畑君。地震と火山の研究室に入ったそうです。こちらも動き始め、前日の巡視、広葉樹施肥・生育状況確認、県庁との打ち合わせにも付き合ってもらいました。
土曜日はずっと雨。朝は小ぶりでしたので、空港東の残存クロマツ林での「藤づる」「クズ」「ニセアカシア」の刈り取り、2018年植栽地「エニシダ」集中繁茂0.1haの刈り取りを午前中で仕上げました。リピーター中のリピーター中心ですから、早い!「私たちの仕事もこれで早くなる」(松島森林総合 藤澤さん)。午後は久々に現場を視察して歩いて、ずぶ濡れでになりましたが、駆け付けてきていただきありがとうございました。
真っ先にやりたいと思っていたことを限られた時間で仕上げ、皆さんとしばらくぶりに会えました。いつも来てくださっている鹿島建設東北支社の部長さんが、ご後任の方を伴って新しい出会いも。「引退した後も来るから!」と言いつつ。短い時間でしたが、やるべきことはやった1日でした。
今年はオイスカ創立60周年。次期10ヵ年計画立案作業、Global Sustainability Missionという新しい部署の広報・資金獲得の通常業務と並行しての海岸林再生プロジェクト第2次10ヵ年計画の1年目。とんでもなく忙しい1年になりますが、抜かりなく頑張ります。
巡視の重要性を教えていただきました!
東北大学4年畑誠斗と申します。
昨年度、ボランティアとして何回か活動に参加しており、
見かけたことあると言う方もいらっしゃると思いますが、
そうでない方も、何卒よろしくお願いします!
この日は主に南側にある広葉樹エリアでの、生存数カウントと肥料やりでした。
広葉樹エリアには大量の蚊がおり、作業の間、腕や顔を刺され続け、
吉田さんにお借りした虫刺され薬を大量に塗ることになりました。
先端が赤っぽくダメになってしまってる松が多くありました。
そこで急遽、松の剪定、シンクイムシ駆除を行いました。
普段から様々な所に目を向けておく事で、ツルマメやクズなどの害草にいち早く気づき、
広がる前に阻止することが出来るのです。さらに、野鳥やキツネなどの野生生物も
たくさん発見することができ海岸林を自然として楽しむことも出来る様になります。今後の活動で、私も現場に多く足を運ぶことがあると思うので、
この巡視の心がけで細かな変化にも気付くことが出来る様になりたいと思います。
ボランティアの力を借りて、7月中旬までにやりたいこと
吉田です。
昨日のブログの「藤づる」の場所は、2019年に密生した篠竹を刈り取った場所。固く尖った切り口で危ないので、ここにボランティアは入れないとしてきましたが、2年経ったので切り口も少しは柔らかくなったとも言えます。藤つるの密生具合は、松島森林総合の佐々木代表が確認していますが、地元の指導者的存在の大槻さんにも下見していただくよう頼みました。私は18日の午前中に、新しくインターンに採用された東北大学4年生の畑君と歩きます。
藤つるは、名取市海岸林南半分の「作業道沿い法面・林縁部」に点在。とてもこの日だけでは終わりません。この日は、リピーター多数。覚えてもらうことが大事と思ってます。これ以外にもやりたいことは他にもたくさんあるのです。
まず、ツルマメ。メインターゲットは、閖上サイクルセンター周辺の2018年植栽地約6ha。
本当は19日に必ずやりたいのがその場所の、排水溝改修1ヵ所。(力持ち3・4人で)
ちょっと、しっかり落ち着いてやりたいのが、「寄付者銘板約2,200枚の引っ越し」。2015年植栽地の防風垣がボロボロに朽ちて銘板が落下してしまうので。北釜ゲートの海側、堤防近くの作業道に沿いの防風垣に異動しようと思います。7月中旬に臨時作業日を設けるかも。
6月19日(土)東北在住者限定の公募ボランティアの日にやりたいこと
吉田です。
先程、東北在住の方でメールアドレスがわかっている方に一斉送信して、ボランティア再開を周知させていただきました。狙い通り、「オイスカ海岸林=ツルマメ・土方」が定着していますが、たまには違うこともやります。
今回は、「藤」のツルの刈り取りを。
(*一日中、同じことやるわけではありません)
林業の人間としては、山を車で走らせていて、針葉樹林に藤の花が咲いているのを遠目に見ると、「手入れをしていない山」と考えます。また、仕事で山の仕事場に徒歩で向かう途中、ツルに絡まれた木を見ると、素通りせず、鉈で一振り切断します。即、ツルの切り口から驚くほどの水が流れ出してきます。藤のツルは人間の手首を超えるような太さになって、木々を締め付けます。
これか去年あたりから、わが現場にも急激に増えました。全体的に「林縁」から発生するとも言えます。作業道を走らせていると、葉の特徴とツルでわかります。プロだけでは間に合わないと判断し、藤ツルを「探して」、切断する。これを19日からスタートしようと思います。また覚えるべき「草」が増えました。
とてもこの日1日で終わるようなものでもない・・・広範囲にあります。
名取市海岸林の中央から南(全体2.5㎞×200m)の「林縁部」(すぐ見えるので、わかりやすい)に集中しています。ちなみに、2014年植栽地の最北端の最初に植えた木の数m横にも出ています。
藤ツルと並行して、クズも刈り取ります。
↑↑ 足場悪し! 厚底の頑丈な靴がヨシ! ↑↑
また今年も頑張りましょう! 早く、全国公募が出来ますように!
吉田です。
5月18日、毎年の生育状況の毎木調査前に、全体を歩いてきました。毎木調査は来週に。以下写真報告にて。
まず、空港真東(市有林)の約200本の状況。多くが2016年植栽。

左は種子が生物多様性配慮ゾーンから自然に飛んできて実生で育った「ハンノキ」去年、急激に大きくなりました。治山木として知られる、劣悪な環境に強い木です。我々の現場に3本育ってます。右は2016年に植えたヤマザクラ。
次は、名取市海岸林の中央、最も内陸側、山砂中心の国有林。多くが2016年植栽。ここには合計470本植えましたが、去年も枯死が目立ちました。ですが、根付いたものは何とか形になってきました。
育ちが悪い箇所では草も生えません。なんとか育っている個所でも草の背丈を越えました。
したがって、今年から広葉樹は一部の場所を除き「おおむね、下刈卒業」です。
ですが、葛の枯殺だけは続けます。
この木はなぜ枯れた?? ~クロキボシゾウムシ??~
吉田です。かれこれ1か月前、5月18日のこと。
清藤城宏先生と浅野さんと、仙台空港真東の広葉樹を見に行ったとき、、2015年植栽地で変色した松を1本だけ見つけました。二人は枝下に顔を突っ込み、潜り込む勢いで凝視。
「一番下の枝下に、穴みたいなのがあります」(浅野)
「葉はまだ黄緑色だけど、松脂が止まってるから、もう枯れているね。頂芽の伸びも止まっている」(清藤先生)
「私が2月に来たときは、間違いなく枯れていなかった」(吉田)
「頂芽が伸び始めた時に枯れたということだ。あとで穴の場所の皮を削ってみて」(清藤先生)
名取事務所にて・・・
「たまに1本だけ枯れるのがあるよな。なんだろな。でも、蔓延する感じではない」(佐々木統括)
翌日、清藤城宏先生より「クロキボシゾウムシではないか?」「マツの虫害は大概、衰弱木、壮齢木、枯死木に多いですが」と。この程度なら騒ぐことではないと思っていますが、来週現場に行ったら、また周囲の様子を確認します。しかし、たったこのぐらいかじっただけで枯らせてしまうってしまうのも、すごいと言えばすごい。
お詫びブログ:ヤマドリではありませんでした!!コジュケイでした。
以下、鳥に詳しい、宮城の三浦さんからのメールです!
吉田様 。お疲れ様です
久しぶりですみませんが
海岸林のブログをながめていて間違いを見つけましたので 連絡します
5月22日のブログですが
写真のヤマドリとしている鳥はコジュケイです
コジュケイについて
コジュケイはヤマドリと同じくキジの仲間ですが
ヤマドリ(尾羽の短い♀で50~60cm)の約半分(約27㎝)の大きさの鳥です
中国中南部原産で日本には1920年頃に東京、神奈川などで放鳥され始めた外来種です
特徴的な「ちょっとこい、ちょっとこい」と聞きなしが有名な
鳴き声にかなり特徴のある鳥です
声は聞けども姿が見えない、なかなか姿を見ることができない鳥です
里山付近で時々声を聴くことがありますが
私も写真を撮ったことがありません
参考に他の場所ですがヤマドリ♂の写真を添付します
念の為確認お願いします
吉田コメント:この前、鈴木和代さんから「浅野さんがちゃんと調べたら、あれはコジュケイだって言ってましたよー」と指摘あり。私の周りにはちゃんとした人がいますので、ほんとに助かります!!
令和2年度「森林・林業白書」に紹介いただきました
吉田です。「森林・林業白書」への掲載について、若い職員の方から最初にお話しいただいたときは、本当に光栄に思ったのと同時に、「失敗したら林野庁にも恥をかかせてしまう」ということが頭に浮かんだことを思い出します。表紙には「通常国会提出」とも書いてあります。閣議に提出されるんです。以来この10年で3回も紹介いただきました。白書づくりは、各部署の若手職員が集まってまとめられ、上に上がってゆくと聞いています。まず、そういうプロセスで若い人たちに認めてもらえたことが嬉しいです。ありがとうございます。
書籍「松がつなぐあした」についても言及されています。明日は、各都道府県の森林セクションに書籍PRの資料をお配りする手配をしに、林野庁に行きます。
まず、東北在住の方でボランティア再開します! ~6月19日(土)ボランティアの日~
「松がつなぐあした」が、雑誌「オルタナ」で紹介されました!
さっき、林広報室長からのメールでびっくりしました。
元日経論説委員のあの原田勝広様が、あの雑誌「オルタナ」に我々のプロジェクト、書籍「松がつなぐあした」を紹介くださったと。しかも、Yahooニュース(今日5月28日)で紹介されたと。3拍子揃ってる!とてもうれしい!
雑誌「オルタナ」 原田勝広の視点焦点 (Yahooニュースより引用)
ぜひ、ご覧ください!
なお、6月19日(土)の公募ボランティアの日の実施判断は、来週前半に。できれば宮城県民だけででもとは思っていますが、改めて慎重に判断します。