福島県北部の海岸林再生 ~震災前約200ha⇒震災後約600haへ~

2021年11月、名取から東京へ向かう車での帰り道、ちょっと違う道でゆるり帰ろうとしたとき、福島北部(新地⇒相馬⇒南相馬⇒双葉)で進む、復旧(海岸林再生)&海岸林3倍への増設工事に驚きました。そして、今度はしっかり見ようと小林省太さん(元日経論説委員)を誘って、南から北上してみました。写真中心に報告します。





















宮城県北部、気仙沼市の海岸林再生
すこし前のことですが、2月18・19日に元日経論説委員の小林省太さんと、宮城県北部、気仙沼の海岸林再生現場を歩いてきました。写真中心に報告してみたいと思います。1ヵ所あたりの面積は1haから、最大でも数haと小さいながらも、津々浦々に点在していました。



















大阪マラソン中止に思う
1月末迄は「この状況で本当に開催するのかなぁ?」
2月も10日を過ぎて「ここまできたら絶対に開催するでしょ!」
と色々ドキドキワクワクハラハラしていましたが、
2月15日、私の誕生日にまさかの発表。
「大阪マラソン市民ランナー参加中止」!!
サブ3.5達成に向けて順調に調整をしていたのに…
お楽しみは4月開催予定の「かすみがうらマラソン」に持ち越しとなりました。
引き続き苦しいトレーニングで自身を追い込みます(実は苦しさをかなり楽しんでる)。
今回チャリティランナーとして大阪マラソンを走れなくなったのは
非常に残念ではありますが、それ以上の収穫がありました。
一つは「海岸林再生プロジェクト」を説明すると同時に「オイスカ」という団体名も
多くの人に知ってもらえる機会が作れた事。もう一つはプロジェクトへの寄付ができた事です。
大会運営サイドによるチャリティランナーへの今後の対応はまだ未定ですが
機会を頂けたら、次回大会は走りたいと考えています。
まずは3月19日のボランティアの日、大阪マラソン参加中止の悔しさを溝切りにぶつけます。
切って切って切って切りまくる!!
千葉県のオイスカ会員、齊木郁でした。
皆様今年も名取でお会いしまょう。宜しくお願い致します。
2/22(火)15:30~ ラジオ関西「PUSH!つながる 神戸」に電話出演します!
ラジオ関西の「PUSH!つながる 神戸」にて、オイスカ本部GSM担当部長の吉田俊通が出演。
宮城県名取市で進む「海岸林再生プロジェクト」の最新情報をトークでお伝えします。同番組には2014年から取り上げていただいており、今回は11回目の出演です。昨年7月に除幕式を行った石碑の建立やコロナ禍における現場の様子、今年1月に開始した本数調整伐などについてお話する予定です。
radikoでインターネットからでもご視聴いただけます。
■日 時:2月22日(火)15:30~(10分ほど)
■番 組:ラジオ関西(558khz)「つながる神戸から」
本数調整伐でクロマツの根も育てる
2011年5月25・26日、東日本大震災後の初調査の際、かなりフォーカスして倒れたマツの根を見ました。清藤城宏元オイスカ緑化技術参事(元山梨森林総研)は「根が浅い」というほかに、「根周りが小さい(=根の範囲が狭い)」ことも指摘していました。のちの内部報告書でも記述があります。当時私自身は、駆け出しの海岸林オタク、100%素人でしたので、「そういうものか~」と思った程度。育苗に関わるなかで、苗の段階でも、木になっても、肝心なのは「根」だということを長年かけて徐々に理解していきました。
2022年2月7日、河北新報掲載記事「奇跡の一本松の「根」を公開 幅10メートル、津波を耐え忍ぶ」という記事が出ました。高田松原の西端のユースホステル敷地内にあった樹齢173年、高さ27.7m、胸高直径87㎝、アカマツとクロマツの交雑種「アイマツ」です。根の深さ2m、半径10m・・・本当に立派なマツだと思います。https://kahoku.news/articles/20220206khn000014.html?mailmaga=0625
これまでもこのブログで、根が重要とお伝えしてきましたが、本数調整伐の際、切り株がその後の作業で邪魔にならないように、ユンボで「抜根」したものをいくつか見かけました。惚れ惚れする根でした。森林組合の作業班のベテランさんも「いい根に育ってるね」と言っていました。
名取をはじめ全国の海岸林には、多湿の土壌を避けられない場所もあります。たとえそういう場所であっても、本数調整伐をすることで、残されたマツの根もより広く生長するはずです。地上部にしっかり見合うだけ、広がっていれば十分強度が得られるという調査報告もあります。地中の見えない部分が大事です。3月26日(土)の森林立地学会シンポジウム「津波にねばり強い海岸林(もり)づくりの「これまで」と「これから」(オンライン。学会員以外も聴講可能。申込必要)では、森林総研や名古屋大学の方たちが、根に関する最新の知見を発表なさると思います。オイスカもこのシンポジウムで発表しますので、ぜひ申し込んでくださいね。



日 時:2022年3月26日(土)13:30 ~ 16:00
開催方法:オンライン(最大500名)*学会員以外も聴講OK
参加方法:参加フォームよりお申し込みください。
下記の方々には、名取でご一緒させていただいてきた方も多く、いずれのテーマも名取と関係が深く、最新の研究成果が出てくると思うので私自身も楽しみです。トップバッターですので、あとに続く皆様の発表の話題提供になるよう関連付けながら、10分の発表時間を使ってみたいと思います。オープンに開かれる、無料の学会シンポジウムも珍しく、長時間ですが、ぜひライブで聴いてみてください。(吉田)
発表テーマ(敬称略)
第一部:津波に“ねばり”強い海岸林づくりへの挑戦
・宮城県名取市における100haの津波被災海岸林再生への挑戦(公益財団法人オイスカ吉田俊通)
・海岸林の生育基盤盛土の硬さが植栽木の根系発達に及ぼす影響(森林総合研究所・野口宏典)
・滞水環境が植栽苗木の根系へもたらす影響(森林総合研究所藤田早紀・野口享太郞、東京大学・丹下健)
・津波防災のため整備された防潮堤のり面における自然再生の取り組み:酸性土壌への植林活動とその後の経過(住友林業株式会社筑波研究所渡辺名月)
第二部:広葉樹導入の可能性とその“根張り”
・秋田県における海岸林への広葉樹導入にむけた取り組み(秋田県林業研究研修センター新田響平)
・西日本における広葉樹海岸林の意義と可能性(森林総合研究所大谷達也)
・防災林として植栽された広葉樹やクロマツの根の発達(森林総合研究所太田敬之)
・土を掘らずに“根張り”を評価:地中レーダーの可能性(名古屋大学谷川東子)
総合討論(コメンテータ:名古屋大学平野恭弘)
森林立地学会シンポジウム「詳細ページ」
シンポジウムのお知らせ | 森林立地学会 (shinrin-ritchi.jp)
間伐を体験しました!
今日のブログは、3ヶ月ぶりの名取の現場、そして最後のインターン活動であった1月29日の活動についてお話しします!
1月29日の活動は吉田さん、林さん、大槻さんと僕の友人の5人での活動でした。1月の海岸林の現場は、陽が差していたお昼頃だけを除いて、ひたすらに寒い現場でした!
現在の海岸林は、予定されていた全ての植樹が終了し、今後はクロマツのケアが活動の軸となってきます。その中でも一大作業であるクロマツの間伐が1月よりスタートしました。
オイスカの管理する場所では、”2残1伐”、つまり2本のクロマツを残し、1本伐採するという基準の下、伐採を行なっています。また他の区画では、”3残1伐”、3本残し1本切るというスタイルになっています。これらの異なる伐採量により、クロマツが今後成長するに使うことの出来るスペース、そして日照量が大きく変わります。その違いが残されたクロマツの成長度合いにどの程度違いをもたらすのかを調査により明らかにする事ため、伐採直後である29日に樹高、胸高直径を調査しました!今後の数年間調査することで、今後同じ様な海岸林を作る際の間伐の指標モデルとなる重要な仕事でありました!

また、調査の合間に、自然発生した枯れたクロマツを1本、ノコギリで伐採しました。樹木を伐採する際に大切な事は、樹が倒れる際に自分が下敷きにならないよう考えて刃を入れる事であり、そのためにはその樹の生え方、その土地の形状を根拠に倒木方向を決定します。私が切ったクロマツの場合、幹の曲がり具合から、写真置く方向に樹を倒す判断をし刃を入れました。ノコギリを真っ直ぐに引いて切ることに苦戦しましたが、無事伐採に成功しました!(プロはノコギリではなくチェーンソーを使って伐採しています)
今回は伐採に関連した活動内容となり、今後の活動を見通す事の出来る良い体験でした!


SOMPO環境財団「CSOラーニング制度」インターンの8か月を振り返って
皆さん、こんにちは!インターン生の畑です。
6月よりインターン活動を行ってきましたが、1月をもちましてインターン活動が修了となりました。
ボランティアの時から行っていた名取の海岸林の現場での活動はもちろんのこと、インターン生になった事で、仙台日経懇話会を聴講させて頂いたり、オイスカの海外での活動をより知る事ができ、大変貴重な体験をさせて頂き、ありがとうございました。
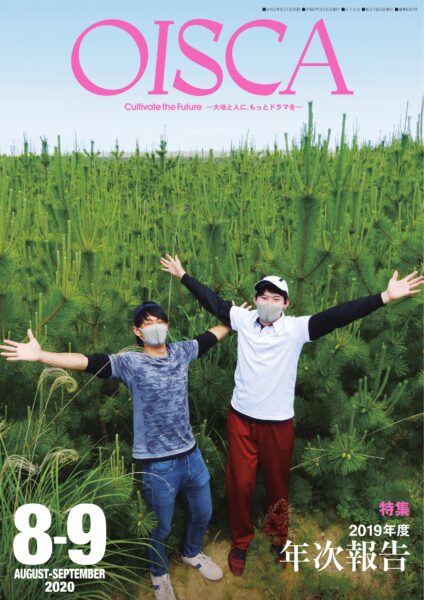
その中でも仙台日経懇話会での吉田さんの講演は印象深く残っています。吉田さんが海岸林再生にかける想いやその行動力は、今後自分が仕事に就く際にも忘れず、全力を注げる仕事を見つけたいと思いました。その他にも、林さんや浅野さん、大槻さんや小林省太さん、そしてリピーターの方々との活動を通じた関わりの中で、様々な視点や想い、考えに接する事ができました。
東日本大震災当時、小学生であり、関東にいたこともあって震災被害に触れる機会が希でありました。インターン活動の一環として震災伝承館や震災遺稿に行く事ができ、震災被害の甚大さ、そしてそこからの復興の大変さについても学ぶ事ができました。また、海岸林再生という形でその復興に携わる事ができ、これからも携わり続けたいと考えています。
最後になりますが、8ヶ月間にわたるインターン活動を受け入れてくださったオイスカ、応援してくださったリピーターの方々にこの場を借りて感謝したいと思います。本当にありがとうございました!
これからもボランティアの一員として海岸林再生プロジェクトに参加する予定ですので、今後ともよろしくお願いします!



オイスカの現場以外でも保育作業が「ガンガン」始まっています!
名取の海岸林の最も山側の国有林約10haは、オイスカ協定地2.91haを含めて約10団体が分け合って2014年に植栽が行われました。すでに国に返還され、国直営で防風柵撤去、つる切り(葛)、本数調整伐が始まっています。名取以外の地域でも同じです。クロマツ補植、ニセアカシア除伐、管理道刈り払い、排水不良個所の素掘り水路・・・いろいろな工種が発注されているようです。本格的に保育が始まったことは、妙にうれしく、とても心強く思っています。宮城のオイスカボランティアの人たちも、現場を見れば変わり様がわかるかもしれません。
歴史的に見て、国有林は最も早く整備されたため、大まかに言って最も内陸側に位置します。その後、市町有林、県有林の順で海側に向けて海岸林の幅を広げてきました。葛・藤つる・ニセアカシアなどは、どうしても内陸側から広がってきます。つる切り・除伐を最もしっかりしなければならないのは内陸側。行政の頑張り、本当に頼りにしています。これからは追々、これに松くい虫対策が加わってくるでしょう。名取だけよくなっても仕方ない。国や「みやぎ海岸林協議会」の皆さんとの協働で頑張っていきたいと思います。



本数調整伐の「運び手」
吉田:「この仕事どお?」、S君「飽きますね。はっきり言って、やりたくないです(笑)」
なにしろ数が数。17,000本の伐採ですから。こう言わなかったら嘘でしょう。最初の数日は、班長は先回りして段取り付け。プロの伐り手2人に運び手2人。これだと非常にキツかったです。
概して20m前後先に、伐採木を延々集積します。枝を切り落とさず、丸ごと運びますから重いです。バッサバッサと松は伐られますが、運び手はこれぞ林業の重労働。枯れ落ちた松葉でふわふわした林床、排水溝があるアップダウンを、樹高4m前後、体感20kg~30kgに感じるマツを平均20m引きずり、所々の枝葉の薄い場所を使って強引に通り抜けて運ぶ・・・
吉田:「仕事のキツさ、5段階評価でいくつ?」C君:「3ですね。斜面じゃないし、木も細いから」
作業道の両側は延々、盛土の高さまでクロマツ伐採木が積まれていきます。あっという間に。いずれ近々、トラックの登場です。伐った木はすべて林外搬出で、大和町の宮城県森林組合連合会に持ち込み、チップ・バーク堆肥などに再利用されます。そのあたりもいずれ現地レポートしたいと思います。
私は2日体感しただけで、11年ではじめてルートイン名取のコインマッサージ機の世話になりました。「そんなものボクには必要ない」って思ってましたが、風呂のあと、100円/10分×3回。私の場合、とくにふくらはぎのマッサージが抜群に効きました。履物はブカブカとしたスパイクのない長靴ではなく、足にシャキッとフィットしたスパイク付き足袋がいいですね。昔、はじめて履いた時、電動自転車か、飛んで歩いてるように感じました。






