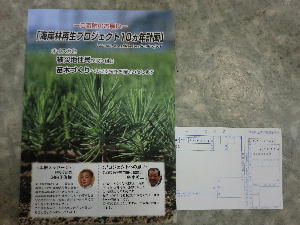吉田の名取出張レポート その6 播種から8ヵ月!の苗を試験植栽 in仙台
昨日の続きです。
何で説明会に秋田の東北局からも、仙台署からも、
種苗組合からも、大勢が来ているんだろうと思っていました。
試験植栽にしても、かなり時期が遅いような……
さておき、たった1時間で話をしたい人とたくさん会うことができました。
で、
コンテナでたった8ヵ月の短期間で植える規格まで育った100本の苗を、
①コンテナ穴の鹿沼土の配合率20%、バーク堆肥を底に播く、固形肥料も使用
②コンテナ穴の鹿沼土の配合率20%、バーク堆肥を底に播く、固形肥料なし
③コンテナ穴の鹿沼土の配合率20%、バーク堆肥・固形肥料なし
④コンテナ穴の鹿沼土の配合率40%、バーク堆肥を底に播く、固形肥料も使用
⑤コンテナ穴の鹿沼土の配合率40%、バーク堆肥を底に播く、固形肥料なし
⑥コンテナ穴の鹿沼土の配合率40%、バーク堆肥・固形肥料なし
以上6パターンに分けて植栽。
結果はいかに。
もちろんコンテナ苗には、長所もあれば、短所もある、技術的には当然課題がある育苗方法です。専門家の中でも意見は様々。
根元の径が若干細く、倒れやすいとも言われています。しかし、それは杉やヒノキの話。しかも海岸林では試した事例がそもそも少ないことでしょう。
我々は実践部隊。
来年の播種までに、僕らも色々な試験結果をギリギリまで情報収集して、ベストの選択をしなければならないし、その選択ための準備はすでに始めているのです。良い機会に恵まれました。
吉田の名取出張レポート その5 基本情報満載。国有林の現地説明会
11月22日に、林野庁東北森林管理局による、
仙台市若林区荒浜国有林2haについての現地説明会に
行ってきました。2回で合計8団体が来たそうです。
少なくて意外でした。
林業会社の感覚ですと、たとえ手を挙げるつもりがなくても
社長は必ず行っていました。
ここは、盛土を作る前から何度も訪問しており、
11月4日にオイスカの中野会長もキックオフ植樹式に参加しました。
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/sidou/kizuna_shokuju.html
東北局HPにはその時の写真が満載。
見るのと見ないのでは大違いと思いました。
これからも定点観測をして、参考にさせて頂こうと思います。
6月13日、10月24日ブログ
http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=1074
http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=2204
説明会の内容は、東北森林管理局のHPに掲載されている通りです。
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/sidou/kyoutei/arahama_koubo.html
これが基本の情報なのです。
こういう説明会の、一言一言のニュアンスは、
私にとって非常に重要でした。
今回の説明会終了後は、更に貴重な情報源に。
それはまた後日。
吉田の名取出張レポート その4 今の苗
視察・種拾いに参加しました!
住友化学労働組合 宝塚支部長の田中嘉人です。
今年2月に、オイスカの皆さんのご協力のもと、タイ・ラノーン県でのマ ングローブ植林活動に参加させていただきました。
また、今回は東北の「海岸林再生プロジェクト」の現場視察に伺いました。
この両プロジェクトとも、行政、専門家、支援者、そして、地域住民を中心に継続的に取り組んでいくプロジェクトであること、長期にわたって支援していくプロジェクトであることを感じました。
当日は広葉樹の種子拾い、海岸林・育苗場の視察を行い ました。
広葉樹の種子拾いでは地域の森林組合の方とどんぐり (コナラ)、栗拾い。
参加者十数名で1時間実施しましたが、取れたのは少しだけ。
 少しではあるけれども、この種たちが内陸の防風林などと して活躍することを期待します。
少しではあるけれども、この種たちが内陸の防風林などと して活躍することを期待します。
驚いたのは、この種たちのその後。
取った後に1日水につけ、殺虫剤の種子処理をするとのことでしたが、種子処理 に使う殺虫剤が住友化学の商品(スミチオン)でした。クロマツの育苗でも同様に自社製品(スミパイン)が使用されていることを知りました。
今回の現地視察で自分たちの商品がこういった形で植林 活動に繋がっていることを知ることができ、大きな喜びとともに本業でも貢献していける可能性を感じたところです。
海岸では、まばらに残ったクロマツを見ながらの現地視察でした。どこまでが住宅地だったのか、どこまでがクロマツの海岸林だったのか分からない状態でしたが、吉田さんの話を伺いながら、ここには地域と密着した海岸林が、確かにあったことを知ることが出来ました。

特に印象に残ったのは「誰が植林の主役か」という吉田さんの質問です。地域住民による、過去の植林について記載されている石碑「愛林碑」の前での言葉でしたが、参加者全員が考えさせ られる質問でした。地域の歴史、文化を学び、地域住民と理解しあいながら参加する必要があると感じました。
白砂青松を取り戻すまでの長い長い道のりを、住友化学労働組合も長く長く支援、サポートしていけるよう取り組んでいきたいと思います。

吉田の名取出張レポート その3 年度末に向けて工事はトップギア
日曜日以外は、ダンプがバンバン走っている。
林業会社にいた時、この時期からは社長の目の色、従業員の雰囲気が変わっていた。
「社長の機嫌」の話題がただでさえも多いのに、一層多くなり……
それぞれの会社ではそういうムードなのでしょう。
防潮堤工事(国交省)は今年度末であらかた終わる計画で、いよいよ林野庁の出番です。
予定通り、倒伏したマツは整然と片づけられています。
(国交省の I さんも頑張ってるんだろうなぁ)
その脇では、復興組合の方達、40人ぐらいか?
ビニールハウス1,000棟の跡地で、以前刈り取った葦を運び出すために
まとめている。女性もたくさん。
あれ~、3月の播種の後に「祝い唄」3曲を歌ってくれたSさんだ。
思わず立ち話。
「俺たち仕事がないから、こんな仕事してるんだ~。セシウムのことがあるから~」
日暮れも早く、4時過ぎると視野も狭くなる。
工期内満了に向けて焦る季節。
寒いと小さな怪我でも身に染みる。
お互いに怪我のないように……
僕も明日は防風ネットの修繕だ。
慣れない仕事。林業会社でやっていたように、安全管理しよう。
吉田の名取出張レポート その2 来年の計画イメージ
来年の事業計画を名取事務所で話し合いました。
復興計画や復旧工事の進捗、自然や技術の微妙なところに
左右されるので(決める人にもよる)、我々には不断の
情報収集力と、その情報を見極める力が必要です。
12月7日(金)の秋山君のトークイベント&懇親会in日比谷の場で、
現時点での状況を、せっかくの機会なので口頭で行い、
このHPやブログなどでも随時、全国の方にもお伝えしようと思います。
来春からいよいよ一般市民の出番が少しづつ出てきます。
やはり、大きく動き出すのは平成26年の、早くて春と見ています。
その前にやっておきたいことが。
来年はボランティアを受け入れるためのボランティア育成をテーマに。
早くからご協力いただいている人とできるだけ懇意になり、
現場ロジや知識を一つでも多く、体で知っていただく期間にしたいと思います。
本部事務所と名取事務所でそれぞれ定期的に「ボランティアの日」を定め、
汗もかいてもらい、座学も行い、その後ちょっとノドも消毒する。
本部事務所では、毎月第1土曜日、まずは12月1日(土)午後、
東京ならではの仕事と、ときにミニ講演会も。
名取の方では、まずは第1回は2013年4月19・20日(金・土)。
これ以上の詳細は今しばらくお待ちください。
地元の方とともに苗の移植。
日々揺れる復興の真っただ中。小出しの情報をご容赦ください。
このHPが生命線だと思って、維持・構築したいと思っています。

来年4月第3週(金・土)、2012 年3月播種のクロマツはこの空いたスペースほぼ全面に移植されることになる。

寒空の名取事務所。5月頃までは蔵王からの風が。
吉田の名取出張レポート その1 とんちゃん
プロジェクト担当の吉田です。
名取事務所に長逗留中。
事務所を手伝って下さっているMさんが、第1育苗場班長に電話して下さって、5時過ぎにやっぱり「とんちゃん」は始まった。
(このブログ読者はたびたび登場する「とんちゃん」をご存知かと思いますが、ご存じない方、こちらをどうぞ)

地元の人は好きですね。
やっぱり体を使う仕事をしているから。
班長はいつも七輪。小窓がとても便利です。
油がバシバシ飛び、名取事務所休憩室は煙で真っ白。
今日の話題も多岐。
●の話題はボリューム大
●何故引っ越してきた人が自治会に入らないか。(班長は自治会長)
→Y君はナゼ自治会に入ったのか。
●俺のなんとかマスカットと、Mさんの巨峰がどっちが旨いか。
・秋田の海岸林視察でクロマツ植栽に自信を持った。
●Y君は女性に何を求めるか。→班長は「お互いを高め合うこと」
・Mさんの離れて住んでいる息子さんについて
●イチジクとナンテンが津波で10日水につかっても枯れなかったのは何故か。
・秋山君(10月末までオイスカ名取でインターンの大学生)のここでの
稀な経験を将来どう活かすか楽しみ。
・名取の「雪菜」はおいしい。⇒12月7日秋山君トークイベント来場者にはもれなく。
・津波で蛇は全滅したと思っていたら、1匹だけ、見た人がいた。
・美田園駅周辺の地価上昇。
・「学校植林」の石碑をついに発見。
(地元の名取市立下増田小学校が、昭和28年全国学校緑化コンクール第1位。
前年2位。後日ブログで紹介予定)
・「学校植林」のクロマツ林8haをなぜ植えたか。
●死ぬとき何と言って死ぬか。
班長 「い~世の中だったな~」
Y 「あ~おもしろかった」、
Mさん 「?」(班長が混ぜっ返して、答えるいとまなく)
まさに順不同。
いつか皆さんと、そういう「とんちゃん」を。
助っ人大募集! 12月1日(土)午後、手伝ってください!!!
ファミリーデーにぜひご参加ください!
「海岸林再生プロジェクト」の活動報告の機会を全国で作っています。
そのひとつがこれ。
愛知県豊田市で開催「オイスカファミリーデー」。
来年2月のイベントなのでまだ先ですが、プロジェクトの報告以外にも
バンド「セーリング」のコンサート、女優紺野美沙子さんの記念講演もある
なんとも盛りだくさんなイベントなので、ぜひご参加いただきたくご案内します。
皆様のご参加が支援につながります!!
ご案内チラシ (PDF 750KB)
第6回オイスカファミリーデー
主催: オイスカ豊田推進協議会
後援: 豊田市・(公財)豊田市文化振興財団・みよし市
日時: 2013(平成25)年2月09日(土) 開場13:00 開演14:00
場所: 豊田市文化会館大ホール
定員: 1500名
申込締切日: 定員になり次第締め切り
対象者: 会員・支援者・一般どなたでもお越しください。
入場料: 1,000円
お問合せ:TEL 0565-42-1101 FAX 0565-42-1103
E-mail chubu@oisca.org 担当:小杉裕一郎
愛知県の支援者訪問with中学生
先週、オイスカ愛知・静岡・岐阜・三重県の会員の大きな会合で
プレゼンをするため、愛知県に出張してきました。
前後の時間を活用して支援者訪問などをしましたが、
オイスカ中部日本研修センターの近隣の中学校から3日間の「職場体験」に来ていた
2年生の女の子と一緒のスケジュールが組まれていました。
さすがに人づくりの中部センター。
本部事務所にも毎年中学生が体験に来ますが、
彼女は「環境」に関心があってオイスカに来たそうです。
「ちょっと難しい話になるけど、ごめんね」と断って会員企業訪問に行きました。
(途中で寝ちゃうんじゃないかなー)
会社の前に来ても彼女は固くなる雰囲気がない。
「緊張しないの?」「将来、営業できるんじゃない?」
どうも全く平気な模様。
豊田市の太啓建設㈱、ユーズネットさんと2社訪問し、支援のお礼を伝えることを大きな目的に、全くいつも通りの仕事をしました。
彼女は、大きな会社の社長さん、常務さん、部長さん、課長さんの名刺をしっかりいただき、僕の資料もレポートで使うためにしっかり持ち帰り。
「ぶっちゃけ、どうだった?」
「何回か眠りそうになった。クロマツの話が多かった。難しかった。」
2時間弱、よく辛抱していました。
迎えに来たお母さんに報告もしました。
大きな目的は彼女にも伝わった気がします。