6/23(金) OGFS・ボランティアレポート
SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。
6月23日、初参加となるOGFS(フェデレーション・オブ・オリエンタルランドグループ・フレンドシップ・ソサエティー……つまり、オリエンタルランドグループの労働組合です)から18名の方々がボランティアにいらっしゃいました!
本日の作業は北釜の藤刈りから。昨日のメンバーに野本さんご夫妻が加わり、バス到着の1時間前から作業が始まりました。私も藤の相手をするのは久々で「そういえば藤ってこんなにデカかったっけなぁ……」と不意に感心してしまいます。最近は葛ばかりでしたからね。藤以外にもドクウツギや棘付きのバラが繁茂しており、中々に手強い作業でした。


バス到着後は作業内容の確認と恒例のKYを済ませ、手分けして藤刈り&法面の下草刈りへ。法面の藤を端から端まで辿ってみたり、鳥の巣(既に空っぽでした)を見つけたり、皆さんと新しい発見を楽しみながら汗を流すことができました!
その後、私含む常連チームは残る防風垣の解体、オリエンタルランド労働組合は広浦の葛刈りに分かれて作業しました。ちなみに防風垣の解体はわずか30分程度で終了。大槻さん・野本さんのプロ仕事は流石の一言でした。勉強になります。


オリエンタルランド労働組合は翌日の公募ボランティアにも参加します!
引き続きよろしくお願いします!


吉田です。むかし高校の先生から「読書百遍」という言葉を教わりましたが、オイスカに入ってからは「現場百遍」と思っています。フィリピンのはげ山600haを森林に変えたロペスさんという先輩も、1日2回、毎日山に登ると言っていました。
暑さに体を慣らすには絶好の夏日。例年通り、普段通らない経路を目一杯歩いて、集中的に今年の葛駆除の作戦を立てようと。ボランティアは北側半分、松島森林総合は南側半分というのが大まかな分担ですが、松島チームは例年通り林外法面は全域を担当します。
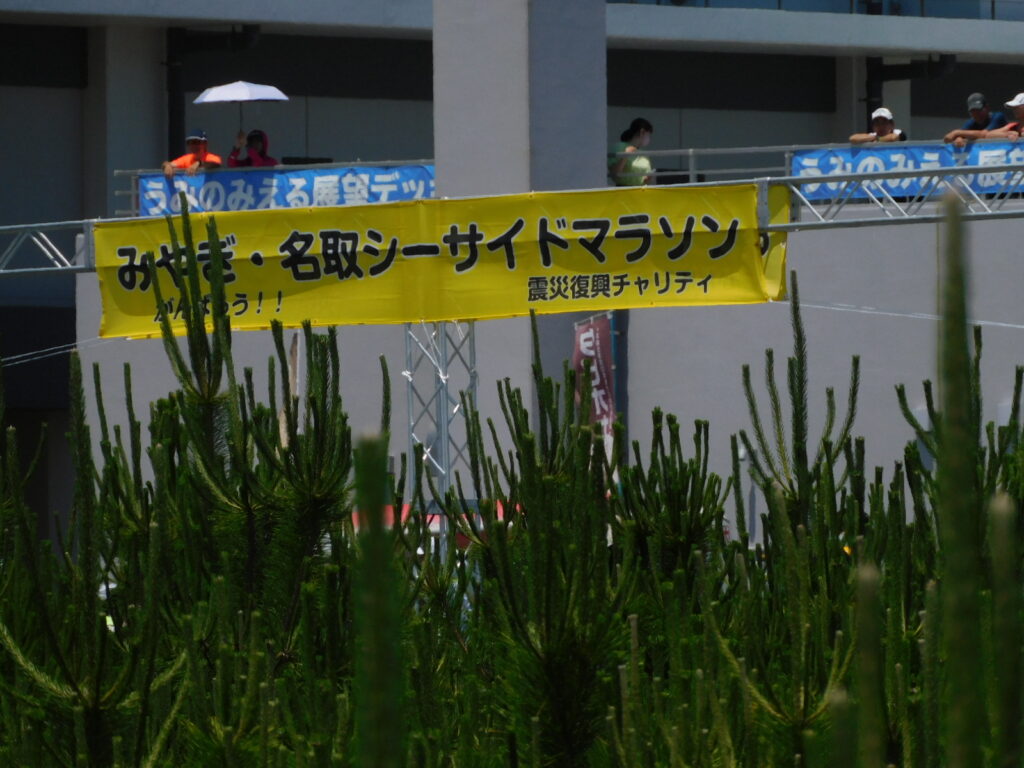

害虫マツカレハの発生状況についての佐々木統括の見立てとしては「(密度は)薄い」。1本に30匹ぐらいいると枯れることもある。確かにいる場所は限定的。でも、2020年みたいにもう少し鳥に食べてほしいなあ。目が慣れてきて、ゆっくり歩きながらでも見つけられました。使いかけのアースジェットとキンチョールが3缶空に。ほんのちょっと軽くかけるだけでも、もんどりうって、数分のちに落下します。おそらく来月にはみんな蛾になっていなくなるんでしょうけど。
去年頑張った場所がどうなっているか・・・いまのところ、やはり「激減」です。でも本当に伸びるのはこれからです。今年、プロチームは広大な場所を抱えます。ボランティアチームは、時期に遅れず好スタートを切りましたので、9月頃には「手伝いましょうか?」とプロに言えたらいいなあと。競争ではなく、励みにして今年も戦います。









吉田です。今年の5月下旬はほとんど雨が降らず、6月になってからは、中旬まででは過去10年で上位の約100㎜が降りました。6月16日夜半から昼までに、まとまって44㎜程度だったので、排水の様子を見に行きました。
名取市海岸林の北半分の広大な敷地は、震災後約2年半、名取市内のがれき全ての集積地と処分場になり、重機が走り回る場所でした。ですから、盛土の下は極めて固いことがわかっています。つまり、水が抜けにくいということです。森林総研による2018年の調査では、「土壌貫入計が折れそう」「50㎝以上下は掘れない」「穴を掘ると水が湧く」「グライ化(白い山砂が青くなっている)している」と専門家が話すのをその場で聞きました。元の地盤、つまり海砂が重機やダンプで「転圧」されたことによるあまりの硬さによって、この場所ではクロマツの根は深くは刺さらず、雨水の浸透も期待できないかもしれません。ですが、根が深くなくても、広く根を張ることができれば、津波にも耐えるレベルの強度があるという研究結果があります。「間伐」の大きな意義と期待です。














上の写真は2013年4月10日の国連NGO課長のアブラモフ氏とともに、名取市海岸林の北側全体を占める規模の瓦礫処分場を、西松建設さんの案内していただいた時のものです。
さらに2年さかのぼって震災後まで振り返ると、2011年5月25日に清藤城宏先生や松島森林総合の佐々木勝義代表や私などオイスカ調査団8名でここに行きました。あたり一面はクロマツの「倒伏」でした。間伐が一度もされていなかったため、「幹が細い」「根周りが小さかった」と清藤城宏先生が結論付けたことが、とても印象に残っています。
-138.jpg)
-126.jpg)
-136.jpg)
-141.jpg)
-142.jpg)
-144.jpg)
上の写真は、2011年5月25日のオイスカ調査で撮影。名取市サイクルスポーツセンター周辺
排水対策としてのボランティアによる溝切りは、名取市海岸林南部で2015年から本格的に始めました。「雨水の8割は林外に出したい。残る2割は、蒸発1割と浸透1割」と佐々木統括が何度も言っておりました。2016年には中央部から北での植栽が始まりましたが、滞水と排水先に困る場所ばかりでした。例えば、村井知事や佐々木前市長が植えた2016年植栽地の約4haは、溝切りした2年後からはっきりとした生長を見せていることが、その場のマツを見ればわかるので、いつも説明する場所です。この前の6月16日の44㎜の雨の直後は、排水口から音が聞こえるほど、滝のように流れ出ています。ここはボランティアによる排水溝修復と大幅増設により、国の工事で設けられた「排水口」も「排水先」を活かせるようになり、努力が実りました。




サイクルセンター周辺は2018年に植栽しましたが、夏の大雨でクロマツの間をカモが泳いていました。田んぼの様でした。引いたように見えても歩くと泥濘があり、苔が生えている場所もある。「2週間水か引かないと枯れる」と統括が言います。ここだけは本当に枯れるかもしれないと思いました。


そして大小様々な「溝切り」を4年越しで続け、最も多湿度が酷く、湿地に生える葦だらけの場所も、今年の春ようやく溝切りを終え、5月13日にタイの方たちに補植してもらうにまでなりました。サイクルセンター屋上から見ると、それがどこかすぐわかります。マツで鬱閉されて地面が見えなくなるまで葦は生えると思いますが。5月13日のタイの漁民の手による補植120本のその後は、2週間、1ヵ月が経ち、1本も枯れていません。活着率100%です。








国も作業道を50㎝掘り下げて、道路兼用の遊水池を掘ってくれました。5月13日に完成した300mの排水溝を伝ってこの遊水池まで排水できれば、元の地盤の海砂がすぐ下。実際にこれまで遊水池が滞水したことはありません。




2015年以降、溝切りを続けてきました。ボランティアによる前人未到の努力とも言えると思っています。まだ溝切りしたい場所はあるのですが、これから私たちが為すべきことは、葛との戦い、病虫害の防除など山ほどありますが、とにかく確実な間伐(本数調整伐)の実行です。根周りがしっかり広がっている、最強の海岸防災林に仕立てることだと思っています。与えられた条件のなかで、様々な方たちと一緒に、最大限の努力をして、最終的に後世の人にも愛される海岸林にしたいと思います。
【和泉】これから8か月間、インターン生として活動します!
宮城大学4年、ボランティアの和泉です。
この度私は、公益財団法人SOMPO環境財団が実施している「CSOラーニング制度」を活用し、オイスカ名取事務所のインターン生(名取では5人目と聞きました)として6月から8か月間活動させていただくこととなりました。今回は”インターン生”として初のブログ更新となります!そこで、改めて自己紹介と、今後の活動についてお話したいと思います。
■プロフィール
名前:和泉 壮汰(いずみ そうた)
出身:福島県郡山市(現在は仙台市泉区)
所属:宮城大学 事業構想学群 地域創生学類 地域科学コース4年
趣味:サイクリング
好きなもの/苦手なもの:アイス/お酒(サワーならいけます!)
■これまでの活動とインターン参加のきっかけ
私は昨年3月から約一年間、オイスカの「海岸林再生プロジェクト」のボランティアとして活動してきました。参加回数は20回ほどでしょうか。まだまだ勉強中ですが、段々と経験者としての役割を任せていただけるようになりました。そんな中、吉田さんからCSOラーニング制度を紹介していただきました。これまでボランティアで培った現場経験やスキルをフル活用できるだけでなく、インターン生として海岸林再生事業を管理・運営する立場の知見を、より間近で実践的に学ぶことができることに強く惹かれ、応募を決めました。
■インターン生としての主な活動内容
主にボランティア受け入れのサポートとブログ更新を行っています。サポートとは、事務所での事前準備や道具の管理、現場での指揮執りなど、吉田さんの補助的な役割を担っています。ブログ更新は、私が参加したボランティアのレポートを中心に、都度更新しています。また現在、海岸林リーダー1期生・2期生共同のイベントを計画しています。こちらはまた別の機会にお伝えできればと思います。
■卒業研究について
CSOラーニング制度とは別の話になりますが、自身の卒業研究として名取市海岸林をフィールドにしていきたいと考えています。テーマは「名取市民の海岸林に関する意識調査」です名取市にとって海岸林は、潮風や飛砂、時には津波といった脅威から内陸部を守る防災機能を果たしたり、沿岸地域の美しい白砂青松の景観を形成する上でなくてはならない存在です。そして、海岸林を将来的に持続可能な形で維持・管理していくためには、海岸林と共生関係を築いてきた地域住民との協働が必要となります。しかし、海岸林の重要性を知り、協働による海岸林の保全活動に意識を向ける人は、ごく一部に留まっています。本研究を通して、名取市民の海岸林に対する認知度や関心、管理のあり方、ボランティア活動への意識など種々の観点から切り込み、定量的なデータを踏まえた名取市海岸林の現状を記録として残していきたいと考えています。まだ詰め切れていないところではありますが、今後は研究の進捗についてもブログを通してお伝えできればと思います。
■今後の抱負
参加者にプロジェクトや海岸林について自信を持って話せるくらい、現場について詳しくなりたいです。これからインターンと研究で海岸林漬けの生活になりますが、気を引き締めて一つ一つ真剣にやっていきたいです。8か月間よろしくお願いします!!!


吉田より:彼が来てくれるようになって1年。その初日から自転車で2時間かけて来ている「タフな男」です。アンテナが高く、行動力に秀でていると思います。名取の現場は様々な調査フィールドですが、社会学からの研究は彼が初めてで、非常に貴重な記録となるはずです。同じような研究は富山県の入善海岸しか見たことがありません。当然、東日本大震災被災海岸林では誰もやっていないでしょう。10年後、20年後、誰かが追跡調査するとすれば、さらに価値が上がると思います。おそらく、ボロボロの深刻な結果が出ると思いますが、バイアスを排除した現実を知りたいと思います。私にできるバックアップをしたいと思います。
吉田です。6月16日は佐々木統括の代役で、種苗組合北海道・東北地区の視察研修30名への説明役も。大雨だったので現場に行かず、これまでの視察対応ではじめて事務所だけで対応。
16・17日は再生の会の方たちの苗木出荷の準備でした。長い時間一緒だったわけじゃないんですが、まず、相変わらず元気で楽しそうで(笑)。休憩時間にミヤギテレビ「Oh!バンデス」で放送された25分の上映会したり。
17日に亘理町の植え直しの現場に2,000本出荷するとのことで。苗木はこういう外部の要望のために、焼却処分などせずに大事に育てています。他地区の様子を自分の目で・・・とも思ったのですが、どうも助っ人は不要そうだったので、オタクの休日は、存分に現場を歩いて、繫茂状況を図面に落とし、この夏の葛刈りの作戦を考えることにしました。






30人ぐらいならこんな感じで。私はカメラの位置で立って説明。

6月上旬~中旬のいきもの
吉田です。定期野鳥観察中の地元ボランティアの三浦さんと現場で会った時、「アオジがいますね~」と言っていました。鹿島の山下さんからは、「シマヘビの子供が土嚢の下にいた」と。あれ、かわいいです。三浦さんの2022年度鳥類調査によると、6月は一番多くの鳥を確認できる月。松が大きくなってますから、以前のように、足元の鳥の巣を見つけにくくなりました。写真は撮れませんでしたが、ウグイス、カッコウはよく鳴いてましたし、ツバメ、スズメ、ヒバリ、ムクドリ、カラスもいます。ハヤブサ系は見れませんでしたが、ミサゴは何度も見ました。












でも、もうすぐ蛾になっていなくなるでしょう。


















*大変恐縮ですが、Google翻訳です!
東京本部GSMで吉田部長と働いているグラゼンです。6月7日から10日まで、吉田さん、浅野さん、和泉さんと一緒に、カネボウ(30名)、積水化学(50名)、化学総連(50名)のボランティアグループの受け入れ、のため、名取に出張しました。このような活動は初めてではありませんでしたが、3日間連続で大人数を相手にするのは、正直言って緊張しました。


ボランティアで来てくださる方々の本音は、「このサイトをより良くしたい」ということだと思うんです。私は、ボランティアは地位や立場に関係なく、平等に扱われるものだと考えています。特別扱いされることはありません。ボランティアはお客様ではなく、私たちのプロジェクトの重要性を理解し、与えられた仕事がプロジェクトの長期的な影響にとっていかに重要であるかを認識している仲間であると私は感じています。
確かに、森林再生プロジェクトに携わる場合、植樹活動以上に、サイト全体の管理が大変です。名取の現場では、クロマツにからみつくクズの蔓をどう抑えるかが大きな課題でした。頑丈な敷地内に入りやすいように道を作り、クロマツを締め付けるクズの蔓を取り除く作業が必要な場所もあります。また、針状の葉から目を守るため、ゴーグル付きのヘルメットを着用し、安全第一で作業を行いました。


一方、一部の地域では、クロマツに毛虫が発生しているところもありました。この虫を駆除しないと木が弱り、他の病害虫に襲われやすくなります。エアゾールスプレーを手にしたボランティアは、この不気味な生物と戦っていました。個人的には、性別に関係なく、立ち向かうのは勇気がいることです。20代の男性ボランティアに「またボランティアに行きたいですか」と尋ねると、「毛虫が全滅しない限りは無理かもしれません」と素直に答えました。
また、「カマを使うのは初めてですか」という質問には、7割近くの人が手を挙げました。私は最初、”おっ “と思いました。しかし、大槻さん(81歳)、森さん(ボランティア)という地元の名士がいることで、最も効率的で効果的な草取りの方法を、ボランティアにわかりやすく教えてもらいました。心強かったです。
吉田さんの説明で印象に残ったのは、「森林再生プロジェクトで一番難しいのは、地域の人たちに愛される森を作ること」ということです。アジア・太平洋のさまざまな国で行われているオイスカ森林再生プロジェクトのプロジェクト責任者も、きっと同じように感じていることでしょう。
すべての森林再生プロジェクト活動を完全に実施するには、15年以上かかると認識しています。その出口戦略として、プロジェクトの持続可能性とオーナーシップを確保するために、地域コミュニティとの関わりを重要視しています。簡単な仕事ではありませんが、私たちはそれを実行に移すことを約束します。




6/9(金)-10(土) 化学総連・全積水化学労連 ボランティアレポート
【※本記事には毛虫の写真があります】
SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。
6/9(金)と6/10(土)の2日間、化学総連の総勢100名の皆さんと一緒に活動しました!その中でも積水は倍率が2倍超えと人気だったようで、100名のうち50名が積水という大所帯での参加でした。(積水は1日目のみ参加)
本部からは浅野さんとフィリピン人職員のグラゼンさん、地元からは大槻さんと森さんが駆けつけてくださいました。グラゼンさんは第一回海岸林リーダー報告会でお会いして以来、久々の再会です!
1日目はあいにくの雨空。午前中に現場の見回りに行った際はLLサイズ溝が水浸しになっていました。午後から始まる作業をやるかどうか決めかねていたところ、たちまち化学総連から「やりましょう!」と声が上がりました。そんなやる気に応えるように、現場に到着する頃にはほとんど雨が上がっていました。


今回の作業は葛刈りと枝払い。蒸し暑い環境ではありましたが、皆さん集中して取り組んでくださいました!








地面を這うツルを徹底的に攻めることが肝要!
特に目立ったのはこの虫。名前を「マツカレハ(通称“マツケムシ”)」と言います。名取では2020年に大発生して以来のようで、私も本物は初めて見ました。
このマツカレハ、幼虫が葉っぱを食べてマツを枯らしてしまうほか、体を覆う毛束に刺されると痛みや痒みを伴いながら大きく腫れあがってしまいます。ボランティアの安全確保のためにも、殺虫剤などを使いながら地道に駆除していかなくてはなりません。一本のマツに5匹いることも珍しくなく、ある方は「もう100匹以上はやりましたかねぇ。」と苦笑い。
実はこの前日、オイスカの浅野さんが飛んできた毛?にやられてしまったらしく、首・腕・脚まで赤くなっていました。(浅野さん曰く、黒とオレンジのモンシロドクガのような毛虫によるものとのこと)症状は患部の痒み程度ということで一安心です……。




2日目は打って変わって快晴。前日の作業をさらに詰めていきます。
化学総連の皆さんも、もう慣れっこと言わんばかりの手際の良さを見せてくれました。買い足したキンチョールを片手にどんどん進んでいきます!
最後に払った枝を外に運び出すと綺麗な一本道ができました。とても達成感のある光景でした!


2日間に渡る作業も無事終了。今回は作業もさることながら、参加者の方々やグラゼンさんから貴重なお話を伺うことができたことが、私にとって一番の収穫でした。インターン生としての活動が始まった今こそ、自ら学びに行く姿勢を大切に活動していきたいです。
皆さん、本当にお疲れさまでした!!



コロナ前、香川県高松のオイスカの女性役員さんたちと食事したとき、「オイスカに関わるとこういうメリットって何ですか?」と伺ったら、「出会い!」と即答。関わってくださる人達に、そう感じさせる仕事でありたいです。
先月、タイからの訪日研修が終わりましたが、とくにその実行の過程で、私にとっても名取で新しい出会いが続きました。
6月のある休日の午後を使って、閖上の朝市協同組合の桜井理事長と事務局の佐藤さん、マルタの相澤社長、センシン食品の高橋専務に訪日研修でお世話になったお礼のご挨拶に行こうと。
その午前中、「7月の県立名取北高校での「生物」の授業(45分×屋敷林・海岸林の2コマ)の下準備でもしようかな」と思ったのですが・・・通りがかった北高のグラウンドから、野球の音が。
いつもと違うパターンでオタクの脱線。野球、好きなんですよ。とくに楽天の岸投手(名取北高校出身)が、西武時代から大ファンです。
3月にボランティアに来た野球部の練習試合が始まったばかり。打線が1巡するぐらいまでは見ようと外から観戦。初めて会った1年生から「どうぞ中へ」って2回も誘われたのですが、知ってる生徒さんがいるから恥ずかしくって。しばらくしたら榊先生(生物のご担当)が来て、バックネット裏で一緒にどうぞと。キャッチャーのすぐ後ろで高校野球が見れる・・・コロナ禍が一段落したことを実感しました。2回表から6回表までゆっくり特等席で観戦。生徒さんの話や授業の話、北高全体の総合学習の話もしながら。

午後は、予定通り挨拶回り。朝市の桜井理事長は、「今年、必ずタイに行きたい。1週間ぐらいいつでも空けるから!」と。

マルタの相澤社長とは、超長話に。社長、ごめんなさいね。北高野球部OB、しかも岸投手の1年上って、北高の榊先生に伝えました。先生が会いたがってましたよ。

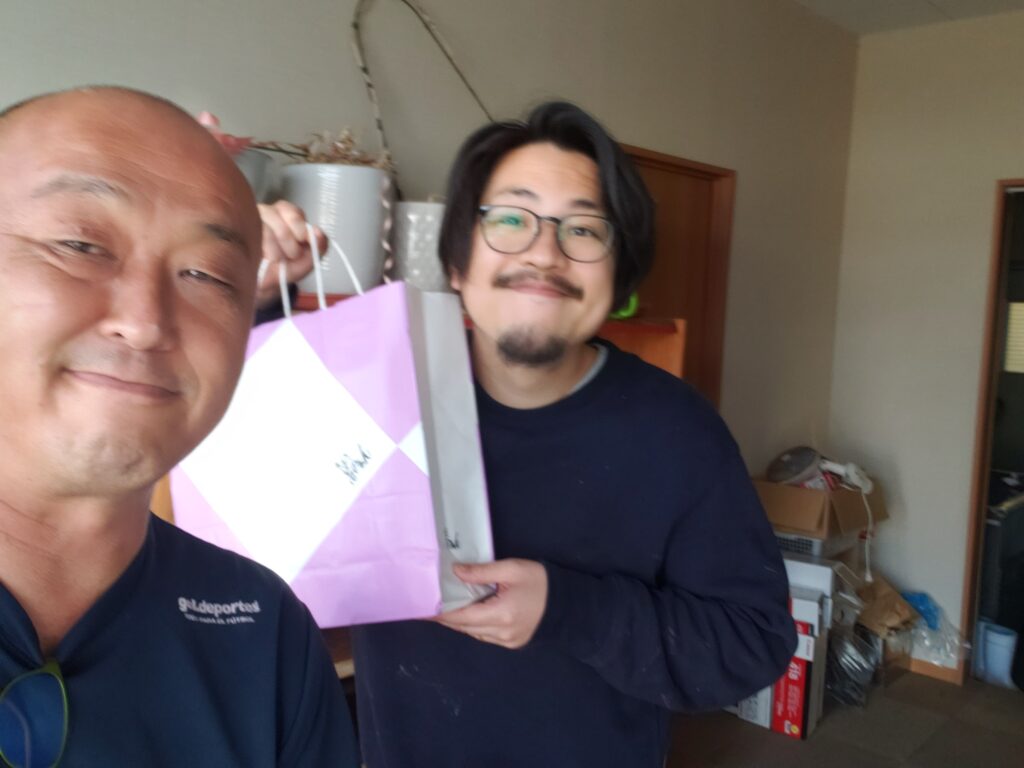
盆明けごろ、このみなさんと名取第一迎賓館で落ち合って、南部タイ行きの結団式をします。海岸林ボランティアにも声掛けて合体するといいなあ。「オイスカの良さは出会い!」と宮城の人からもっと言ってもらえるように。私の頭の中には、ツアー行程シュミレーションは完全に出来上がってます。バンコクの夜は、凄まじい海岸浸食を政府がマングローブで止めようとしているタイ湾まで行って海産物レストランです。
ということで、いつもと違うパターンの、現場を歩かないオタクの休日でした。
6月8日(木) カネボウ労組 ボランティアレポート
吉田です。カネボウ労組30名が全国各地から来訪。「あの葛・藤のツルと戦ってもらうのは忍びないなあ・・・」という気持ちは私にもあります。人間ですから。でもなぜか、その皆さんたちを前にすると、そういう気持ちはどっかに行ってしまいます。習性ですから。


今年は葛の出足がいつもより早いです。真っ先に手を付けたい現場が空港の近くに。2015年植栽地のぼくらが「出島」と呼ぶ、100haで「唯一」、蚊がたくさんいる1ha。林外の畑にかれこれ10年、古タイヤが捨ててあり、市役所に相談したのですが撤去されず、ボウフラが沸く場所になってます。以前オイスカの中野悦子理事長もそこで草刈りをしました。「蚊が多くないうちに」と思ったのですが・・・蚊の出足も早かった。






以上は、蚊がたくさんいた場所。潮風の影響を受けにくい、波打ち際から400m離れた場所にクロマツを「盾」にして広葉樹6種類200本を植えた場所(植栽2016年)。




ここは今日は蚊がいなかった。葛ではなく「藤」のツルが繁茂。
30人で10m×300mの葛と藤ツルを2時間でやっつけました。私が担当した場所は蚊がいなかったのですが、「たくさんいました」と報告されたのは事の後。ごめんなさい。(でも、夕食の時、その話題は出なかったなあ~)今年ここはあと2回ぐらい刈らないとダメでしょうね。藤ツルの太さは親指2本ぐらいの太さでした。
市役所には「古タイヤ10年置きっぱなしの人、何とかして!」ともう一度陳情しますね。皆さん、遠方からありがとうございました。


