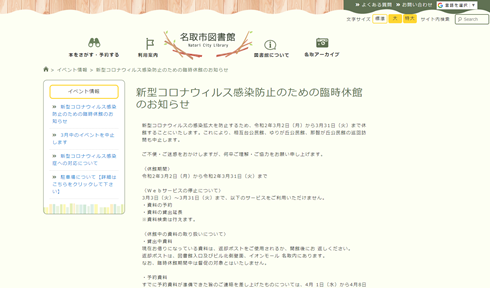いつもと変わりなく、静かです。蔵王おろしの突風の音だけでした。今年は暖冬。小さな苗木の赤変がなくて安心。
林野庁仙台森林管理署の環境調査にはっきり確認したとの記述はないのですが、冬の名取の海岸林には、コミミズクがいます。夜行性なので夕方見ることが多いといいます。群れで飛んでいたという話も地元の三浦さんから聞いたことがあります。毎年1回は見ています。2年前、防風垣の上に留まっているのを気づかずに私が近づくと、本当に面倒くさそ~に、のっそり逃げたのが妙に印象に残っています。1.6mの防風垣から飛び立つと、体が重いのか、一度地面スレスレまでゆったり下がってから、上昇しました。広げた羽が随分おっきいことがインパクトありました。あの姿を見たいがために、冬の実踏は午後から夕方を選んでいます。
ですが、なかなか出くわさない。今年はダメかな・・・
【観察日記】植栽1年後
海岸林担当の鈴木です。
3月5日の吉田のブログ、久しぶりの執筆に力が入っていて、やはり海岸林オタクなんだなぁと改めて思います。
執筆に力が入ったのは、50日ぶりの久しぶりの現場だったこと、活動再開が間近に迫っていて高揚感があったからなのでしょう。
吉田の高揚ぶりは海岸林スタッフLINEでも報告され、着信音がうるさいほど(^-^;
風の音がBGMになった解説なしの現場の動画が8本、
写真がなんと23枚!
深さ1mの位置にマツの根っこを発見したことがよほど嬉しかったらしく、角度を変えて4枚の根っこの写真を連掲
とにかくオタク
オタクよいうより熱いと言った方が正しいでしょうか・・・
でも、
このプロジェクト担当部長の熱さが伝染して、たくさんのみなさんが協力してくださるのだと思っています。
送られてきた写真の中に私にとってもとても嬉しい写真もありました。
東京の事務所で育てた19本のクロマツ苗を去年4月に地元ボランティアの大槻さん、イラストレーターのico.さん、子ども2人と一緒に植えました。(その時のブログはこちら)
その19本のその後の写真です。
最も内陸側の広葉樹の近くに植えたため、海風は最前線のクロマツたちに遮られ、いちばん環境のいい場所です。
守られて育ち、随分と幹が太くなっていました。

葉も濃緑で健康そのものです。

考えてみれば、種からの成長を追えているのは、35万本のうちのこの19本だけなんですね
もう少し真面目に報告しなければならないことを痛感(^^;)
もう少し暖かくなると、背丈がぐんと伸びるだろうと思います。
元気にすくすく育ちますように!!
吉田、1か月半ぶりの実踏
たいへんご無沙汰しておりました。吉田です。
3月5日、半日かけてじっくり現場全体を実踏しました。
11月から2月は、大阪、岐阜、愛知、東京、宮城の支援者訪問や、海岸林以外の業務の助っ人などに明け暮れておりました。ミャンマー中部の国連が{Dry Zone」と呼ぶサバンナ地帯のオイスカ農業研修センター出張など、ECO-DRR(森林など生態系を活用した防災・減災)関連にも力を入れていました。3・4月に予定していたフィリピン北ルソンとインドネシア出張は、コロナウイルスが理由で延期しました。名取のことだけに集中できる時期は、もう完全に終わったと思っています。
ですが、一度名取に戻ってくると現場から離れ難い・・・
歩きたくて歩きたくて、たまらない。
先週、森林総研東北支所の手による、土壌断面調査の新設4ヵ所では、関心のあまり動けなくなってしまいました。
2014年~2016年の盛土工事建設会社の重機オペレーターのおじさんとすごく久々に再会。
おじさん:「吉田さんっすよね~!俺のこと覚えてます~?」
吉:「県の工事に入ってくれてたんですか~。気づかなくてごめんなさい!」
暴風警報の突風が吹いているのに、超!話し込んで。会話の主導権は私でなく、おじさん。ネタは排水対策。工事の効果。自分が手掛けた工事のその後がどうだったか。仲良くなったきっかけは、林久美子さんも一緒にいた時、排水口の作り方とか・・・いろいろ談義したとき。排水口がいつも崩れて、何度もやり直ししてくれていました。
おじさん:「いま作ってる排水路、雨がちょっと降るとすぐ崩れるじゃないですか・・・」
吉:「作ったばかりの盛土は、誰がどうやっても崩れますよ。あとは任せてください!」
今回の宮城出張は、上半期の配布資料を大量に運ぶため、珍しく車で来ました。夜から吹雪になるのはわかっていたのですが、現場を離れたのは日没後。歩き疲れたし、猛烈にお腹がすいて、白石市の日帰り温泉に。帰宅は日が替わっていました。
毎年この時期思うのですが、もうすぐ開幕。腕が鳴るって感じです。
KAIGANRIN REPORT 最新号完成!
こんにちは
海岸林担当の鈴木です。
久し振りのブログ投稿です。
コロナウイルス感染防止のため、行き交う人たちがマスクをつけ、多くの学校が休校となり、人混みに行かない、人の多い閉鎖空間には立ち入らないなど、日常生活が制限されています。
誰もがストレスを感じているこの状況が、子どもが小さいころに読み聞かせた「おひさまパン」(エリサ・クレヴェン 作・絵)に似ているような気がするなと思っています。(こんな悠長な事態ではないとはわかってはいますが)
暗くいてつくような寒さの季節、動物たちは家の中で怒ったり、泣いたり、病気をしたり、ケンカしたり、みなが不機嫌になっている中、犬のパン屋さんが、「本当のおひさまは隠れたままだから、わたしが小さなおひさまを作るってわけ」と、大きなおひさまの形をしたパンを作りました。輝くようなおひさまパンを見て、みんなの心が明るく元気になっていく、そんなお話です。
みんなの心が明るく輝くような「おひさまパン」があるといいのにな・・・ 早く収束することを願うばかりです。
プロジェクトをご支援くださっているみなさんに8月と3月の年に2回、手紙をお届けしています。
年明けから原稿づくりに取り掛かり、数日前にやっとすべての原稿が仕上がりました(*^-^*)
毎回、締め切りまでに間に合うだろうかとカレンダーとにらめっこの日々ですが、今回も2月上旬はヒヤヒヤでした。
何しろ、KAIGANRIN REPORTは前号に続き、また自分で絵を描こうと決めてしまったものですから
頭をひねりひねり今回のテーマを
「『なぜ』が『!!(わかった)』に ~いろんな疑問をDr.清藤に聞いてみよう」 に決め、
甲府市にお住まいのオイスカの緑化技術顧問の清藤先生に取材に行くところから始まり、原稿を書き、イラストの練習を重ね、何とか約1ヵ月で完成!
これですべて終了!というわけにはいかず、大阪マラソンチャリティランナー募集チラシ、名取公民館・図書館でのイベントチラシの制作が残っており、カレンダーとにらめっこして何とか完成しました。
海岸林を身近に感じてもらえること、名取の海岸林の今の状況をお伝えすることを目的にお送りしている手紙です。
手にしてくださったみなさんが、何かを感じてくだされば、送り手をしては嬉しい限りです。
KAIGANRIN REPORTを同封した手紙は、3月9日発送予定です!
イベント中止のお知らせ
パンフレットの設置にご協力いただきました!
名取市図書館 パネル展&イベント
2019年度「北高野球部」溝、役目果たしています!
2018年植栽の最も枯れる確率が高かった個所の一つ3.81ha。
いまのところまったく無事です。
それもこれも溝のおかげ。
ボランティアの皆さんのおかげです。
「県立名取北高校」野球部顧問の榊先生から「今年も!」とメールいただきました。嬉しい!
2019年の溝切り開幕戦は北高野球部溝40m。要の場所です。
この1年、修復なしで役目を果たしました。以来、多くのボランティアで掘りに掘ったり1,150m。
LLサイズ以上だけで。野球部以外もたくさん続いてくれました。
(Mサイズ以下は計測にかなり手間がかかるので測ってませんが、500mは下らない)
2020年度野球部にお願いしたい場所はこの近く。もう決まってます。もちろんこの溝も見れます。
3月31日、楽しみにしています!!
去年はベスト16頑張ったね。本業でも頑張れ!
キツネの巣穴の再利用
一人で現場実踏する際、中央部から南1㎞の範囲で、一瞬で走り去る、体格の凛々しいキツネをかなりの高確率で見ます。今回の踏査でも見ました。やっぱり、いいカラダしてました。でも、人に見せようとするとなかなか・・・去年、浅野さんは閖上の港近くの植栽地で新たに巣穴を見つけています。私は、途中で断念した穴を今回も見つけました。
中央から北1㎞あまりの場所には、下刈ボランティアの皆さんによくお見せするキツネの巣穴があります。去年だったか、この巣穴から出た瞬間、おそらく猛禽類に攻撃された子ギツネの亡骸がありました。その後は、蜘蛛の巣が張り、もう巣穴を使わないのか??と話していたのですが、今回は歩いたばかりの足跡と、掻き出したばかりの砂があり。穴も増えていました。こんなに掘りまくっても、マツが枯れないのが不思議。
「この穴、奥でみんな繋がってるんだよね。随分奥まで穴があるんだろうね」と一緒に歩いた地元オイスカ会員の大槻さん。「またカップルができるんかな~」
キツネが増えたからか、去年はチドリのヒヨコを一度も見れず。2年前はシマヘビが復活。去年は松島森林総合の鈴木純子さんが発見。いる場所は決まっています。広浦沿いの遊水地付近。まだキツネに食べられていないけど時間の問題??。徐々に徐々に、いろいろなことが変化。今年はどんな変化があるのか、本当に楽しみです。
クロマツにとって、とくに重要なキノコとは
目下、名取の現場ではキノコを追って調べている専門家はいない模様です。ですが、現場の推移を観察するうえで、キノコの発生状況について名前を特定できなくても、ブログで多少の写真記録は残してきました。HPブログカテゴリー「いきもの」「傘だけでなく、裏のヒダの写真も撮るとイイ」そうです。現場で見ている限り、キノコがよく出るのはクロマツ成長の良い場所とは限らないように思います。また、クロマツを植えて3年後あたりからはとくに増える感じがします。クロマツとキノコはお互いにとって重要な関係がありますから、海岸林オタクなりに現場の「指標」として考えたいです。マツにとって将来にわたって厳しい条件がいくつもありながら、こうして育っているのはキノコのおかげでもあり、よい育苗場、よい育て親の農家とのめぐり合わせのおかげだと、常々思います。来年度もさらに観察してみたいと思います。
この冬、はじめてキノコの本を2冊買いました。先週、清藤先生が東京本部に出勤した際、とくにクロマツの生長に寄与する代表的なキノコに付箋をつけていただきました。先生はあっさり片づけてくださりました。震災前に海岸林で発生していたかどうかは別として、また、2冊に掲載されていたキノコだけですが。写真は「きのこ図鑑」より引用

![ショウロ OIP[5]](http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2020/01/ショウロ OIP5-300x223.jpg)
ショウロ:早春・晩秋発生。マツ林の代表的キノコ。全体は黄褐色で歪んだ球形、表面にピンク・赤色の斑点。甘い香り。断面はスポンジ状。基部に根状の菌糸束がある。震災前も発生。育苗場では発生したが、まだ植栽地では見たことはない。

![キツネタケkitunetake-e[1]](http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2020/01/キツネタケkitunetake-e1-241x300.jpg)
キツネタケ:夏秋発生。傘・ヒダは黄褐色(キツネのような色…)。傘の肉は柔らかいが柄は固い。基部に白色の菌糸体。食用。よく見ます。

![ヌメリイグチnumeriiguchi_2[1]](https://oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2020/01/numeriiguchi_21.jpg)
ヌメリイグチ:夏秋、比較的開けた場所に発生。傘は粘性、褐色。チチアワダケと似ていて、つばがなくなると識別困難。林業用接種でも使われるらしい。よく見ます。
![アミタケamitake_2[1]](https://oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2020/01/amitake_21.jpg)
アミタケ:夏秋発生。マツ林の代表的キノコ。粘性。オウギタケと混生する。調理で加熱すると赤紫色になる。食用。震災前も発生。食べたことあります。
![チチアワタケchichiawatake_1[1]](https://oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2020/01/chichiawatake_11.jpg)
チチアワダケ:夏秋発生。傘は明褐色で粘性。つばを持つ。加熱すると紫色になる。植栽地では非常によく見かける。林業用接種でも使われるらしい。よく見ます。
![ツチグリtsuchiguri_1[1]](https://oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2020/01/tsuchiguri_11.jpg)
ツチグリ:夏秋発生。球形で、成熟すると外皮が星状に剥がれ、革質のような内皮の中から胞子を出す。まだ植栽地では見たことはない。

ドクベニタケ:夏秋発生。有毒。赤色のベニタケ属は最も識別困難なグループ。まだ植栽地では見たことがない。
![ハツタケhatsutake_1[1]](https://oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2020/01/hatsutake_11.jpg)

ハツタケ:夏・早秋発生。震災前に発生。マツ林の代表的キノコ。傷つくと暗赤色の乳液を出し、のちに青緑色に変色。傘は淡紅褐色で環紋模様がある。ヒダはワイン色を帯びた淡黄色。食用。まだ植栽地では見たことがない。この青いの見たことあります。

アカハツ:夏・秋発生。ハツタケと区別しない地域もある。傷つくとのちに青緑色に変色。傘は橙赤色で不明瞭な環紋模様がある。ヒダ・柄は傘と同色。柄は短い。食用。まだ植栽地では見たことがない。

クロハツ:夏秋発生。猛毒。傘は灰黒色。ヒダは疎。

シロハツ:夏秋発生。全体は白色、中央に沈む。ヒダはやや密。柄の頂部が青色を帯びる。食用。見たことあります。

キシメジ(キンタケ):秋発生。マツ林の代表的キノコ。傘は5㎝前後ですすけた黄色。ヒダは黄色。食用。震災前も発生。見たことあります。

アンズタケ:秋発生。傘は鮮明な黄色。ヒダが乱れる。