ボランティアふたたび再開!
こんにちは、浅野です。
7月4日の宮城県民向けの活動を最後に中止していたボランティアの受入れが9月12日に再開しました!
2か月ぶりのボランティア♪と楽しみにしていたのですが、あいにくの雨予報。
前日には土砂降りの予報となり、急遽お申込みいただいてた皆さんに連絡を取りました。
「警報も出そうな予報なので、作業はやらないで見学だけになるかもしれません」と伝えると
遠方の方は「もう行くつもりで色々準備したから行くよー」と言ってくれて、
近くの方は「久しぶりにみんな来るんでしょ?顔見に行くだけでも行くよー」と。
結果、申し込みをしてくださっていた方のほとんどが参加してくれました!
当日は予報通りの土砂降り。
午前は車に分乗して名取の植栽地の見学を行いました。
土砂降りの中、車を乗り降りするのはよくないということでLINEミーティングを使って
吉田の説明を車内で聞きながら進むことに…オイスカらしくない試みですね。笑
雨が弱まったタイミングで車から降りての見学も交えながら久しぶりの現場に皆さんイキイキとした様子でした。
午後は「どうしても作業をやりたい」という声があがったのでツルマメの抜き取りを行うことになりました。
午前ほど雨は強くなくカッパを着ていれば作業は可能でしたが、さすがに長時間の作業は推奨できないので、
1時間ほどで切り上げ、15時には完全に解散しました。
今年は出るのが遅かったツルマメですが、場所によっては7、8月の雨と夏の太陽を浴びてすくすくと成長したものも
あったようです。久しぶりにモンスタークロマツを見ました…。

9月26日に参加予定の皆さん、クロマツの救出にご協力よろしくお願いします!
いよいよ本に! –その3–
こんにちは
海岸林担当の鈴木です。
3連投
私が書籍用に用意したものはイラストと写真。
基本的にはこれまで冊子に掲載してきたものを使用するのですが、
プラスαで
・巻頭のカラーページに掲載する書籍の顔ともいう写真
・冊子には掲載できなかったけれど、あれば文章理解を進むであろう写真
・まだ刊行していないVol.13とVol.14用の写真
の選定をしました。
選定するといっても、これまでプロジェクトで撮ってきた写真は数万枚
その中から選ぶのですから、相当なもの
いい写真はたいてい印刷物やブログなどで使用しているのですが、他にも掘り出し物があるはず・・・という考えのもと、写真フォルダを開けて上から下まで見て、また別のフォルダを開けての作業の繰り返し。
やっと見つけても
「この写真、どっかで使ってたよね・・・」と小林さんからひと言あれば、また探す・・・・
それでも適当な写真が無ければ、持っていそうな方に連絡して提供していただく。
再生の会の方々が作業をしている写真は、数万枚から再生の会の方が写っている写真2841枚を選びだし、その中から選んだ1枚です。1枚の写真の裏に2841枚が重なっているのです!!
映画のヒロインのオーディションのような高倍率(^^;)
編集者への提出期限間際に写真の提供をお願いして、快く対応してくださったボランティアの三浦さんには感謝感謝です。ありがとうございました。
書籍はやっと原稿が編集者へ渡ったところです。
この後、書籍用に編集の作業があり、写真のレイアウトをし、表紙を決め、帯をつけなどと作業が続いていくものと思います。
書籍発刊は11月中旬~下旬を予定しています。
詳しいことが決まったら報告します!
楽しみにお待ちください(*^-^*)
私自身、どんな表紙になるのか、とても楽しみにしているところです
いよいよ本に! –その2–
こんにちは
海岸林担当の鈴木です。
昨日のつづき
小林さんが火だるまになりながら原稿執筆をしている横で、
近くでお尻を叩いていただけ!? まぁそんなようなものですが・・・
『よみがえれ!海岸林』を書籍にするにあたり、
「海岸林って必要なの?」
「何か効果があるの?」
「クロマツばっかりだけど、他の木じゃだめなの?」
など、素朴だけれど核心をついた質問に解答しようと、イラスト入りの解説ページを設けています。
どんなイラストが伝わりやすいか、イラスト内で伝える内容は何か?などを考え、イラストレーターさんとのやり取りを通じて、
あーでもないこーでもない、
こうした方がわかりやすい、
このイラストはもっと右にあった方がわかりやすい、
ここの表情は笑っていたほうがいい
などなど、細々した調整をしてイラストを完成させていきました。
イラストレーターさんは、いつもお世話になっているico.さん。
ico.さんは、こちらの要望を汲んで、どんぴしゃのイラストにしてくださるすごい方なので、なくてはならない存在です。
数種類のイラスト作成で苦労したのは、
○海岸林の防風効果は何キロ先まであるのか?
○海岸林を通り抜けると塩分減少率はどのくらいになるのか?
を調べること
まったくの専門外で、何を参考にすればいいのかすらわからない状態
手さぐりで論文を何本も読みました。最初のうちは、書いてあることの半分も理解できず、ちんぷんかんぷん。それでも、ガマンして読んでいると、何となくわかってくるものですね
やっと適当な論文を探し当て、イラストに反映させました。
でも、イラスト内で反映するのは「375」と「1500」たったこの2つの数字のみ。この数字の後ろに何十時間もの苦労が隠れています!
楽しかったのは、
松くい虫の被害拡大についてのイラスト制作!
こちらも訳が分からない論文を何本も読みました。
「マツノマダラカミキリ」と「マツノザイセンチュウ」の絶妙な共生ぶりに驚き、
「マツノマダラカミキリ」の蛹の芸術性の高さにまたまた驚き、
「マツノザイセンチュウ」10000匹を体の中にかかえた「マツノマダラカミキリ」を妄想して笑い、
驚きと笑いの連続でした。
でも、このたった1㎜の体長のセンチュウに感染して、枯れてしまうマツの大木を思うと、笑ってもいられず、深刻ですが・・・・・
そして、研究を続けたいのは
宮城県の海岸林は本当に伊達政宗が命じて作られたものなのか?
というギモン
いまのところそのような史実はないという説ですが、地理学に長けていたといわれる政宗が仙台市や名取市の海岸に立ち、農地を守るため、津波から命を守るために
「このあたりに雄松(クロマツ)を植えよ!」
と、本当に命じていたらかっこいいな~
と、これまた妄想しています。
何をどう調べたら、こんな史実は出てくるのだろうか??
このギモンにつまづき、「名取の海岸林史」をつくるのに相当な時間がかかってしまいました。
相当な時間がかかったものの、
これまで知らなかったことを知る楽しさを味わいました。
~ また明日へつづく ~
いよいよ本に! –その1–
こんにちは 海岸林担当の鈴木です。
しばらくのご無沙汰でした。
事務所の下の階に保育園があるのですが、ちょうど1歳児ちゃんのお部屋を見ることができます。
まだ歩くのもおぼつかない子もいて、見ているだけで幸せ気分です。窓際にいるベビちゃんたちに手を振り、癒されています。手を振り返してくれる子がいると、その日は一日幸せ気分です(^^♪ ・・・・このところの私の楽しみです。
前置きが長くなりました
ここしばらく、元日経新聞論説委員でオイスカアドバイザーの小林省太さんが執筆している冊子「よみがえれ!海岸林」の書籍発行のための準備にかかりっきりでした。
冊子「よみがえれ!海岸林」は、小林さんご自身の視点で見たプロジェクトを綴ったもの。
2018年6月から発行を始め、現在Vol.12まで発行されています。
聞きなれない林業専門用語が出てくるような林業の技術書ではありません。
プロジェクトの正当性を証明しようと、独自に取材先を選び、丁寧に取材を重ねて綴った「プロジェクトX」的とも言えばわかりやすいでしょうか。
これまでの取材先は、50人近くになっているはずです。
近くで仕事ぶりを見ていて、新聞記者で培われた記者魂、まさにプロを感じます。
冊子「よみがえれ!海岸林」は、オイスカ会員さん、プロジェクトの支援者さんにお届けしていますが、この内容は決してオイスカの内輪だけに留めておくものではなく、広く世の中に送り出して、多くの人の目に触れて欲しい内容です。
海岸林を再生する道のりでの人々の葛藤
プロジェクトの原動力
地元住民の想い
ボランティアさんの想い
など、かかわる人々の心の内も綴っています。
災害が発生し、同じように何かを再生しようとした時、交錯する「想い」を同じ方向へ向ける難しさを「感じる」内容です。次世代を担う中高生にも手に取ってもらえるように、簡単な言葉で語っています。
冊子の内容を書籍として世の中に送り出したいと願っていた時、
偶然にも陸前高田市出身の編集者と出会い、書籍化が実現することになりました!
発刊時期を検討し、最終的に11月中に落ち着き、
逆算して、原稿締切は8月末・・・・・・お尻に火が付くどころか、体中が火だるまだよ と言いながら、小林さんは書籍用の原稿を書き進めていきました。冊子では、誌面の関係上、書ききれなかった内容を、「膨らし粉を入れてるところ~」と言いながら書き加え、締切の1週間前まで名取市に出向き、取材をし、2年前の内容を「いま」に書き直し、書き上げていかれました。
そして(締め切りを4日延ばしてもらい)9月4日に原稿を提出し終えました。
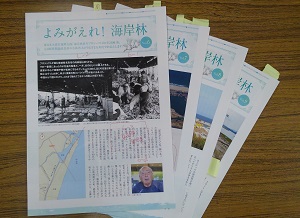
原稿執筆はすべて小林さんのお仕事で、私は近くでお尻を叩いていただけ!
というわけではなく、何をしていたかというと・・・明日へ続く
「生物多様性調査報告(林野庁)」種数の増減抜粋
こんにちは!インターン生の嶋村です。
私は、国際基督教大学の三年生で、開発学を専攻しております。オイスカでのインターンに応募したきっかけも開発学を実践する方法を学びたいという想いからでした。開発学では困難に直面している国や人々をいかに豊かにしていくかを学んでいます。そこで、実際に海外開発協力など開発に直結する活動を行っているオイスカで、その学びを実践に活かす力が身につけられると考えたのです。
オイスカで行われている様々な取り組みに関わらせていただく貴重な機会を沢山頂きました。海岸林再生プロジェクトの仕事にもご縁がありましたので報告させていただきます。
東日本大震災が発生した2011年、私は11歳でした。テレビで放送される津波の様子を目にし、状況を理解できないままに恐怖を感じたことを覚えています。11歳の私にとってその映像は衝撃的で、約10年たった今でも鮮明に思い出すことができるほどです。震災発生当時、これほど大きなショックを受けた私でしたが、振り返ってみると記憶に残っているのは震災それ自体の衝撃ばかりで、被災後のことをしっかりと考えたことはありませんでした。テレビでの放送を見て、復興支援のことはなんとなく知っている、その程度でした。
そんな私ですが今回、クロマツ植栽地の生物多様性についてのブログへの掲載を手伝わせて頂くことになりました。これをきっかけに、被災地の復興についても、改めて多くの学びを得ることができました。
「2019年度 名取地区生物多様性調査報告書」( 仙台森林管理署)より、プロジェクト開始して間もない2013年から2019年までの生物の種数の遷移が掲載されている箇所を抜粋しました。ものすごく分厚い報告書です。「公式な調査が名取でおこなわれたことは、ものすごく光栄だし、幸運。このような調査は、オイスカのような民間団体単独ではとても出来ない。毎年、結果をとても楽しみにし、仕事の励みにしてきた」と吉田さん。
【名取地区全データ】
| 2013 | 2019 | 増加数 | |
| 植物 | 299種 | 369種 | 70種 |
| 昆虫類 | 286種 | 362種 | 76種 |
| 鳥類 | 36種 | 48種 | 12種 |
| 哺乳類 | 5種 | 3種 | -2種 |
| 両生類 | 3種 | 3種 | ±0種 |
| 爬虫類 | 2種 | 1種 | -1種 |
| 魚類 | 8種 | 4種 | -4種 |
| 底生動物 | 4種 | 15種 | 11種 |
*鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類、魚類、底生動物の2019年データは、内陸側保護スペースの調査。
*最終調査報告(要旨)は、今秋、林野庁東北森林管理局のHPで公開される予定です。
全体を見ると、生物種数がかなり増加しています!
*これまで現場で確認した生き物の話題(ブログカテゴリー「いきもの」)
本プロジェクトの担当部長である吉田さんのお話によると、正しい施業を心がければ多様な生物がそれに伴って育つそうです。この調査結果から、クロマツが丁寧に育てられていることが一目でわかります。防災林としてだけでなく、生物多様性を保全する役割も担っているのです。
今回、このように海岸林再生プロジェクトに関わらせていただきましたが、オイスカで活動させていただく以前は、このような活動が行われていることすら知りませんでした。そこで、プロジェクトについて丁寧に教えて下さったのが、担当部長の吉田さんです。何も知らない私にとって、驚きの多いものでした。特に印象的だったのは、このプロジェクトが被災された方々にとって、「防災林の植栽」以上の意味を持つというお話です。活動が現地の被災された方々のコミュニケーションの場所になっていることや、震災により壊滅的な打撃を受けた場所に種から緑を育てること自体に、復興の希望が感じられていることを知り、意義の大きさを感じました。
また、吉田さんの言葉の一つ一つには熱がこもっていて、関わっている皆さんが強い想いを持って活動されていることが伝わってきました。「月面に植物を植えるようなもの」とも言われた被災地でのクロマツの植栽ですが、約10年でここまで立派なクロマツが成長したのは皆さんの強い想いがあってこそだと感じさせられました。
このように、私のように「何も知らない」という人もいると思います。少しでも多くの人にこの大切なプロジェクトが伝わればと思います。
注目! 上空からの定点観察写真(2011-2020)
近々ドローン撮影を計画しています。皆様への報告用はもちろんですが、隅から隅まで現場の施業状況を確認したいので。撮影は早ければこの週末にも。本当は木々が分かりやすく、天候が安定している5月に撮影したかったのですが、コロナで身動き取れず。松島町の「三立重建」さんにお願いしています。先週26日にテスト撮影をしていただきましたので、最新の写真と過去の写真を比較ください。
以下、2014年・2015年植栽地27haの定点観察(名取市海岸林「中央」から南を望む)
ボランティア再開します!!
こんにちは、浅野です。
7月4日のボランティアの日を最後に中止をしていたボランティア受入れですが、9月12日より再開します!!
7月、8月と予定されていた受入れは全て中止となり、3月からの中止期間も含めてのべ1050人のボランティアが
キャンセルとなりました。中には年に1度だけしか来られない方や遠方からの参加を予定してくださっていた方もいて、中止の連絡をするのが本当に心苦しかったです…。
6月末のボランティアは宮城県民限定での開催だったため、全国からの受入れは昨年の11月以来9か月ぶり。
その間はプロに草刈りを委託し、背丈が伸びるタイプの雑草はきれいに刈ってくれました。
多くの方が気になっているツルマメは、地元のリピーターの皆さんが自主ボランティアとして
抜き取り作業をしてくれています!(すでに2回終了、3回目も予定してくれているようです)
もちろん、コロナ禍であるということを忘れずに三密を避け検温や消毒作業は徹底します。
参加される方は下記にご協力ください!
【参加者へのお願い】
・作業時以外はマスクを着用ください。
・ご自身が使うための消毒用品をご持参ください。(アルコールジェルなど)
・自宅を出る前に検温をし、平熱より1℃以上高い方は参加をご遠慮ください。
・宮城県民の方は、極力自家用車でご参加ください。
・宮城県民の方は、極力着替えの必要がない恰好でご参加ください。
・ごみは回収できませんので、全てお持ち帰りください。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます!!
海岸林で鳥見ing(2020/8/15)
地元のボランティアの三浦隆です。
名取市の海岸林で観察した生き物、主に野鳥を中心とした情報、話題の6回目を発信したいと思います。
海岸林オタク、富士山に登る
広報室の林です。
オイスカは「海岸林再生プロジェクト」以外にも
国内各地でさまざまな森づくりに取り組んでいます。
同プロジェクトと同じ100ha規模(植栽は約4万本)
の植林を行っているものに「富士山の森づくり」の活動があります。
そのプロジェクト名の通り活動地は富士山。
「海岸林再生プロジェクト」と同様に、富士山の活動地でも今年は
ボランティアさんを受け入れての活動ができずにいます。
そんな中、担当スタッフが調査活動を行うというので、
吉田と一緒に参加してきました。
この日の道具はこちら。
「海岸林再生プロジェクト」の現場でも調査を行いますが、
この中には、私は使ったことのないものも。
今回の調査は、風などで倒れた苗木の本数を調査するので、
健全な木と倒れた木に色付きテープで印をつけ、それぞれの本数を
2つのカウンターで数えていくのです。
こちらは健全な苗木。
ピンクのテープをつけています。
こんなふうに倒れてしまったものには黄色のテープ。

※ちなみに黒いネットはシカなどの獣害対策用。
途中、こんなふうに林内に落ちている枝の皮が
シカに食べられた跡をみて、ネットの必要性を実感。
周りにはシカのフンが大量に落ちていました!!!!
吉田は作業着のポケットにこのテープを入れて作業へ。
……が、ここでも何かを見つけて写真撮影。
キノコではありません。キツネでもありません。
カメラの先にいたのはちょうちょ。
アサギマダラだと担当スタッフから教えてもらいました。
何だと思いますか??
実はこれ、吉田の靴の底。

久しぶりに履いた靴で劣化が進んでいたようで、
両足とも底がはがれてしまいました(笑)
そんな吉田が最後に見つけたのは……

なんと、シカの頭蓋骨!
越冬できずに死んでしまったシカでしょうか?
海岸林の現場でも動物の骨を発見しては嬉しそうにしている吉田。
ここでも最後にシカと遭遇できて満足そう。

富士山で進む森づくり活動。
今日は吉田の活動の様子を中心にお伝えしましたが、
現場の様子をぜひ知っていただけたらと思います。
マングローブを植えられない場所での海岸防災林造成に向けて
2013年に巨大サイクロン「ハイエン」がフィリピン中部を襲ったこと、ご記憶にあるかと思います。レイテ島タクロバン市の名前が知られました。
これまで日本でも苦労して造った海岸防災林が、継承力のなさや無知により、機能をわざわざ弱めるように開発された例は多々あります。世界と同じです。海沿いギリギリまで人は土地を求め、マングローブは切り倒されました。荒れ地になったいまも、土地の権利関係はとても複雑で、タイでは、悪質な不法占拠者に対しては裁判を起こしででも、あるべき姿に戻そうとしています。防災機能を高めるために造林出来る「公有地」は限られるのが実態なのです。
そんななか、東京本部海外事業部の長部長や清藤先生たちは、マングローブを植えられない砂浜海岸でも、小砂丘かつ貧栄養土壌のわずかなスペースでも「海岸林」なら出来るのではないかと考えました。
折しもサイクロンの後、1980年代後半にオイスカがモロカボック島(セブ島の西の小島)に植えたマングローブ林が漁村を守ったことが確認されました。マングローブ林の林帯幅が狭い個所でも、砂丘にわずかでも森林があれば防災機能はその分だけ強くなります。マングローブを植えられない場所もたくさんあります。潮流の影響など・・・理由は実にさまざま。海岸林の幅が確保できる場所も少ない。1列、2列・・・という世界も多いと思います。しかし、「これまで行ってきた沿岸部造林はすべて失敗した」(フィリピン天然資源環境省レイテ島担当者)とのこと。まずは、育苗が大事で、その次に植栽方法を確立しなくてはなりません。オイスカでは2015年から3年間、外務省のNGO連携支援無償を活用し、災害に強い森づくりを行うとともに、2016年から2019年まで国際緑化推進センターからの助成をいただき調査研究しており、その成果が公表されております。
資料公開:森林再生技術普及セミナー「3.ヤシ殻等を利用した海岸砂丘林造成技術開発」
この前、長部長にいくつか質問をしたのですが、造林としてはまだ未解明な点があると知りました。林産物による収益性にも課題がある。ですが、探すのに困らないものを有効に使った低コスト・高生存率の苗木生産方法、植栽方法の解明は有効。この次の展開が楽しみです。





















-070-300x199.jpg)



























