どうやったら伝わる?
広報室の林です。
普段、成長がよく、育った木の生育具合をどうしたら写真で伝えられるかを考え、
背の高い吉田と並べて撮影したり、脚立を使ってみたり……。
でも、全部の苗木が5m級の成長をしているわけではありません。
個体のもともとの問題もあれば、水はけが悪いといった環境の問題などから
生育がよくない場所や苗木も見られます。
今回はそれが分かるように写真を撮ってみました。
同じ年に植えたのに、奥の方に見えるマツは柵を超えていて
手前の方は柵よりも背が低いマツが多いのが分かると思います。
色の濃さも違います。
そしてあまり大きくなっていないマツを撮影しようと比較物を探し
自分の長靴(ひざ下)と比べたらいいかなぁと。

でもなかなかうまく収まってくれません。
そこで長靴だけ置いてみることに。

どうですか?
私のひざ下ぐらいにしか達していないこと、伝わりました?
撮影って難しい……
11月3日(火・祝)ボランティアの日開催します!!
こんにちは、浅野です。
今年はコロナウイルスの影響でほとんどのボランティア活動を中止しました。
9月に入り全国からの受入れを再開してからは天候不良で3回中2回を中止。
ツルマメ抜き取りの時期は過ぎてしまいましたが、やりたいことは山ほどあります。
なので、11月3日(火・祝)に臨時でボランティアの日を開催することにしました!
モニタリング調査をメインにプロット看板設置やごみ拾いなどもやりたいと思っています。
参加される方は防寒着、防チクチクをしっかりしてきてください!
皆さんのご参加、お待ちしてます!!

ここは名取に来たことのある方は1度は見たことがあると思います。
北釜地区に1軒だけ残っている家です。
「鈴木会長は震災を風化させないために」とこの家を残しています。
家の前には小さな小屋を建て震災前の写真と震災後の写真、
津波がどれほど恐ろしいものだったのかが伝えられています。
http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=24946

そんな小屋にハチの巣が…しかも小屋の中と外に2つも…。

なんか大きい…。
飛んでいる姿はアシナガバチですが、よく見るフタモンアシナガバチではありません。
ボランティアの皆さんを連れていくこともあるところですし、この時点ではハチの種類も分からず、
刺されたら危険だという判断のもと駆除することに決めました。
刺されると困るので、少し窓を開け車の中からハチノックを噴射!(吉田さんが)
相当数のハチが巣の周りに落ちました…。
少し経ってからハチの種類を確かめに行くと2㎝~3㎝の大きなハチがたくさん。


調べてみると、セグロアシナガバチかキアシナガバチということが分かりました。
(どちらのの特徴があるものもいたので、どちらか確定ができませんでした…)
ただ、どちらもアシナガバチの中では毒性が強く、
刺されるとアナフィラキシーショックを起こすこともあるということでした。
駆除して正解だったとは思うのですが、巣に帰ってきたハチを見てすごくいたたまれない気持ちになりました。
来年は駆除されないような、人が来ない所に巣を作ることを願います…。
こんにちは。林です。
先日、森林組合の皆さんが植栽作業をしている間、
松島森林総合のSさんにご協力いただいて
ニセアカシアをやっつけてきました!
いつも吉田が説明するのは、ニセアカシアは侵略的外来種であるということ。
少し調べると、外来生物法において要注意外来生物に指定されているとの説明も見られます。
クロマツ林の中で見つけたらすぐにやっつけたい相手です。
使う道具は上から除草剤、水色スプレー、ハサミ。
太くなってしまったものはSさんがノコギリで切ってくれました。
その根元に除草剤をたっぷりかけます。
そして、そこにスプレーで印を。
トゲが痛いので、切り取った部分は防風柵の中に。
あ~スッキリした。
ごめんなさいっっっ~~~!
広報室の林です。
先日、2018年度の植栽地のツルマメ抜を浅野と一緒に抜いていたのですが、
浅野は途中から別の作業のため離脱。遠くでみんなの声は聞こえるものの
1人で作業する心細さを感じていた時のこと。
急に1メートルぐらい先の茂みから
キジが飛び出してきてビックリ!!
思わず口から出たのは
「ごめんなさいっっっ~~~!」。
キジにもびっくりしたけど、
「ごめんなさい」と叫んだ自分にもびっくり。
写真はその時に見たキジとは違いますが、
現場にはけっこうたくさんのキジが住んでいてよく見かけるのです。
でもこちらの存在に気付いたら、1メートルまで接近する前に
逃げていってくれたらこちらもびっくりしないですむのですけどね……。
12分、貸してください!
広報室の林です。
先日倉本が報告していた塚本カメラマンは
これまでもプロジェクトの動画を手掛けてきてくださいました。
その塚本さんが先日撮影した映像を編集してくださっている際に
電話で話をしていると、こんなことをいわれました。
「一番最初のビデオ、あらためて見たんだけど、
あの時点で言ってる10年計画の通りにやってきたことがわかって
オイスカってすげ~なぁって思ったよ。もう一回見てみなよ」
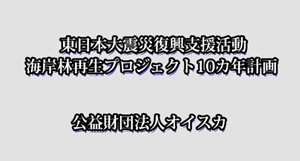
久しぶりに私も見てみました。
ゼロからここまでよく来たなぁ~と
いろいろな思いが胸に迫ってきました。
動画をYouTubeに上げるってどうするの??と
教わりながら作業をしたことも思い出しました。
そして気になったのが、ナレーションの声。
そういえば、私がやったんだっけ……。

事務所の3階の和室で録音をしたなぁ。
お聞き苦しいナレーションですが、
プロジェクトの始まりが分かる内容になっています。
お時間がある時、12分ほどのこのビデオ、
あらためて見ていただければと思います。
このほかのビデオもありますので、よろしければご覧ください。
広報室の林です。
今週、「海岸林再生プロジェクト」の最後の植栽が行われました。
6日には名取市長も来られましたが、ただの記念植樹ではなく、
植栽前の場所に生えているツルマメの抜き取りや植える苗木の準備等
(根の部分を吸水ポリマー液に浸して、苗木袋に入れて担いで移動)も
体験していただきました。オイスカは市長相手でもスパルタです(笑)。
オイスカの関係者、約20名で植えたのは約150本。
ほんの1区画です(高所作業車から撮影)。

森林組合のプロたちは1人で500本植えるそうです。
150本は、2年目の若手でも午前中で終える本数。

若い彼に「下刈りと植栽どっちがいい?」と質問。
「どっちもやんだ!」(どちらもいやだ!)
即答でした(笑)
若いとはいえ、どちらも体にこたえる重労働です。
もくもくと作業に取り組んでくださる皆さんには本当に頭が下がります。
ありがとうございます!
こんにちは、浅野です。
10月10日(土)のボランティアは中止とすることが決まりました…。
今年はコロナの影響で3月~8月のボランティアがほとんど中止、
宮城県民対象のボランティアも9月のボランティアもほとんどが天候不良でした。
そして今回は台風…思うようにいかないものですね。
仕方ないので、クロマツに頑張ってもらいましょう。
次回は11月、リピーター向けのボランティアです。
作業はモニタリングですので参加される方はチクチク対策をしっかりして来てくださいね。
5m前後のマツのモニタリングをする場合は顔に松葉が当たることもありますし、
下手すると目にマツが入る可能性もゼロではないので…。
10月6日 メディアの取材を受けました!
こんにちは
海岸林担当の鈴木です。
9月中旬ごろ、最後の植栽をぜひ取材してもらおう!と、浅野がプレスリリースの内容を練りに練り、何度も手直しを加え、
取材に来てくれるかな・・・??と、期待と不安を感じながら9月28日にリリースしました。
なんとなんと!
10月6日に NHK仙台、東日本放送、読売新聞、河北新報
10月7日に みやぎテレビ
が取材に来てくださることになりました。
6日は、高所作業車からの遠景の撮影、山田司郎名取市長の現場訪問、名取市での最後の植栽が始まったことと、取材の材料が多く揃っていました。
植栽する前の苗の準備
森林組合の作業員の植栽の様子
植栽地でやっかいなツルマメ草抜き取りの様子
山田市長の植栽の様子
あいま合間に浅野や再生の会の鈴木会長、オイスカ理事長の中野へインタビュー
そして、高所作業車での遠景撮影
と、取材いただき、
できあがったのがこちら
NHK仙台でお昼のニュースで流していただいたものです。
(NHKは午前中の取材でしたので、残念ながら山田市長の植栽の様子を取材いただくことはできませんでした)
NHK仙台放送 (放映日時10月6日12時21分)
(※10/6~12まで視聴できるようです)
こちらは、ラジオで放送されたものです。
全国放送 NHKラジオ第1「武内陶子のごごカフェ」全国放送 NHKラジオ第1「武内陶子のごごカフェ」全国放送 NHKラジオ第1「武内陶子のごごカフェ」
(放送日時10月6日13時37分ごろ)
↑上記の残り時間13分21秒くらいから
(※10/6~12まで視聴できるようです)
今日は、継続して取材いただいているみやぎテレビの取材が入っています。
どのような映像に仕上げてくださるのか、楽しみです!


















