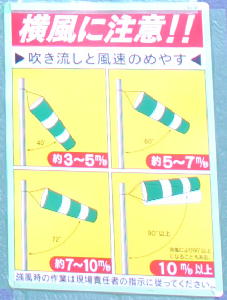出張報告 5 ~沖風が吹き始めた~
出張報告 4 ~名取測候所~
「海岸林は防霧の効果も持つ」
防霧保安林も各地にあります。
昨年、秋山君がインターンの面接に来た際、最初に腕試しに「仙台管区気象台HPの気象データを自分なりに分析してみて」と頼んだ事を思い出しながら、とうとう自分で仙台空港管制塔の建物の中にある名取測候所を訪ねることに。

16:00過ぎ。
大勢人がいます。初めて行きましたので驚きました。
写真は朝番と夜番の人の引き継ぎ風景です。
「霧発生日数」を含む気象データをいただきましたが、海岸林が無くなる前と後で、霧発生日数の変化がどうかは、素人が簡単に判断出来る事ではありません。
仙台空港に勤務する複数の人から、昨年の濃霧について聞いており、どの様に表現できるかは、じっくり専門家の話や地元の人の話を聞いてみたいと思います。
ある方からは、「反当たりの収量も調べる価値があるのでは」とのアドバイスを頂きました。
「富山の黒部では、海岸林造成で農家の方が非常に喜んだ」との話を聞いた事があるとも伺いました。
どなたか、何かご存じありませんか?
どこに行けば良いものか。是非欲しいデータです。
飛砂・飛塩調査 その1
6月3〜4日、宮城県名取市・岩沼市にて、オイスカの吉田さん、秋山さんと一緒に、飛砂・飛塩調査をおこないました。
この調査は、海岸林があることにより、海側から内陸に飛んでくる砂や塩分の量がどの程度防がれているのかを計測することが目的です。
昨年秋に、新潟大学農学部の権田先生・川邊先生に、調査方法をご指導いただいた末に、今回の実施となりました。
調査地点は二カ所で、海岸林が完全に失われてしまった場所(名取市閖上(ゆりあげ)地区)と、ある程度残存している場所(岩沼市南浜地区)に設定しました。いずれの場所とも、海岸の目の前・約400メートル後方・800メートル後方のポイントに、砂や塩分を捕捉する器材(ガーゼを空中にさららして飛んでいくる塩分を吸収/地面にカップを埋めて砂を捕捉)を設置して、24時間置いたのちに回収しました。
海岸林が残存している場所では、林を間に挟んで前と後ろに設置することになり、砂や塩分が飛ぶのを食い止める効果が予想されます。
調査結果は、このブログで追って紹介いたします!



(アース・ブレークスルー 菅 文彦)
出張報告 3 ~盛土工事~

アリジゴクはお寺の軒下にいるものと思っていました。(笑)
この前、踏査をしている時に、どう考えてもアリジゴクの穴が。
しかも、たっくさ~ん。
アリもいるのでつい地が出て、小学生に戻ってしまい、
同行していた秋山君と菅君の両方から「いい加減にしろ」と。
アリをゲットしようとして、底から砂を掛ける様は、ミクロながらも迫力満点。
しかし、アリもさるもの。一度も捕まりません。
海岸林が倒伏して晴天に晒されるところにもアリ、いるんですね。
サラサラした砂があればイイのでしょうから。
津波で海から砂が押し寄せて良い環境が出来たのでしょうが、震災前は暗い森だったはず。
元はサラサラした砂があるところではない。
あんな小さな、歩く事など不得意そうな生き物が
どうやって来たのでしょうか?
震災後、ヘビは全く見なくなったとの話を聞きました。
ネズミは居るそうです。
出張報告 1 ~とんちゃん~
プロジェクト担当の吉田です。
飛砂・飛塩調査と、気象庁仙台管区気象台名取測候所での霧に関する聴き取りのため、
海からの風が吹き始めるこの時期に、NGOアース・ブレークスルーの菅さんといつものように名取に来ました。
「極楽湯」に行き、潮風でベトベトからサッパリ。
「サッポロ食堂」で「とんちゃん」を買いました。
タレとお新香はサービス。
「とんちゃん」とはホルモン焼きのこと。
こちらに来るとよくふるまわれるのです。
第1育苗場班長の大友さんの家で、第2育苗場の事務所で、3月30日の播種祝いの会では育苗場で。
育苗場がある杉が袋地区の集会所にお呼ばれした事もありました。
この日は育苗場横の事務所でインターンの秋山君と3人でとんちゃんパーティー。
ペロッとなくなり・・・。
男3人、文字通り川の字で、いつものように事務所で寝袋に包まり、翌朝はまた腹が減っている・・・。
地元農家からいただいた採れたて小松菜、うまかった。