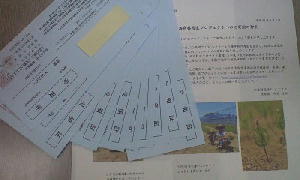インターンの秋山です。
先日、フィリピンのお土産を持って久しぶりに北釜耕人会の畑を訪ねました。
北釜耕人会は3夫婦6人で、主に内陸の第2育苗場でクロマツを育てています。
訪問の目的は作業日報を回収するためです。
作業日報にはクロマツの育苗について、いつどんな作業を何時間したかを記入してもらっています。
9月になったので、8月分のものを回収し、新しいものを届けてきました。
7月には畑には枝豆やとうもろこしなどがありましたが、先日訪ねたときにはそれらは収穫された後で、新たにブロッコリーを植え付けしてる最中でした!
男性がトラクターで耕転し肥料をまき、奥様方が苗を植えています。

写真ではわかりにくいと思いますが、奥のほうにクロマツの苗床も見えています。
東北森林管理局のHPに「海岸林復旧の考え方」が掲載されていました。 写真が多くわかりやすいです。 ぜひチェックしてみてください。 「海岸林復旧の考え方」
「海岸林再生プロジェクト」のホームページでも、役に立つわかりやすい公開情報が入ったら
プロジェクト概要「リンク集」にも掲載します。
企業・労組・各種団体などのご担当の皆様にも役に立つと思います。
ぜひご覧ください。
先日「効率的なコンテナ苗生産のための技術検討会」に参加しました。
会場は茨城県日立市の森林総合研究所材木育種センターで、席に座りきらないほど多くの人が来ていました。
北海道から九州まで、育苗農家や企業担当者、都道府県職員、林野庁関係者など多方面から参加していました。

コンテナ苗とは?
コンテナは写真のような小さいポットがたくさんくっついてるものです。

コンテナ苗は露地播きの苗と比べて、成長が早いことや、植栽後も活着率が良く成長が早いので、植付本数を少なくすることができるなどのメリットがあると言われています。
しかし、生産には資材費がかかり、散水や薬剤の散布などきめ細やかな管理が必要で、技術的にも難しいとも言われています。
海岸林再生プロジェクトもコンテナ苗生産の準備を進めていますが、1年で植付できる大きさに成長することから、海岸への植栽時期をにらみながら植付本数や時期を検討中です。
検討会にはLIECO社というオーストリアの林業苗木会社の社長が特別講師として来日し、貴重な講演を聞くことができました。
他にも、コンテナ苗生産技術の確立に長年取り組んできた方々のお話を育苗初心者である私たちは耳をでっかくして聞いていました。
他の参加者からも「これは来て良かったな!」という声が聞こえてたとおり、良い勉強になりました。
宮崎県の海岸林(一ツ葉海岸)
ボランティアの木邑です。
家族で宮崎に行きました。
ホテルの窓から立派な黒松の海岸林が一望!!
ふと、このブログのことが頭をよぎりました。(^-^)
ちょうど沖縄に史上最大級の台風が来ていて、
宮崎もその暴風圏内に入り、晴れ間も見えながら、
突然大雨が降ったり、すごい風がふいたりな天気でした。
窓から見える海は大荒れ。
風が直撃するところは飛ばされそうなくらいでしたが、
黒松の林のそばは風もほとんどなく、防風林なんだなぁと実感しました。
前回滞在したときには林の中を散策したのですが、今回は林の中に入れませんでした。
林の中で実施するホテルのアクティビティも、
「松の枝が落ちてきたりするので中止しているんですよ」とのこと。
一ツ葉海岸と言って白砂青松百選のところでした。(帰ってから調べました…)
海岸に沿って12kmほど、幅は最大1kmで約830haの広さがあり、
200年ほど前に、地域住民が飛砂や塩害を防ぐために植林した海岸林だそうです。
林はよく手入れされていて明るく、リゾート地としての活用も多々。
前回には気づかなかった視点で海岸林を見ることができておもしろかったです。
また天気のよい日に、この林を歩きたいなぁと思いました。
宮城県内からのご寄附
「海岸林キックオフ植樹」in七ヶ浜町のその後
7月3日に秋山君がレポートした宮城県主催「海岸林キックオフ植樹」in七ヶ浜町のその後を8月18日に見てきました。

仙台火力発電所や新日本石油施設が見えます。
遠くから見ると海岸林は残っているように見えますが、実際には「疎林化」しています。
津波でやられてしまい、虫食いのようになっています。
一面被害を受けたような場所だけでなく、被害程度は高くないものの、
「疎を密にする」再生方法を求められる場所も数多くあります。


地山は草が茂ります。

こちらは全く下草が生えていません。
「地山をえぐられ凹が出来ため、山砂を入れて植栽をしたために今年だけは下草が生えない」
そうです。そのような何らかの理由でえぐられ、凹になった場所はよく見かけます。
この様な「壊滅的打撃」に至らない海岸林は全被害面積3,660haのうちの約70%あります。
*被害程度75%未満
ここは国の直轄地域でないため、県が再生事業を進める地域です。
宮城県南部は壊滅的打撃を受けたため国が直轄します。
国交省による防潮堤→林野庁による海岸林の基盤となる盛土工事、その後に植栽が開始されます。
キックオフイベントは別として、本格化するのは平成26年の春頃でしょうか。
日本海側の小さな海岸林にて
プロジェクト担当の吉田です。
京都出張の帰路、先日ご紹介した天橋立のマツ林を見た後も、小浜市を経て帰る間、
外海に面した場所で海岸林を見つけては小休止しました。
(そんなことをやっているから帰るのが遅くなる)
幅は狭いが、十分な高さがあり、防風林として相当地域の役に立っているように見えた。

飛砂防止重視か。林帯幅を確保できないため、下枝が十分張るように育成され、
低木としてトベラなどが植えられているのに加え、低い防砂ネットもあり。

樹高も低くまだ若い海岸林ですね。でも20年以上の樹齢では。
大きな砂丘を盛土にする典型的な海岸林。延々続く海岸林の背後には、集落もずっと続く。


「白砂青松100選」などの有名所でない小さな海岸林にも生活との密着感があると感じています。
盛土がある場所のマツの根
プロジェクト担当の吉田です。
夏休みに、森林組合の佐々木さんにご案内いただいて、牡鹿半島に行った時、
永年精一杯の機能を果たし生き残った海岸林と、立派な松の根を見ることができました。
「クロマツ根っこショールーム」さながらでした。
息子達は綺麗な海で嬉々とし、やはりオヤジ達はマツを見てしまいました。
ここは牡鹿半島ですがリアス式海岸ではなく、台風や高波の他、西に向いた海のため、
春の奥羽山脈からの強風が海を越える事による塩害を受けやすい立地かもしれません。
海岸林背後には壊滅した小さな集落があります。全長1kmぐらいの小規模な海岸林とは言え、樹齢は120年。大事に守られてきた事が伺い知れます。
海水面から最大3mの盛土の上にクロマツ林があり、倒れたマツは小川に沿って引いてきた波で盛土ごと海側に引き倒されたのだと思います。周囲には寛政年間等の墓石が散乱しています。
しかし、たった1~2mでも海岸林での盛土の効果を名取市北釜地区と同様に目の当たりにしました。
盛土を失っても、上部を伐採されても立っているマツの根もありました。



下の写真は、昨年東松島市野蒜で見た、盛土が無く、地下水位の高い場所で倒れた樹齢150年近いマツの根です。
マツらしい直根がありません。

ところで、いよいよ名取の治山工事、すなわち盛土工の入札を迎えました。
3m程度の盛土の造成が始まろうとしています。そして、津波で倒されてもなお飛砂を防いできたクロマツは撤去されます。
それでもまだ何かに利用され人の役に立つように思えます。