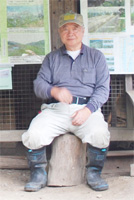北釜耕人会の生い立ち その②
(昨日のその①の続きです)
我々北釜耕人会は、3夫婦6人で構成しています。
毎日何もすることがなく、ごろごろしていた時、
「このままでは人間としてダメになるのでは」と思い、
避難所近くを散歩して場所を探したり、近くの友人を頼り、
農地を貸してくれるよう場所を見せてもらいました。
(海岸より内陸に約10km。今、この農地は、第2育苗場でもある)
初めて見せてもらった時は「ここが畑か」と疑うような荒れ地で、
草が1mも生い茂っていました。
4月16日にその荒れ地に初めて手を入れ、5月には小松菜の種蒔きをしました。
震災前の海岸林横の農地は砂質土壌で、震災後に借りた農地の土と性質が全く変わり、発芽するまで皆はとても不安でした。
そして6月の初収穫。園芸課長に「苦難を乗り越えよく頑張った」との色紙をもらい、皆で涙を流しました。
その後、生協さんとのタイアップで仙台白菜の再生事業などの取り組みもしています。また、露地野菜中心では年間を通じて出荷できないため、国の補助事業などを利用しながらパイプハウスを20棟の組み立てを行いました。
来春からはハウスを利用した周年栽培で、安全で安心して食べられる野菜を
1年を通じて安定的に生産してゆくので皆さんにも利用していただきたいと思います。
北釜耕人会の生い立ち その①
※10月24日のオイスカ国際フォーラムでの発表をもとにお伝えします。
北釜耕人会 常務 高梨仁 (名取市海岸林再生の会 幹事)
名取市下増田北釜地区は、仙台空港の東、太平洋と貞山運河に
挟まれた、約800mの間に107戸、400人ぐらい住んでいました。
震災により住宅、車、農機具を失い、そして54人の犠牲者を出してしまいました。
集落の北に従前より耕していた農地25haと、30年ほど前に仙台空港拡張に伴い代替用地として国有林の払い下げを受けて開発した農地25ha、あわせて50haの農地に約1,000棟のパイプハウス(ビニールハウス)を建て、青梗菜(チンゲンサイ)をはじめとする小松菜・みず菜など軟弱野菜を仙台市場に年間を通して出荷していました。
青梗菜で仙台市場年間流通量の80%に達する産地が、一瞬にして瓦礫の山になってしまいました。林帯幅300mのマツ林も失い、農地から太平洋が見える状態です。
震災では、消防団として避難誘導に務めたため逃げ遅れ、波が来る一瞬前に、登ること自体考えられない高さの自治会館の屋根の上に登り、水が引かないため雪の中、2日間耐えました。
仙台空港で土産物の萩の月や笹かまぼこを分けてもらい、
3月13日に市の指定避難所の名取二中の体育館に移り、
5月31日までの2ヵ月半、雑魚寝状態でした。
その中、5月24日にオイスカと出会い、
海岸林再生に我々も協力すると、はっきり伝えました。
かしわ餅のカシワ~北海道・石狩海岸の天然カシワ林~
担当の吉田です。
今年は地方出張で22県に赴きましたが、その際には、極力時間を作り、
論文などをにわか勉強をして、ご当地海岸林を視察しています。
今回は北海道森林管理局の素敵な方に、
とてもいい資料をいただき、空路は熟読しました。
地吹雪の中、オイスカ北海道支部の役員さんと二人、石狩川河口に。
そこから小樽市東部まで全長20km。
森の平均の幅は500~600m、広いところでは800m。
総面積653haの天然カシワの海岸林があります。
こんなに大きなカシワ林は見たことありません。
港の近くですから、船荷を積んだ大きなトレーラーがカシワ林の
脇を通りますが、それすら小さく見えました。
カシワの木に関する面白い話は、こちらでも触れましたが、イメージするに「かしわ餅」「子どもの日」⇒「縁起物」「葉っぱが落ちない」⇒「代が途切れない」、「子孫繁栄」
カシワは冬芽を守るために、冬に落葉しないそうです。
浜に出ると、強風で砂が頬を叩き付け、さらには砂丘を越え、葉をつけたカシワ林に及び、砂は静止します。落葉樹では潮に強いとしても、防砂防風効果は半減するでしょう。
カシワの実は、厳しい冬を迎える動物にとっても貴重な食源でもあり、古くから人間の生活や産業に不可欠だったことでしょう。
「札幌までは少し離れているけど、大きな意味では札幌まで守って
るのかもしれないね。住んでいても知らなかったよー」
オイスカの役員さんの言葉とともに、まさに保安林という印象が私には残りました。
本部・広報室の林です。
しつこく、しつこく、さらにしつこく言い続けると、ちゃんと願いがかなうんだなぁ~と思ったお話です。
12月7日、名取の現場でインターンをしていた秋山君のトークイベントが行われました。

地元の皆さんにとてもかわいがってもらい、貴重な体験ができたと語ってくれました。
いえ、私の願いをかなえてくれたのは、キナ君ではなく・・・。
このイベントに来てくれたANAすかの皆さんです!
10月に行われた仙台空港空の日のイベント用につくった「ANAすかオリジナル松ぼっくり」、
記念にひとつ欲しかったのですが、当日来場者が多く、全部配ってしまったのだそうで・・・。
残念だなぁ~、欲しかったなぁ~としつこくしつこく言い続けていたら、
2ヵ月が過ぎたこの日、どこから出てきたか、とうとう私の手元にやってきたのです
見てください!!

クリスマスプレゼントのようでうれしいです!
もう一度おさらいすると、この塗料は、ANAの飛行機に使われているもの。
そしてリボンは飛行機のカーペットを裂いたもの。
完全ANAオリジナル松ぼっくりなのです。
きれいでしょ~。

「事務所に飾ってください」といわれたのに、自分のパソコンの上に飾らせていただいています・・・。
ANAすかの皆さん、ありがとうございます!!
支援者お手製の写真パネル展示 in川崎市
活動報告会や、現場での視察会に、いつも足を運んでいただいている
川崎の井上さんからメールをいただきましたのでご紹介します。
******
これほどのご尽力、関係の皆様に深く御礼を申し上げます。
11月14日(土)の川崎市民アカデミーフェスタでの、
「海岸林再生プロジェクト」写真パネル展示と募金に関して報告をいたします。
当日、私は娘の結婚式のため、準備のみで説明に加われず、仲間にお任せしていました。
あいにくの雨で、フェスタ全体の入りは今一だったようですが、
それでも我々の展示には延べ70余名の方が来場いただきました。
後日、「海岸林のパネルが一番見られていたよ」。太田猛彦先生(東京大学名誉教授・
林野庁「通称:海岸林再生検討会」座長)から声をかけられました。
先生自ら、見学者に説明をして下さったようです。うれしい限りです。
今後も他のイベントに、私の作った「海岸林再生プロジェクト支援」のパネルが
展示されることになりました。
川崎市民アカデミー、早野聖地公園里山ボランティア 井上文雄
富山県・入善(にゅうぜん)町海岸防災林造成事業
12月4日にオイスカ支部役員会でのプレゼンを行った翌日、
朝からホタルイカの沖漬けなど食べた後に、
1994年の新人駆け出しのころ、イロハを教わった上司でもある
支部事務局の北森さんと、富山市から北東1時間の入善町に行きました。
だいぶ以前に林野庁東北局の幹部の方から教わった、
水田に対する潮害防止の防潮林再造成事業(昭和60年~)でした。
住民アンケートでも7割を超える人が事業の成果を認めているようです。
最初に見たのは平成23年の植栽地でした。目前には海。砂浜はほぼありません。厳しい海岸浸食を食い止めるための離岸堤があります。
もとはマツ林だったのが、昭和30年頃に海まで水田に造成。カメムシ被害に加え、潮風・高波などの塩害により「赤米」となり、収量激減のため、昭和60年より平均林帯幅30mの海岸林造成を開始しました。
海抜0mのような場所。黒部川河口も近く、近くには湧水もあり、地下水位も高いのでしょう。林道残土を使い1mの盛土をしています。山砂や赤土、こぶし大の礫も。
ここは、「寄り回り波」というこの地特有の高波が、冬の時期に港や集落、水田を襲います。2008年には越波して大きな被害を出しました。
従って、盛土周りも滞水しないよう排水溝が整備されています。
事業開始から25年で樹高は15mに達する場所もありました。
まさに事業進行中で、近い将来の海岸林の姿の見聞と、
住民と行政が最初からタッグを組む必要を改めて感じた意味で貴重な視察となりました。
12.7 地震その時
12月7日、トークイベントのため秋山君と一緒に 日比谷に向かう地下鉄の中にいて、地震には気付きませんでした。 霞が関駅から地上に上がり、名取事務所統括の佐々木さんに 別件で何度か電話しても、「只今、大変込み合っています」の繰り返し。 おかしい!と思い、二人の班長や海沿いにいるだろう人の 何人かに電話しても誰もつながらない。 同僚がネットで地震を確認しました。 しばらくあと、地主さんに繋がり、 「市民会館近く(海から7km内陸)まで、放送指示に従い一応逃げた」 「渋滞がひどくて車が全く動かない」など、 およその様子を聞くことができて少し安心しました。 その後、自治会長でもある大友班長は笑われながらも 下増田小学校まできっちり逃げたことや、 行政や消防署の避難誘導放送があったこと、 幹線道路は渋滞があるが、水田の農道は空いていたこと、 信号は一応機能していたことを確認しました。 統括の佐々木さんは、石巻に行った帰路高速上で遭遇し、 ハンドルを取られそうになるほどの揺れを感じ、 路肩に車を寄せたと聞きました。 来年からは現場に来る人がさらに増えます。 海岸林から最短距離の避難先は美田園駅か、仙台空港ビルなど 幾つかありますが、緊急体制についても、地元の情報を整理し、 不測の事態に的確な指示ができるようにと思っています。
「ご寄附のお願い」チラシ設置先 続伸中②
11月15日にホームページの「インフォメーション」でお知らせした、 新しいチラシの設置のお申し出をたくさんいただいています。 川崎の里山ボランティアの方により、整備している里山の掲示板に 設置いただいたことを機に、全国への呼びかけをやってみようと思いました。 オイスカの会員や、全国の支部、そして海岸林支援者の ご協力のおかげで、特に富山、広島、愛媛、香川、愛知、 宮城、東京などで設置先が続々増え、1ヵ月半で15県に150ヵ所。 例えば、 企業の総合受付 旅館のロビー お寿司屋さん お寺の本堂入口 ガソリンスタンド 自動車販売会社の全店舗の折衝テーブル 県民文化会館、教育文化会館、文化ホール 県立森林公園・自然公園・植物公園のロビー 県議会議員の事務所 官公庁出先機関ロビー 自然環境保全団体の会報に封入 本部膝元の杉並区、初めての設置先は、 会員さん行きつけの整体院のロビー。 皆さん、我々の知らないところで、それぞれがプロジェクトの事も 説明をしてくださってるのだろうと想像します。 設置先に電話をしながら、まだ見ぬ方のお心遣いにありがたく思い、 そして力を得た気持ちになります。 心からお礼を申し上げます。
吉田の名取出張レポート その8 防風ネット修繕
 11月26日厚く垂れ込める寒空の下、防風ネット修繕のため「名取市海岸林再生の会」より男女16名が集まった。
11月26日厚く垂れ込める寒空の下、防風ネット修繕のため「名取市海岸林再生の会」より男女16名が集まった。
佐々木さんによる作業説明と安全管理指導の後、軽く体操をしてさっさと始まった。
班長以下数人は作業の趣旨を当に理解しており、指示は短い。
他の人も勝手知ったる仕事なのだろう、さっと散って行った。
そもそもこの防風ネットは、前田建設工業㈱のご配慮で、単管パイプ1,400本・ネットの他にも、事務所・ビニールハウスなど資機材一切の提供頂いたもの。3月には社員さん30余名によって1泊2日で据え付け工事を行った。積雪の中、指折り思い出に残る、珍しい作業だった。
 それから8ヵ月。
それから8ヵ月。
春の風速30m超の蔵王おろしに備え、先手を打って補強修繕を行った。
すでに風向きが西風に変わりつつある。
午後から雨が降り始めたが、大勢が集中して作業するので作業は本当にキリの良いところで終わった。
お見事。
作業と同時に取材対応を2本。
TBS 日曜の夜21:54の「風の言葉」は1月、オレンジページは2月2日にお目見えの予定。
早朝、震度4の揺れで資材がきしむ音で飛び起き、あっさり二度寝して、キジの鳴き声で目を覚ましました。
スーパーハウスの我が事務所は、カラスが屋根の上を歩く音がよーく聞こえます。夜は特に。
朝、まず第一育苗場に向かうと、地主さんの家との境や、防風ネット沿いに動物の足跡が・・・。今までは気付かなかったけど。
タヌキではないかと思いました。巡回道路なんでしょう。
出会うのはなかなか難しいでしょうね。
これまでも、育苗場の方に車のライトを照らしてみたりしましたが、なかなかヒットしません。
事務所のビデオを据え付けてみようとも思いましたがホームビデオじゃ、漆黒の被災地では無理ですね。