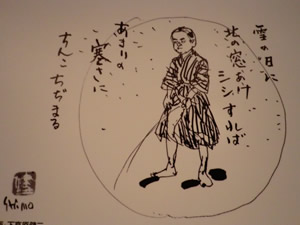震災から4年半となった9.11、明け方まで大雨が降り、
宮城北部の大崎市、大和町、栗原市、富谷町などを中心に大変な一日となった。
共同通信社が9.11をめがけて当プロジェクトを含む被災地復興について
記事を全国に配信したが、購入するメディアは少なく、不発になったかもしれない。
朝5時半過ぎ、テレビをつけると、東北本線や仙台空港アクセス線などは不通が決まった。
東京から寄附者が贈呈式と視察を兼ねてくる予定だったが、延期にしていただいた。
しかし、東北電力労組はすでに半年ほど前にはこの日に来ると決め、
参加する方は休暇を取り、覚悟を決めて前日から名取の隣の岩沼市入り。
お互い余程のことがない限りやるつもり。
昨年は、二度と来たくなくなるぐらいの、1年で最も暑かった日に草と格闘。
前日は1時間もいただいて、プロジェクト活動報告をさせていただいた。
この配慮はありがたい。即現場に突入できる。
雨上がりこそ「溝切り」です。朝からこれonlyになりました。
平成27年度植栽地のうち、最も水捌けの悪い1ha(約5,200本分)を、
根腐れの恐れから「救出」していただいた。
今年の約10haの植栽地の「溝切り」は、すべて終えたことになる。
ここまでやってダメなら、キッパリ諦めます。
11月まで、一応、点検、補修は続けようと思っていますが。
この1haは、今までで一番悪い場所。
4月、8月、9月の3回、合計100人強×3時間ぐらいの労力をかけた。
自然の降雨の力も借りながら、1番手、2番手、3番手と、徐々に深いものに仕上げ、
随時新設もしてもらった。
水溜りのない場所でも、足の感覚で「水脈」を当てます。
この1haは、表面に水がなくても、地中で滞水しています。
柔らかさがチガイマス。試しに一鍬掘ると、水が染み出てきます。
そこを水源地として、「松と松の間を通して」、最寄りの排水溝まで最短距離の溝を作ります。
放っておけば、半分以上枯れるのは、隣の他団体の現場を見ればわかります。
しっかり作れば、昨年の植栽地と同様、翌年その場所はやる必要がなくなる。
ザックリ言えば、植栽したその年しっかり頑張ればいい。
9.11。
やっぱりこの日は、東北に住む方が頑張ってくれました。
頼りにしています。ぜひ個人参加もしてくださいね。
ホームページが新しくなりました
海岸林担当 鈴木です。
海岸林再生プロジェクトのホームページを改修していますと以前、ブログにてお伝えしていました。
時間がかかってしまいましたが、やっと完成しました!(一部ですが・・・)
完成したのは、【個人での支援】【法人での支援】の2つ
★変更ポイントその1★ バナー表示の変更
これまで、バナーのメニュー表示の中で【隊員募集】【隊員紹介】となっていましたが、
個人で支援できることは何だろう? 法人として支援できることは何だろう?
というギモンを分かりやすく解決するために、【個人でのご支援】【法人でのご支援】に変更しました。
ご支援の内容が分かりやすくなったかと思います。
★変更ポイントその2★ 写真を多く掲載
特に、ボランティア活動レポートでは、多くの写真を掲載し、
写真を見ただけで活動内容がわかるよう工夫しました。
他のページでもなるべく多くの写真を掲載するようにレイアウトしました。
ボランティアにいらしてくださった方は、どこかにお顔が掲載されているかもしれませんよ!
★変更ポイントその3★ 隠れていると開けてみたくなる!
ボランティア活動レポートでは、「アコーディオン式」と言われる方式を採用しました。
通常は閉じているのですが、使う時に蛇腹を開くアコーディオンのように、
最新のレポートのみ写真を表示し、以前のものは通常は閉じられています。
▼をクリックして開けてみてくださいね
やっとみなさんに公開できる運びとなり、やれやれの感です。
制作を担当してくださった㈱ディ・エフ・エフのみなさん、
オイスカの広報アドバイザーをしてくださっているコーズ・アクションの菅さんに感謝申し上げます。
トップページ、プロジェクト概要などのページは9月末ごろを目処に引き続き改修を進めていきます。
こちらもお楽しみに!!
こんにちは
海岸林担当 鈴木です。
プロジェクトの所在地は仙台空港のすぐ近く、飛行機誘導等の近くですと度々伝えていますし、クロマツと飛行機の写真がブログに掲載されることもしばしばです。
今回、ボランティアに参加してみて、本当に飛行機が間近に見られるのに驚き、うわぁ!こんなに近くで見られてラッキー!と思えるほどの近さです。

写真ではどうしても飛行機が小さくなってしまいますが、実際は本当に大きくて迫力があります。
ソラ男さんたちがわざわざ写真を撮りに植栽地の近くまで来るくらいですから。
飛行機が間近に見られてラッキーと思ったのは最初の数機・・・次々と降り立つ飛行機を見ては、「(乗客は)きっと、この雨の中、あの人たちは何をしているんだろう?」と思っているのだろうなぁと飛行機を見上げていました。
雨で濡れて作業をしながら、’機内で「仙台空港に着陸する寸前の両側に見えますのは、津波により消失した松林を再生させようと、全国からのご寄附により実施されている『海岸林再生プロジェクト10ケ年計画』の植栽地です。ボランティアの方々が作業している姿が見られることがあります」’などとアナウンスされていたら、雨の中の作業も報われるなぁと一人考えていました。
今度は、飛行機に向かって大きく手を振ってみようっと!!
天候にあった身なりは重要
こんにちは
海岸林担当 鈴木です。
8月29日のボランティアの日は早朝から降雨。
ボランティア作業が始まる9時、どんよりとした雲が立ち込め、まったく雨があがる様子はなく、みなさんカッパを着ての作業開始となりました。
最初は育苗場での草取り作業。
草取り作業に気乗りのしないわが子たちが、ふと見ると体が隠れるくらいの一抱えの草を運んでいました。
よしよし、張り切って作業をしている姿を見て、去年8月にボランティアに来た時に比べて、1年で成長するものだなぁと満足していました。
育苗場の草取りがあっという間に終わり、植栽地に移動し、ハンパなく成長した雑草のツボ刈りをしました。
容赦なく雨が降り続きます。
長靴ではなく防水の運動靴で作業していた子ども達の靴の中は濡れ、靴下も濡れ、ズボンの裾も袖口も濡れしていくうちに、小学1年の下の子は「もうヤル気0.00%」と鎌を放り出してふらふらと歩きまわり、小学4年の上の子は、ツボ狩り作業中だというのに溝切り作業をやりだしてしまいました。
成長を喜んだのも束の間、やはり1年で成長を期待したのは甘かったのか…確かに靴の中が濡れるのは気持ちが悪いのはわかります。
次回は、重いからと面倒くさがらず長靴をもってこようと思います。
作業内容や天候に合った服装というのは本当に重要です!
ボランティアのみなさんは雨を予想してか、ほとんどの方が長靴をはいていらっしゃいました。
今回のボランティアさんの中には、遠くは山口県からいらしてくださった方もいて、キャリーバッグを転がして遠路はるばる参加してくださる方もいます。その中に長靴をしのばせて。
カッパや長靴、作業着、着替え、ゴム付軍手など、重い荷物を持って遠方から新幹線などに乗っていらしてくださるみなさんに、改めて感謝です。
震災から4年半の9.11。宮城県は大雨特別警報。
「そちらは無事か」とメールなどいただきました。ご心配頂きありがとうございます。
今日9.11は東北電力労働組合21名の皆さんと、8時半から「溝切り」などの作業。
最も水捌けの悪い場所約1haの溝切りに専念。そこの約5,200本を守るために。いい仕事になりました。
植栽地のクロマツは、根腐れの恐れはありますが、今のところ無事です。
育苗場は、若干高い場所の上、2011年に50cm盛土された場所を選びましたので無事です。
再生の会の皆さんの自分の農地なども。
市内は堤防決壊、家屋浸水などはないと市の農林水産課の方は言っていました。
しかし、海岸林背後は、もともと巨大ポンプがいくつもあっても非常に排水が悪い低地。
そのうえ見渡す限り1mちかく地盤沈下。育苗場周辺にも海抜ゼロmの場所がたくさんあります。
海岸林背後では、ようやく小松菜の作付が始まったビニールハウスが浸水。
小松菜の値段はいつもの3倍。ある農業法人は20棟が浸水。ポンプ2台で排水しているとのこと。
400万円ぐらいの被害になるのでは。
翌日9.12は青空。今日のうちに引けば大丈夫かもしれないが。
9月19日のボランティア急募!!
9月19日(土)のボランティアの日、急募しています。
「嵐」のコンサートで宮城隣県まで宿が取れず、首都圏の人は望めません。
宮城県内の人を頼りにしようと、口コミの手を打ちました。
再生の会第2育苗場の櫻井班長のご自宅に行ったら、
「さっき、東北放送(ラジオ)でも流れてたぞー。吉田君が頼んだのかー?」
「いや違います。たぶん名取市役所が手を回してくれたか、東北放送が自分で情報を取ったか。
市のHPにも出してくださったし」
空港近くの航空機関連企業、毎月ご寄附いただいているパシフィック㈱の鈴木社長や、
トヨタ部品宮城共販の社員さん、名取市役所にお勤めの方などからお申し込みが続いています。
福岡や愛知の方も来ます。
現場での仕事は山ほどあります。

去年植えた木、今年植えた木、来年再来年植える苗木のお世話をしていただきます。
ガンガン生えてくる雑草、つる草、ニセアカシアが待っています。予定では宮城中央森林組合のプロも、プロの仕事をしに来ますので、仕事っぷりを見てもらえるかもしれません。
宮城の海岸林の歴史を研究している東北学院大学の菊池慶子教授も
今年2度目のご参加。講義もしてもらえるかも。
現在70名ほどのお申し込みです。120名まではお受けできます。
「警報」が出ない限り雨天決行です。
雨が降った時こそやる仕事「溝切り」もあります。
炎天下であっても実施しています。

宮城県内のみなさん、ぜひ名取の海岸林再生に力を貸してください。
オイスカ愛媛県支部・広島県支部での報告を終えた後、
9月9日、組合員157万人、日本最大の労働組合「UAゼンセン」の定期大会
2,000人の来場者に写真パネルで報告を行いました。
視察も含めればこの4年で、360人は来ていただいています。
傘下組合の組織的単独支援も増え、その人たちを含めると600人を越えます。ですから、さすがに多くの労組幹部の方が声をかけてくれます。仙台駅の写真展など、接客は本当にいろいろな事を感じ、学べます。
支援に関しては、今年も逢見会長のご挨拶と、議事で紹介いただいています。組合誌と、組合の新聞でもたびたび取り上げられています。これから更にUAゼンセンの中でプロジェクトは浸透してゆくことと思います。以前、本部職員みんなで我々のDVDを見ていただいたそうです。ホームページにもある10分の映像。たくさんの方が拍手してくれたと聞きました。一人でも多くの方から少しづつ。いつも思います。
会長は永年オイスカの役員である上、7月には2度目の来訪。
現場で8時間、トップ自ら8時間作業していただきました。
前日、広島市内を歩いていたら街角でバッタリ。
思わぬ所で立ち話。顔を覚えていただいており嬉しかった。
10月の「連合」事務局長選挙への立候補をご挨拶の中でされておりました。
更なるご活躍と、いつか、再度の名取来訪を願いました。
オイスカは全国に14支部。
9月7日、愛媛県支部の幹事会で活動報告をしました。
8月以降、香川、掛川(静岡)で活動報告をしましたが、
行けばいくほど結果が出る。
永年オイスカを支援いただいている会員が意気に感じてくれます。
一度で済まなくなり、香川は「年内にもう一度報告会を」と言われています。
愛媛に仕事で来たのは初めて。
大学2年の時のインカレで1992年に来て以来(体育会ソフトテニス部でした)。団体も個人も早々に負けたので、電車と自転車で四国を1周しました。私にとって愛媛とは「坂の上の雲」。高校生以来何度読んだことか。
毎年寄附をいただく企業のシムラ産業㈱や、チラシを設置頂いている栄養寺の住職さん、松山市議会議員の方などとゆっくり説明できました。
何処に行っても一様に驚愕されます。報告会前と後とでは参加者の表情が全く違います。その後の宴会も本当に盛り上がります。年配の会員さんたちから、「オイスカの会員であることをこれほど誇りに思ったことはない」とお褒めの言葉をいただき、「オイスカ愛媛の集い」での再度の活動報告をと会長から言われました。
今日は松山から広島へ約2時間半の船旅。
フェリーの上でブログ書いています。
広島は寄附者が多い。
各単組組合員が300人も名取に来ているUAゼンセンの定期大会(2,000人)が
広島で開催されることもあり、オイスカ広島県支部幹部との面会も兼ねて
愛媛に続き遠征しています。
名取に来てくれた方とたくさん会えるでしょう。
各組合で寄付チラシを配ってほしいとお願いするつもりです。
帰りは空路仙台空港へ。
空から現場を見るのは、2011年4月21日以来。
飛行機が海側から入ってくれるといいなあ。
なんと手際のいいことでしょう!
こんにちは
海岸林担当 鈴木です。
8月29日のボランティアの日、雨に濡れながらの一日の作業がやーーーーっと終わり、やれやれと解放された気分で車に同乗させていただき事務所に戻ってきました。
私が乗せていただいた車は13台のうちの最後尾でした。
車から降り、荷物を下ろし、カッパを脱ぎ、びしょ濡れになった子どもの洋服を脱がせしているうちに・・・・ 気が付くと水道の周りで泥になった鍬や鎌を洗う作業が手際よく進んでいました。
「ボランティアに3回以上いらしてくださっているオイスカ腕章をつけたボランティアさんは中隊長の役割を担っていただいている」と吉田がよく言う意味が、スーッと理解できました。
今回のボランティアの日の参加者は、初参加が8割ほどだったにも関わらず、ボランティア経験者が手際よく片付け作業を進め、その作業をみなが進んで手伝っているようでした。
私が鎌を洗う作業を手伝っているうちに、倉庫では、水分を拭き取りさび止めをスプレーし、刃物部分を柄に留めてある釘が抜け落ちそうになっていないか確認し、10本ずつきれいに並べる作業が終わっていました。


そして、空港まで送ってもらう時にプロジェクトの軽トラに乗ると、鍬や鎌を積んだ荷台、座席までもがきれいに泥が拭き取られ、きれいな状態になっていました。
何の指示があるわけではないのに、ごく当たり前の事のように一連の作業のように片付けまで終了する・・・ありがたいことだなぁと参加してみて実感しました。
主体的に動いてくださった今回ご参加のボランティアのみなさんのみならず、これまでご参加くださったみなさん、あらためて本当にありがとうございます。
こんにちは
久しぶりのブログ寄稿になります。鈴木です。
昨年8月のボランティアの日に初めて植栽地を訪れてから1年が経過し、2度目の訪問でした。
今回はプロジェクト担当の吉田さんから、ボランティアのみなさんの動きに合わせる必要はなく、自由に植栽地を見てまわって欲しいと言われていました。
午前中はボランティアのみなさんと共に草刈り作業に汗を流し、午後は昨年度の植栽地を歩いて1周してこようと計画していました。
植栽地の地図を持ち、植栽地を訪れる動物たちが載っている海岸林レポート(全国の支援者向けに9月中旬発送予定のダイレクトメール封入用。もうしばらくするとお手元に届くと思います)などを探検バッグ(小学生が社会化見学、理科の観察など野外での活動に使用するもの)入れて準備していました。
午前中は雨でも、午後はきっと雨があがるだろうと期待していましたが、午後もあいにくの雨。
私は晴れ女のはずなのですが、昨晩の楽天の試合で晴れエネルギーを使い果たしてしまったようです。
靴がびしょぬれの子どもを連れて植栽地を1周(約3.5キロ)を歩くのは到底無理。
さらに、午後は子ども達の大好きな溝きり作業。泥んこ遊びの延長のようで楽しいようです。高低差をつけてクロマツの根元から水路を作り、水が見事流れていくのは大人の私もハマリます。

雨が数日続いているおかげで、あっちにもこっちにも出来ている水溜りから水路を作り水を流して、流れ出る水を見ながら悦に入っているうちに1時間以上経過し、結局昨年度の植栽地を1周するという計画が頓挫してしまいました。
それはそれで楽しかったのですが、昨年度の植栽地を1周、時間をかけて歩いてみたかったなぁ・・・これは次回植栽地を訪れたときの楽しみにとっておくことにします。
もしかしたらキツネやタヌキに出会えるかなぁ???