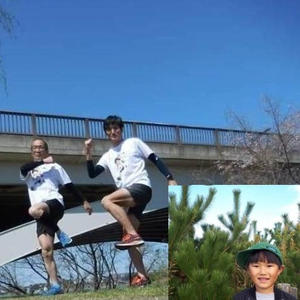先日、大阪マラソンのブログでご紹介した齊木さんからブログが届きました!
原文のままで掲載させていただきます。(写真は勝手に選ばせてもらいました)
————————————————————————————————————————————————————————–
数え年で42歳は男性の大厄年。
そんな2015年は満身創痍で酸鼻を極めた年でした。
「因果応報…今迄の悪行を悔い改め、今後は徳を積んでいかねば。」
と唐突に思い立ち
「何かボランティアをして人の役に立とう。」
と安易に決めた結果が
私、齊木郁(サイキカオル)とオイスカ、名取市海岸林再生プロジェクトが出会うきっかけとなりました。
初めての名取は2017年。
労働組合UAゼンセンの一員としてボランティアに参加しました。
作業内容は植樹祭準備としての割り箸刺しでした。その第一印象は
「吉田さんってカッコイイ!!」おまけに「仙台の牛タンって美味しい」
という、どうしようもないものでした。
しかしこの年、11月のリピーター回を含めて計7回参加させていただいた事で、
こんなどうしようもない人間の意識が確実に変わっていきました。
「何故黒松が必要なのか?」
「何故この作業が大事なのか?」
「今後、松林はどのように成長させていくのか?」
徐々に理解を深め、いつの間にか、
ツルマメの生態や葛の除去方法等を自ら調べるようになっていました。
現在では歴史に残るような、この大プロジェクトに少しでも携われるという
喜びと誇りを持って参加させてもらっています。

そしてオイスカスタッフの方々の熱意に惹かれる。
プロジェクトに参加されている方々の温かさが心地よい。
いつしか、この場所が第二の故郷とも思えるようになっていました。
そんな大切な場所の為に今回、大阪マラソンのチャリティーランナーとして登録しました。
サブ3.5(フルマラソン3時間30分切り)という超個人的目標を胸に秘めつつ(笑)、
海岸林の為に誇りを持って走ります。皆様応援の程宜しくお願い致します。
チャリティランナーの応援よろしくお願いします!
こんにちは、浅野です。
更新が遅くなり、すみません…。
大阪マラソンのエントリーが11月17日に締め切りとなり、
今大会のオイスカのチャリティランナーは22名となりました。
オイスカの会員さんやボランティアリピーターさんが走ってくれます!
オイスカのスタッフからも4名がエントリーしています。
大阪マラソンのチャリティランナーは7万円の募金を集めて出走権が得られます。
(集められなかったら、自分のカードから引かれます…)
それに加えて今年は23,550円の参加費(一般ランナーと同額)も払わなければなりません。
集められた募金は、海岸林へのご寄附となります。
42.195㎞走る練習をしつつ、募金も集めなくてはいけない…という大忙しの
年末年始を迎えるランナーの方たちを一緒に応援してください!
このブログを見に来てくれている皆さんならきっとご存じのお2人をご紹介します!
1人目はこの方!!
小林省太さんです!!2017年にも走ってくれた小林さん。
今回のニックネーム(寄附サイトの名前)は【吉田俊通の分までガンバル小林省太】です!
はい、今回は吉田、走りません!!吉田の分まで小林さんが頑張ってくれます。
2人目はこの方!
右でも左でもなく、真ん中のこの方!齊木郁さんです!
オイスカのTシャツを着ていますが、オイスカのスタッフではありません。
UAゼンセン傘下のウェルシアユニオンの方で、海岸林のボランティアにもいつも来てくれています!
小林さんの応援はこちらから↓
https://osaka-marathon.en-jine.com/projects/oisca/rewards/445
齊木さんの応援はこちらから↓
https://osaka-marathon.en-jine.com/projects/oisca/rewards/431
ランナーを選んで応援される方はこちらから↓
https://osaka-marathon.en-jine.com/projects/oisca
募金は1口500円~何口でもOKです!募金の〆切は1月25日(火)までです。
みなさん、ぜひご支援よろしくお願いします!!
今年最後のボランティア
こんにちは、浅野です。
13日の土曜日に今年最後のボランティアの日を行いました!
約4か月ぶりのボランティアの日、久しぶりにボランティアの皆さんに会える♪とルンルンで名取へ。
11日の夜に名取に入り、12日は地元リピーターの皆さんと朝からモニタリング作業。
調査プロットが10か所残っていたので、さすがに今日中には終わらないかなぁ…と思っていたのですが、
さすがリピーターの皆さん。終わっちゃいました。笑
当日は快晴。作業は前日にプロットのモニタリング調査が終わったので、本数調整伐の試験地の全数調査と
クズの刈り取りと…これ。

皆さん、お尻を向けて何をしているかというと…

大槻さんのご厚意で芋ほりをさせてもらいました。(掘ったお芋はみんなで持って帰りました)
その後、二班に分かれて作業開始。
モニタリング班はこんな感じ。

だいぶ成長したマツですが、本数調整伐がしてあるので比較的通りやすかったみたいです。
無伐のエリアも先にノコギリ隊が道を作ってくれたので、去年までの調査よりはスムーズに終わりました。
一方、クズの刈り取り班は…


クズだけかと思いきや、ツルマメまで…。
午前中では終わらず、午後は全員でクズ退治に取り掛かりました!
おかげ様で、ほぼ100%取りきりました!!これで冬の間、マツが窮屈な思いをしなくて済みそうです。
ツルマメは完全にはじけた後なので、来年はツルマメの抜き取りも頑張らなくては…。
今年もコロナの影響でほとんど作業ができず…今年の受入れ人数は11月13日までで226人でした。
来年こそは普通にボランティアの受入れができることを祈ってます!
皆さん、来年も会えるのを楽しみにしてるので、懲りずに参加してくださいね~
マラソンランナーの皆さんへ
広報室の林です。
本日、17時に大阪マラソンのチャリティランナーの受付が終了しました。
エントリーしてくださった皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
ただ、今日の私のブログは、エントリー済みのランナーの皆さんに向けたものではなく、
名取市のサイクルスポーツセンターで行われるマラソン大会に参加する皆さんに向けたものです。
11月6日のボランティアの日、閖上のあたりで溝切りをしていると、
サイクリングロードで何やらイベントが行われていました。
よ~く見ると「みやぎ・名取シーサイドマラソン」と書かれています。
給水ステーションにいたスタッフさんに防風垣越しにお話を聞きました。
この日、参加していたのは1000人。
1周5キロのコースが設定され、フルマラソンだけではなく、ハーフのほか、
リレー形式での参加もあるのだそう。
仮装をして走っている人もいたりして、何だかとても楽しそう。
大音量で音楽も流れていて、午前中はずっとUSAが、午後になると
ロッキーのテーマの後は、星野源が繰り返し流れていました。
この1000人の皆さんに、海岸林のことを伝えたいなぁと思いました。
調べてみると、別の主催団体が12月4日に同じようにマラソン大会を開くとのこと。
皆さんが走っているコースの周りにあるクロマツは、大事なインフラなんですよ。
全国のボランティアさんが大事にお世話をしてくれて大きくなってきているんですよ。
そんなことが伝えられたらいいなぁと思っていたところ、
各地のマラソンに参加しているボランティアのSさんから、
「マラソン、申し込みました」との連絡が……。
Sさんに海岸林のことが伝わる仮装をして走ってもらおうかと考え中。
(Sさん、マラソン後のブログ、お待ちしています!)
サイクリングロードを走るランナーの皆さん!
クロマツにも少しだけ目を向けつつ、楽しんで走ってくださいね~~!
広報室の林です。
11月のボランティアはモニタリング調査が中心。
この季節、茂みに突入すると浅野も報告していた「バカ」の被害に遭います。
ウインドブレーカーのようなツルツルした素材にもひっついてくる彼らですが、
なんとも驚きの、ある素材には全くつかないことが分かりました。
まったくバカがついていないMさんの作業ズボン。
作業前のきれいな状態であるかのようにも見えますが、
ここ、見てください!
コーデュロイ素材ではないポケットの部分にバカを発見!
こんな内側にまで入り込んで引っ付いてくる奴らが、
表面には全くついていない!!
そこでいろいろな種類のひっつき系のもので試してみましたが、
本当につかないんです! 一瞬ついてもパンっと一回手で払えば
ポロっと落ちていくのです。気持ちいいぐらいに。
意外な発見でした。
秋の作業時は、コーデュロイ素材に限る!
余談ですが、私はコールテンという言い方のほうがなじみがあり、違いを調べたところ
「コーデュロイは若者の言い方、コールテンは年配者の言い方」と説明しているものが多く、
年配者の自覚を深めていたところ、「コールテンは日本で作られたもの」と
コーデュロイとの違いを解説しているものを発見しました!
しかも日本=遠州織物産地としていて、遠州人としては
年配者と言われようと、「コールテン」と呼ぼうと思い直しました。
名取市海岸林再生プロジェクト職員研修に参加して 四国支部 崔 榮晋

この度、10月22日~25日まで職員研修として「名取市海岸林再生プロジェクト」の現場に行ってきました。
2011.3.11.
仁川空港に降りて、バスで移動中でした。ハリウッド映画の予告編のような映像に自分の目を疑いながら釘付けになっていました。仙台空港の飛行機が津波で流れる映像でした。瞬間、日本にいる家族が心配で電話とメールを送ったが、電話もつながらないしメールの返事もありませんでした。これは仙台だけではなく日本全体が大変だと気づかされました。2泊3日間の長い日程を終えて香川に戻ってその深刻さに更に驚いた記憶が今も鮮明です。

今回が東北を訪ねるのは2回目。初めて訪ねたのは、2012年3月震災1年後でした。周りから集めた沢山の支援物資とうどんの炊き出しに行く予定でしたが、受け入れ先が見当たらず直に現地に行くことにしました。当時、長男が小3でしたので、大川小学校に案内された時には正直複雑な心境でした。仮設住宅の住民との会話では想像もしたことのないような話を聞かされました。それから10年、2回目の訪問はその信じがたい映像の現場である仙台空港に松山から飛行機で降り立ちました。夕方の遅い時間でしたので空からは何も見えませんでしたが、空港ターミナルの壁にある津波の高さの表示で、その威力が伝わってきました。

高速道路の横を通るとき、“ここが第2の堤防の役割をしてガレキと一緒に沢山の遺体がここで見つかりました”と吉田部長から説明がありました。ここに来る前に予習として「松がつなぐあした」(震災10年海岸林再生の記録、小林省太著)を読んできましたが、現場ではもっと凄いことが分かりました。
なぜ、海岸林は必要なのか。どうして、黒松でなければならないのか。倒れていない松の木は何の違いがあったのか。海岸林はここに住んでいる人にはどのような存在なのか。出来るだけ住民の立場から理解してみようと思いました。“生活の基盤である農業には欠かせないのが海岸林だよ。海岸林が幅200mもあれば、風や塩害、霧などの被害を受けずに野菜を育てられるのはもちろん、海岸林の後ろの何十㎞までもその恩恵は計り知れないものだよ!” 昔からここには当たり前に松林があり、時代によってさまざまな恩恵を受けつつもその役割の大切さに気付いてないのかもしれません。

「100ha、10年、10億円」
民間NGO団体のオイスカ。私自身オイスカに関わった時間が短いのですが、正直私でも震災直後に聞いたら信じることは難しかったと思います。結果的に今までのオイスカの海外での活動の経験やノウハウを林野庁や行政も認め、地元住民たちにも認められたことは総合的なマスタープランとぶれない推進力と中心人物が居たからではないかと思います。
名取市海岸林再生プロジェクトに参加して、一番「感動」したのは人の心の繋がりを感じたことです。すべての財源は心のこもった募金が集まり、ボランティアの手と汗を借りて手入れや調査、下草刈り、水路作りなどきつい作業の後のやりがいと満面の笑顔と感動は、自分に問う「なぜ」に充分な答えになりました。ボランティア活動に参加するあたりまえと、ここに黒松がある当り前を思いながら仙台空港の滑走路を飛び立ちました。


【感謝】
UAゼンセンの17名の皆さんとご一緒させていただきありがとうございました。
香川県立高松北高校の27名の生徒の皆さん、24日のボランティア活動ありがとうございました。
地元の大学生やボランティアの三浦さん、佐々木さん、畑君
大槻さん、齋藤ご夫妻、東京から三好さん、小宮君ありがとうございました。
そして、本部並びにスタッフの皆さんありがとうございました。
来年はもっと大勢の皆さんと一緒にボランティアに行きます。
11月6日(土)ボランティアの日レポート
広報室の林です。
6日のボランティアは、午前のみの方も含め、32名が参加してくださいました。
JR連合から13名が参加してくださり、大活躍でした。
こちらの写真は午前中のモニタリング調査を終えた一枚。

クロマツの成長は、夏に背を伸ばし、秋に幹を太らせるそうで、
縦にも横にも成長しきったタイミングで生育調査を実施します。
計るのは根元の太さ、背の高さですが、2014年に植えられたマツは
4~5mに達しているものも多く、このエリアでは根元径ではなく、
胸高直径を測定します。胸高は地面から120㎝のところ。
左から2人目の男性が自分の上着のファスナーを120㎝の位置にして、
この位置が変わらないようにしながらノギスで計測をしてくださっていました。
この時もちょうどその位置にノギスを持ってくださっています。
前の週に下の方の枝を切ってあったのでスムーズに中に入れましたが、
前の状態をご存じない皆さんからしたら「すごいところに突入する!」
「マツの葉だらけになる!!」と驚きの作業現場だったようです。
左の写真の男性が持っているのは測桿(そっかん)。
黄色の部分を上に伸ばしていき、右の写真の状態(一番伸びているところ)で止めます。
手元に高さが表示されるのを読み上げると野帳係が記録していきます。
ただ、5m近い高さのマツは、枝も茂っていて測桿を持っている人からは
先端が見えません。見えたとしても下からでは正しい位置が分かりません。
そこで、少し離れたところから測桿の先端をマツの先端ピタッと合わせるために
「もう少し上!」「ちょっと下げて!」と指示を出す人がいます。
とはいえ、これだけ茂っていると、離れたところからもなかなか見えにくく、
対象となっているマツをゆすってもらって動いているマツを探したりしながら
みんなで協力し合って測定作業を進めていきます。
こちらは胸高直径を測定中。
モニタリングの後は溝切り作業に向かいます。
みんなで並んで溝切り中。
こちらはお昼休みの一コマ。お天気が良く、寒くもなかったので
みんなでピクニックのような気分でお弁当を食べました。
お昼の後は先週の作業の時に大量についた「バカ」をひたすら取る2人(笑)
午後も溝切り続行。
東京から来た大学院生のK君は、これまでこちらの現場で
調査活動に来たことはあったものの、ボランティア活動にも
参加してみたいと、東京からやってきました。
掘っていくと途中から色が変わり、土質が変わっていることに
関心を示し、熱心に観察。周囲の人たちに解説もしてくれました。
思いのほか作業が進み、いつもより早上がり。
今回も何人かの方から感想を述べてもらいました。
岐阜からご夫婦で参加のKさんは、労働組合が派遣するいろいろなボランティアに
参加しすぎて『ボランティアマスター』と呼ばれるようになってしまい、
今は個人でこちらのボランティアに通ってきてくださっていることをお話くださいました。
そして久しぶりの参加となった東北学院大学の菊池慶子先生からは
「普段古文書などで海岸林の歴史などを調べている。今回海岸林再生の碑を
見ることができてよかった。100年、1000年先の人たちに、ここがどのように
つくられたものなのかを伝える記憶装置として非常に大事なもの。しかもこうした石碑には
偉い人たちの名前がたくさん刻まれたりしていることが多いが、ここの石碑には
本当にプロジェクトに関わった人たちの名前だけが刻まれている」とのコメントがあり
「記憶装置」という表現がとても印象に残りました。
記憶装置に匹敵するプロジェクトの記録として大切な書籍、
『松がつなぐあした』の著者である小林省太さんも参加していた今回は、
1000円以上の募金にご協力してくださった方に本を差し上げました。
写真はサイン攻めにあう小林さん↓
お天気に恵まれたよい1日でした。
参加してくださった皆さん、どうもありがとうございました!
若手中堅研修レポート③
今回の研修では松林での活動をさせていただきましたが、研修で得た学びとしては
これまでプロジェクトで行ってきた運営や広報の仕方についてが主でした。
その中で、これから松林を存続するために10年後、100年後と手入れが必要ですが、
どうやって新たな人材を取り込んでいくのかが気になりました。
大学院時代に参加した松林保全活動では活動メンバーが高齢で、若い人材を取り入れ、
活動を続けられるような持続的な仕組みづくりについても考えていました。
そこでは、海岸林と同様に作業日に地元の学生や地元住民にボランティアとしてお越しいただいていました。
また松林に興味を持ってもらうために松林ウォークなどのイベントを企画されていました。
個人的には松林に思い入れがある方が保全作業に参加しているような気がします。
ですので、数十年後に松林保全を行う人材を取り入れるために、
もっと松林に興味を持ってもらうためのイベントなどの企画も必要があると感じました。
また東日本大震災の被災地にはこれまで行ったことがなかったので、
被災地の現在の姿を見たり、現地の方々話したりすることができて、とてもいい経験でした。
昨年末、九州豪雨災害の復興支援のため、熊本県にある球磨川へ災害復興ボランティアとして伺いましたが、
研修生と話すだけで被災地の皆様が喜んでくださったことを鮮明に覚えています。
海外の国々ではサイクロンや地震、山火事など、日本では起こらないような災害も起きています。
これから、もしどこかで災害が生じたら、研修生や現地のOB・OG、オイスカメンバーと共に、
いち早く復興支援をできるように心がけたいと思います。
研修の四日間は新鮮で大変勉強になる有意義な研修でした。
また機会があれば活動に参加し、今回作った溝の効果も実際に見にいけたらと思います。
本部スタッフ吉田部長、林室長、浅野主任、また地元ボランティアの方々に、
この場をお借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

若手中堅研修レポート②
現場はグライ化(土の中が水で飽和して酸欠になっている状態)していて、水色の土になっていました。
グライ化を改善させるために、排水を考えた溝切を行いました。
一通り溝切を終えると、一旦、溜まっていた雨水を流して微調整。
溝が開通すると「おぉ~」と歓声があがりました。
実際に水の流れを見るのと見ないのとでは、達成感が全く違います。
普段とは違う作業で個人的にはいいリフレッシュになりました。
作業後は海岸林チームでミーティングと講義。
本部スタッフ3名より海岸林の運営やオイスカの広報戦略などを
レクチャーしていただき、スタッフ同士で意見を交わしました。
その後、みんなで夜ご飯を終えた帰り道、ふと道路を見るとこんなところにもマツが。
名取のランドマークとして認識されているんだろうな、と思いながら帰路につきました。
四日目は内陸側に植えた広葉樹の毎木調査と、枝払いの続きを行いました。
途中、迷子になってしまい、松林の中を探検しましたが、
樹高3~4mほどの地帯に入ると、下層の枝は枯れあがっており、
今までとは違う松林の顔を見ることができました。
作業を終え、大槻さんがお手伝いしている芋畑で芋ほりをしました。
畑の上から別の場所から持ってきた土を載せているそうですが、
津波で流されたごみが畑の中から出てきて、
こんなところにも爪痕が残っているんだと痛感しました。
その後は吉田部長らに案内していただきながら、
閖上にある伝承館へ行きました。
中にはいろいろな展示が。
震災当時の映像と、震災前の模型は特に印象に残っています。
高校生以来、当時の映像を見ていなかったので、
改めてその凄まじさに衝撃を受けました。
また模型では震災前の街並みを復元していて、家屋一つ一つに名前があり、
畑や海辺には地元の方の思い出が付箋で張られていました。
被災された地元の方々の心中を思うと、
とても切なく、力になりたいと強く思いました。
伝承館で受けた衝撃はずっと忘れないと思います。
若手中堅研修レポート①
皆様、はじめまして!
福岡にあるオイスカ西日本研修センターの飯川です。
浅野主任の記事にも記載されていましたが、今回、若手中堅研修として海岸林再生プロジェクトの活動に
参加させていただきましたので、レポートとして初めて記事を投稿させていただきます!
まずは自己紹介から。
福岡県福岡市生まれで、東日本大震災当時は高校1年生でした。
当日は高校のスポーツ大会が行われていて、夕方の帰りの会で担任の先生から東北で地震と津波が
発生したと伝えられたのをはっきり覚えています。
当時は遠く離れた場所で災害がおきた、くらいにしか思っていなかったような気がします。
それから大学に進学し、建築を専攻。その後、大学院に進学し、土木を専攻。
「生物多様性の保全」をテーマに管理放棄された里山の再生や小学校での環境教育などを行い、
また福岡県内で行われていた松林保全活動にも参加しました。
昨年より当センターで国際協力ボランティアスタッフとしてオイスカでの活動を始めました。
そして今年から正職員として人材育成に取り組んでいます。
昨年、オイスカに所属して、初めて海岸林再生プロジェクトについて知りました。
大学院で松林保全活動を経験していたこともあり、いつか行きたいと思っていたので、
研修に参加できてとてもうれしかったです。
仙台空港到着間際に上空から松林を見ることができました。
これだけの数を一つ一つ植え付けたのか、と広大な松林に圧倒されました。
現場では吉田部長と浅野主任、地元ボランティア大槻さんと松浦さんが松林の中から出迎えてくださいました。
研修初日は調査地まで松の枝払い。
チクチクと松葉に刺されながら掻い潜っていきます。
そんな中でもいろいろな発見がありました。
印象に残っているのは、若木だと幹からも松葉が出ていることです。
今まで見ていた松は背の高い成木だったので全く知りませんでした。
そして枝払いを終えると、中部センタースタッフ2名も合流し、
吉田部長が現場講義をしてくださいました。
それぞれいつ植えたエリアなのか、どのような土質なのか、などなど。
大変興味深い講義でした。
また個人的に「海岸林」というと白砂青松と呼ばれるような公園を思い出してしまい、
名取の海岸林もその一つだと勝手に思っていました。しかし話を聞いてみると、
防災インフラのための松林だから、今のところ公園としての機能を考えていないとのこと。
確かに公園として整備するのであれば、人が通るため、また林内を明るくするためにもっと間伐しなければならず、
そうなると津波を防止する機能がある程度落ちてしまいます。
また公園となると松葉搔きをしなければならず、これがまた手間がかかる管理作業になります。
防災インフラとしてであれば、鬱蒼とならない程度で林内を管理できればよいはずなので、
管理作業を省力化できます。目的に応じた手入れが必要になることを改めて実感しました。