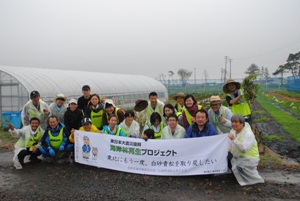クロマツ苗と浅田真央さん
北海道の出張の前半は、7回目の「学校林・遊々の森」全国こどもサミット。
全国から学校林や、国有林を活用した学校教育の制度「遊々の森」で
森に親しむ子どもたちと一緒でした。
「学校林・遊々の森」全国こどもサミットin北海道
http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/sidou/kodomo/
毎年、目を見張るような発表に出会います。
「子どもって凄い!」と感動します。
子どもらしい子どもに、今年も会うことができました。
全国の海沿いの学校では、「海岸林が学校林」という学校もあります。
シンパシーを感じます。福井県のあわら市立波松小学校では、
北潟国有林(約40ha)を活用した学校教育が行われており、
育苗から植栽、育林を行い、総合学習のみならず、各教科でも森が活用されています。
そういう学校もたくさんあるんですよ。
マラソン大会をやるとか、体育の授業でクロスカントリーをやるとか、
地元の素材を活用した羨ましいばかりの学校です。
波松小学校はクロマツの育苗もやっています。僕らと同じマツの苗を日々観察しているのですが・・・・・・子どもの感性って素晴らしいですね。
代表の女の子たちはクロマツの苗を見て何に例えているか?
「浅田真央さんがスピンしているようです」と。
名取市海岸林再生の会のTさんが、たくさんのクロマツの苗を「被災地の皆がバンザイしているようだ」と言ったことを思い出しました。
受け売りでない、自分なりの表現を堂々と言えるって素晴らしいですね。
その感性や、心の豊かさに感嘆しました。
名取の海岸林再生においても、いつか学校教育と結び付けたいと思いますが、今はまだ、それができる段階に双方が至っていないと思っています。物事には順序があると。口当たりの良い「協力」を語るわけにはいきません。ですが、地元の子どもたちに「本物の参画」をしてもらうのは、名取市海岸林再生の会、オイスカ関係者一同の共通の目標です。そのためにやっているともいえます。
名取でもいつか、海岸林再生を通じて、子どもたちの豊かな感性の一端を垣間見て感動する日が来ると思います。いつの日か必ず。
9月の3連休初日の21日(土)、ぜひ育苗場に!
久々、ブログのお休みをいただきました。
北海道に1週間出張してきました。
海岸林再生プロジェクトの将来ために、
Pricelessな財産を得ることができました。
HPトップに既に記載している通り、9月21日(土)終日、 第一育苗場にて草取りボランティアを募集しています。
http://www.oisca.org/kaiganrin/1263
たまらないほど残暑厳しい中ですが、名取市海岸林再生の会の農家の方たちと、 休み休み、おしゃべりしながら、来年わが手で植えるかもしれないクロマツを愛でつつ、口も手も動かしながら、草、抜いていただけませんか?
もし、年に一度しか宮城に来れないとすれば、こういう草取りこそ、 地元の方や、裏方と、言葉を交わす時間がたくさんあると思います。
遠方から来る人もいるでしょう。
一同、「一期一会」のつもりでお待ちしております。
でも、育苗場での草取りは2020年までずっと続きますから、
どうぞご無理なく。
ちなみに私は草取りがなぜか好きです。
子どもの頃から、少年野球でも、大学までのソフトテニス部でも
チーム運営に草取りはつきものでした。ちゃんとしないと後が大変でしたから。
今は本当に時々、育苗場で地元の方に混ざらせていただくのですが、
この時は、ただ一心になれるんです。
でも、こういう作業に来て下さる人がいるのなら、
我々にとって本当に嬉しいのです。
お盆休み関係なく働いている方もたくさんいらっしゃると思いますが、
今週、しばらくこのブログはお盆休みとさせていただきます。
ブログが更新されなくてさびしいという方がいらっしゃいましたら、今月号の月刊「OISCA」(8-9月合併号/年次報告書)に掲載している「海岸林再生プロジェクト」の特集記事をじっくりご覧いただければと思います。
束の間のお盆休み後は、担当の吉田が北海道で見聞きしてきた海岸林再生の取り組みなど、じっくり報告いたします。
 ■宮城県/匿名
■宮城県/匿名
「海岸林再生プロジェクト」に思う
・4月19日にクロマツ苗の移植作業に参加させていただきました。OISCAの広報を通してこの2年間、名取の海岸にクロマツ林を再興する作業がその初発から多くの苦労と困難を伴うものであったことを存じてはおりましたが、現地で詳細にその経緯を伺い、実際に作業の一端に関わる体験をさせていただいたことは、震災復興の進捗状況を身をもって認識する貴重な機会となりました。同時にこの地で仙台藩政の初期から4 世紀にわたり受け継がれてきた先人の植林の営みに思いを馳せることにもなり、わずか1日ではありましたが、ほんとうに得難い体験でした。
・OISCAの進める海岸林再生プロジェクトは失われたクロマツ林の再興と同時に名取の被災農家の暮らしの再建を支援する取組みでもあることは、地元新聞でも何度か報道されています。ただし、一般的にはいまだ他の被災自治体で進行する植林事業と変わらない認識でとらえられていることは否 めません。そうした点で、可能であれば、作業に従事する農家のみなさんの暮らしぶり、その変化の有無などを伝えていただく機会がさらに充実すればと期待いたします。
・当日おいでになったOISCAの若いスタッフのみなさんからは、海外でのボランティアの体験や、日本の政治や文化の現状に並々ならぬ思いを抱いていることなど伺い、強く印象に残りました。OISCAの 立ち上げた活動が名取の地で世代や国を超えて多くの人々の出会いと交流をもたらしていることも意義のあることでしょう。こうして築かれた交流関係が名取市の今後の街づくり、市政運営を活性化させる、なにがしの仕掛けとなることに期待を寄せるものです。
■東京/報道関係者
 私を含めて海岸林を単なる「景色」としてしか見ていなかった多くの人々に、海岸林再生事業は「なぜそこに林があるのか」、「どのように周辺の人々の暮らしを守ってきたのか」を教えてくれました。またその林を再生する ために、どれほどの年月と労力、そして資金が必要かを知らせてくれました。
私を含めて海岸林を単なる「景色」としてしか見ていなかった多くの人々に、海岸林再生事業は「なぜそこに林があるのか」、「どのように周辺の人々の暮らしを守ってきたのか」を教えてくれました。またその林を再生する ために、どれほどの年月と労力、そして資金が必要かを知らせてくれました。
何から始めていいかも分からない、途方もないプロジェクトであるが故、そのプロモーターでありネットワーカーであるオイスカさんには、ただただ敬意を表します。この事業は、これから何十年に もわたって、様々な作業にかかわっていく人たちを育てる、壮大な人材育成プロジェクトでもあります。
国内のみならず世界中で理解と共感を得ることができる事業だと確信しています。
私は被災地出身、両親が海岸林再生の会のメンバーという環境にあり、他の皆さんとは少し異なった視点からオイスカさんの活動を捉えているかと思います。
海岸林再生プロジェクトは海岸林という一つのオブジェクトに対する限定的な 再生ではなく、裾野の広い大 きな意味を持った再生プロジェクトだと考えています。被災農家で考えれば生活(収入)の再生、コミュニティの再生、生きる活力の再生など、プロジェクトが多方面での“再生”に良い影響を与えていると思います。
また“再生”をもう一度“育む”という言葉に置き換えるとすればいつもおっ しゃっている「オイスカは人を育てている」という言葉こそオイスカさんの成されてきたことの意味を表しているような気がします。
私自身もこのプロジェクトに育てられた一人です。
会社組織に属しながら両親らの活動を応援できる環境にいることを有り難く思 うと同時に、応援の活動を通じて日常業務では学び得ないたくさんのことを学ばせていただいています。
また、海岸林再生に多くの時間がかかるように、被災地の復興にも同様に多く の時間が必要となります。多くの被災地支援活動が短期的な活動であるなか、10ヵ年計画という長期プロジェクトである時点で社会的意義、社会に対するメッセージを含んでいると思っています。被災地の復興には多くの時間とお金がかかるという事実を、一つのプロジェク トというゴールを明確にしたわかりやすい単位で明示していると考えています。
オイスカさんのこれまでの取り組みには非常に感謝しております。
個人的な話ではありますが、両親との絆を深めたのは紛れもなくこのプロジェ クトです。このプロジェクトがなければ親孝行の機会もきっと自分では見つけられず、今いるANAすかの仲間たちとの出会いもなかったと思います。そう考えると感謝せずにはいられなくなってしまいます。
細々ではありますが、これからも応援させて頂きますのでどうぞ宜しくお願い いたします。

■宮城/報道関係者
大抵の人にとって、気が付いた時には海岸林は存在していたでしょう。自然景観の一部として。
震災で流失してしまったからこそ、初めてその存在を知り、目を向けるようになったという方も多いのでは。
祖先が植え、人間を守った海岸林を、再び育てる。しかも そこには数十年、数百年という時の流れがある。
プロジェクトはそれ自体、雄大さとロマンを感じさせます。
一人一人の人間が、一本一本の苗木を植えていくことから 始まるというのもいいですね。
これからも多くの人間を巻き込んで進めていってほしいと思っています。
プロジェクトに参加する人は、黙っていてもその意義を理解している方々と思いますが、
土地の歴史や風土と合わせて海岸林を紹介するデータがあると、より深みが増すでしょうね。
その時しか参加できない人もいるでしょうから、1回1回の活動を大事にしてもらいたいと思います。
■東京/会社員男性
<社会的意義について>
 グループ企業全体に呼びかけられた企画に、共にボランティアとして参加した方から「壮大なテーマである印象を感じた」と感想をいただきました。
グループ企業全体に呼びかけられた企画に、共にボランティアとして参加した方から「壮大なテーマである印象を感じた」と感想をいただきました。
私も非常に大きなプロジェクトであり、社会的意義のあるプロジェクトであると強く感 じています。また、日本の中では中規模の空港ではあるが、戦略的に重要な仙台空港の近 隣であることが、社員としては壮大ながらも親近感の沸くプロジェクトとなっており、仙 台空港や東北に関わりのある社員の多くがボ ランティア企画に参加しているのも事実です。
一 方で、仙台・東北にあまり関わりのない方にとって社会的意義があるのかどうかが今後の課題でもあるように感じています。事実、関わりのない方からすれば壮大ではあるものの身近に感じることは難しいのかもしれません。社会的意義をそうした人にもうまくア ピールすることがことができれば社内でも広く募金活動を展開 したり、そこ から派生した新 たな取り組みも行えるのではないかと考えています。
<活動の進め方について>
これは社内の進め方としての課題かもしれませんが、今後の活動の中では本プロジェクトにど こまでどのように関われるのかを見出さなければいけないと感じています。これまでの取り組みの中で、ボランティア活動に関する社員の意識の強さを非常に強く感じました。
一 方で、非常に意欲はあるものの、日々の仕事内容はかなり特殊なものが多いため、言うなれば活動に当って何か実用的なスキルを持ち合わせているわけではありません。「知っている」「行ったことがある」程度の経験だけでなく深い知識やスキル、経験を蓄積しなければな らないとは思いますが、同時に、せっかく意欲があるのだから技術的には素人レベルでも違った形で支援できる方法はないかを検討し、意欲をうまく吸い上げて活かしていくことが必要です。
もしかすると、そうした観点で取組みを継続して行くことができれば、事業成果としてだけではなく、逆説的に復興支援という形で社会的な意義を持たせることができるのではないかと感じています。

震災から一ヵ月後に発表された宮城県震災復興基本方針では、
復興を達成する期間を10年後(平成32年度)としています。
当時、海岸林再生プロジェクトの立案に向けて動き出していたこともあり、
自分なりに読んでみて、あまりの果てしなさに茫然とした記憶があります。
当然、その大方針に重ねあわせながら、チーム海岸林メンバーや行政関係者と立案をすすめました。
県震災復興計画と、海岸林再生プロジェクト10ヵ年計画を重ねると
●復旧期(3年):H23年~H25年 (大量の苗木を生産する体制を整えよう)
●再生期(4年):H26年~H29年 (植栽がピークを迎えるだろう)
●発展期(3年):H30年~H32年 (長い育林に向けた、地域に根差した実施体制を準備しよう)
7月25日の河北新報社に、『復興「再生期」へ専門家8人提言』との小さな記事がありました。
宮城県は、復興計画策定に関わった県復興会議委員の意見を、再生期の施策に反映させるための懇話会を行ったそうです。
「2014年2月には、再生期の施策の実施計画を策定する」との事でした。
「復興」の実現、「新しい東北創造」。
それに向けた実践部隊の一端を担うべく、大方針に沿って、各方面と強力なタッグを組んでゆこうと思います。
私たちは、来年からの「再生期」突入を強く意識し、日々を過ごしています。