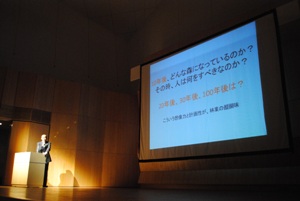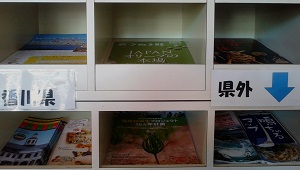3月18日(金)午前2時10分 FM出演(ほぼ全国)
番組名「ON THE PLANET」
出演日 3月17日(木) 26時10分頃~ (7分間)
放送局(JFN系列35局)
【東北】FM青森・FM岩手・Date FM(宮城)・AFM(秋田)・Rhythm Station(山形)・ふくしまFM
【首都圏】FMぐんま・RADIO BERRY(栃木)
【中部】FM-NIGATA・FM長野・K-mix(静岡)・FMとやま・HELLO FIVE(石川)・FM福井
@FM(愛知)・FM GIFU(岐阜)・レディオキューブFM三重
【近畿】e-radio(滋賀)・FM OSAKA・Kiss FM KOBE(兵庫)・V-air(鳥取・島根)・FM岡山・HFM(広島)
【四国】FM徳島・FM香川・JOEU-FM(愛媛)・Hi-Six(高知)
【九州】FMS(佐賀)・FM Nagasaki・FMK(熊本)・Air-Radio FM88(大分)・JOYFM(宮崎)・μFM・FM沖縄
*FM北海道、FM東京、FM山口、FM福岡以外すべて。
*各地域の周波数はコチラ
http://www.jfn.jp/Stations/all
「さて、ここからは夢を追っている人に話を聞いていきましょう。
今日は東日本大震災で奪われてしまった海岸線の海岸林だったクロマツを植樹して取り戻そう
という「東日本大震災復興 海岸林再生プロジェクト」。オイスカの吉田俊通さんに電話が
つながっています。吉田さん、こんばんは!!……」
収録時間 3月17日(木) 23時30分頃~ 名取のホテルで電話収録対応します。
こんにちは。啓発普及部の家老です。
前回に引き続き、視察研修パート3です。
これでシリーズは終了です。
メイプル館で衝撃的なDVDの映像を見た後、研修生は有限会社 耕谷アグリサービスを訪問しました。有限会社 耕谷アグリサービスは、名取市で稲・麦・大豆等の栽培をされており、機械を使用した管理も特徴です。被災後には、津波で塩害を受けた田んぼでも育てやすい綿花を育てました。綿は温かく、色が純白なため、犠牲になった人の鎮魂の意味も込めて綿を育てているそうです。
研修生は、環境保全型有機農業の指導者育成の研修を受けているため、たくさんの質問がでました。
①堆肥を使っていますか?
②田んぼのレべリングはどうやっていますか?
③精米は1回にどのくらいできますか?
④機械の価格、使い方を教えてください
⑤震災のときのどのような被害はありましたか?
⑥ハウスの資材は、どの程度の気温まで大丈夫かですか?
復興しながら、最新の機械を用いた環境保全型農業に取り組んでいる耕谷アグリサービスに、研修生は興味津津でした。研修生の質問に丁寧でお答えいただき、またお忙しい中、対応していただいた有限会社耕谷アグリサービスさん、本当にありがとうございました。
研修生は、先週末それぞれの国へ帰国しました。
同じ釜の飯を食べた研修生は本当に仲良し。涙涙の別れでした。
日本では、復興する日本人の姿を含め、多くのことを学んだことと思います。
宮城県の訪問は、1泊2日と短かったですが、研修生の心には確かに何か残ってくれたと思います。
これから学んだことを活かしながら、それぞれの国で活躍してくれることを願うばかりです。
オイスカ海外研修生視察①
3.11震災から5年
オイスカ海外研修生視察②
こんにちは。啓発普及部の家老です。
前回に引き続き、視察研修パート2です。
名取到着2日目、研修生はまず、仙台市若林区荒浜にある荒浜慈聖観音へ行き、手を合わせました。
その後、名取市閖上の日和山、ゆりあげ港朝市のメイプル館へ行きました。
そのメイプル館で見たDVDの映像が研修生にとって衝撃だったようです。
被災地や海岸林の現場を訪れても、そこに震災、津波の影響を直接感じることはできません。もちろん家がなくなり、建物もなく、ダンプカーが走っていることで、ここは確かに津波がきた場であることは分かります。しかし、以前の状態をしらないため、研修生は被災地を訪れたことだけで、津波や震災を想像するのは難しかったようです。
映像では、地震直後の揺れ、人の悲鳴、津波が徐々に迫ってくる様子、車が津波に飲み込まれる瞬間、それを撮影している人の声が流れていました。
研修生は真剣に画面を見つめていました。
映像終了後、フィジーとパプアニューギニアの研修生は2000円するDVDを購入していました。アジアの各国と違い、メラネシアに属している両国。国土を海に囲まれているため、津波に対する意識も高いのかな?と感じました。
映像を見ることができるメイプル館の詳しい情報はこちらです。→http://yuriageasaichi.com/maple
プロジェクト10ヵ年計画「上半期」が終了した日
チーム海岸林に、昨年、日本経済新聞(論説委員兼解説委員)を退職した
小林省太さんが加わり、デビュー戦ともなった震災5年目、
3.11の一連の行事が無事終わりました。
・3月11日:経済同友会小林喜光代表幹事、復興庁岡本事務次官ほかご一行72名の視察
・3月12日:海岸林再生プロジェクト第3回定期報告会in名取 聴講者106名
・3月13日:海岸林再生の現場を歩こうツアー 参加者54名
これらに関係した方のみならず、全国のどこかで、このプロジェクトに思いを馳せ、
チーム海岸林の「一員」としてご協力いただいている皆様に、心から御礼を申し上げます。
しばらくぶりに、植栽現場の「寄附者銘板」のたくさんのお名前を、一人でゆっくり見たことが、
私の震災5年でした。その時以外、感傷に浸ることはありません。5年目は単なる一通過点ですから。
名実ともに胸を張れるビックチームになりました。どこかで、誰かが、いつも、休むことなく、
毛細血管の様に細やかに、遠くにいても復興の一端を担うチームとなりました。
一連の行事で、名取市海岸林再生の会、オイスカ、支援者・ボランティア有志が一堂に会し、
笑顔で、途方もなく元気よく、堂々と、ご支援に対する成果報告をいたしました。
特に支援者・ボランティアの皆さんの報告は、聞き惚れてしまいました。
素晴らしいトークセッションでした。
また突然、仙台の女子高校のボランティアグループが寄附を申し出てくださり即席の登壇。
予定にないサプライズ。
遠くから来てくださった方もたくさん。
オイスカ富山の熱烈な支援者「大江鉄工」の大江敏光社長、新潟市北区役所の藤井さん、
埼玉県草加市の社協幹部の舩渡さん、ANAグループ社員の廣瀬君、久保君等々…
佐々木一十郎名取市長は、追悼式を挟み、3日連続、我々の全ての行事に来て下さりました。
名取市の農林水産課、政策企画課、震災復興部まちづくり課の皆さまをはじめ、
宮城県庁農林水産部森林整備課、林野庁東北森林管理局仙台森林管理署、復興庁、宮城復興庁
経済同友会、仙台経済同友会、河北新報社、NHK仙台放送局、東北放送、FMなとり。
3.11に向けて、新しい寄附金チラシ作成にご協力いただいた、名取市閖上出身のイラストレーターのicoさん、
パートの鈴木和代さん、デザイナーの土肥さん…お名前を挙げ切れません。
3.14から今年の播種準備「コンテナへの培養土詰め」が始まります。
名取市海岸林再生の会も燃えています。
私もギアチェンジします。
140往復目の名取出張
当然、4年連続で3.11を名取で迎えます。
今回の主な出張目的は、FMなとり出演、経済同友会代表幹事一行約70名の視察対応、
復興庁事務次官ほか幹部の皆さまも含まれる。そして定期報告会、現場を歩こうツアー。
例年通り、来週から出張目的はがらっと変わります。
出張前日というか当日は、どうしても徹夜になることが多い。
やるだけのことをやってからでないと、出足が鈍って時間が無駄になる。
今回は安易なことを先にやっていたから。仕事の順番をつい間違えた。
仙台市内の細かな用事を済ませ、名取事務所入りしたのは午後。
途中で閖上出身のおじいさんとバッタリ会った。
「まだ仮設住宅にいる。かさ上げした災害公営住宅に入居するのは3年先」と。
トレーニングで美田園から歩く。土は乾燥している。今日は蔵王おろしが吹かない。
この調子だと、また去年の様に4月に入ってどっさり雨が降るのか。
来週から再生の会はコンテナ播種の準備である「土詰め」が本格的に始まる。
今日は静かだ。
明日の視察対応の現場確認へ。
途中、あちこちにテントが張られている。
明日は追悼式の他、大小さまざまな行事。
工事関係者はひたすら年度末の工事。
FMなとりは年に3回は広報してくださる。
週末の行事の最終PRの時間をいただいた。
今晩、チーム海岸林に新たに加わる小林省太さん(元日経新聞論説委員)と
ボランティアの鈴木昭さん(元フォーリンプレスセンター職員)と、
清藤城宏オイスカ緑化技術参事(元山梨森林総合研究所主任研究員)が来仙。
酒豪ばかりだ…
3.11 震災から5年
こんにちは。浅野です。
今日で震災から5年です。明日は定期報告会、13日は植栽現場を歩こうツアーを行います。
どんどん時間が経ち記憶から薄れていく人も多い中、3月7日と8日の1泊2日でオイスカ西日本研修センターの研修生たちが現場視察に来ました。
家老のブログにもあったように研修生の来訪目的はオイスカの海岸林再生プロジェクトを知り、その意味を理解してもらうこと。また同時に、被災しても前を向いて復興する日本人の姿を学ぶことでした。
昨年4月に来日し、11ヶ月の研修を行ってきた中で震災のことを耳にしたことはあったようですが、研修場所は福岡ということや震災から4年が経っていたということもあり、ほとんどの研修生がぼんやりとした輪郭しか持っていなかったようです。
せっかくここまで足を運ぶのだから何かを感じて帰ってほしいと思い、震災当時の映像を閖上のメイプル館で見てもらうことにしました。
引率のスタッフも含め、全員が初めて見る映像だったようで衝撃を受けていました。
研修生の中には、国に帰って日本で5年前に何があったのか、そこからの復興をどのように進めているかをちゃんと伝えたい!という気持ちからDVDを買う研修生もいました。
そのあと現場に行き、この小さい松が大きくなってしっかりとした松林になればもし次に同じような災害が起きても被害は今回より小さくなるだろうということを伝えました。
有限会社耕谷アグリサービスでは代表の佐藤さん、前代表の大友さんに震災から今までどのように農地を戻してきたのか・どういった点が大変だったか・現在の状況など、色々なお話をしていただきました。研修生は自分たちも農業を行っていることもあり、熱心に耳を傾けたくさんの質問をしていました。
ミャンマーやフィジーのサイクロン、フィリピンの台風、インドネシアの地震・津波など研修生の国でも大きな自然災害はあります。今回の視察で感じたことが帰国してから少しでも役に立てば…と思います。
今回、震災当時の映像を見せていただき私自身も多くのことを感じました。幼馴染みの祖父祖母がなくなったこの震災。まだ行方不明の方が2500人以上、身元が分からない方も70名以上います。
もう5年、まだ5年、人それぞれ感じ方は違いますが忘れずに過ごしていってほしいと思いました。
「5年間の実績」要約版
【2011年~2015年度実績総括】
7つのシステムを確立しました。
1.大規模官民協働の協定締結(約100ha)
2.大規模苗木供給体制(宮城県必要本数600万本中、50万本生産目標)
3.地元に雇用創出(2014年:1,402人、2015年:1,400人)
4.効率的な一貫施業の実施体制(育苗~植栽~育林)
5.低コスト林業(自家生産の育苗は、購入より低コスト)
6.市民参加の実現(年間ボラ1,600人、視察年500人、報告会年5,000人)
7.民間活力・民間資金導入(寄附金目標額10億円)
●協定締結面積 94.74ha
内訳:国有林:2.91ha、県有・市有林:89.98ha、内陸防風林共有林:1.85ha
*2016年度に内陸防風林市有林1.87haへの支援追加など、今後も増える見通し。
●植栽完了面積 25.49ha
*初播種は2012年3月。2年の育苗を経て、植栽開始は2014年4月。
*2016年度も前年同様、約10ha、50,000本植栽予定
●植栽完了本数 131,416本
*宮城県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ、宮城県産精英樹クロマツ等
*植栽直後活着率は、2014年度:98.4%、2015年度:99.1%
●総雇用数 3,647人(8時間/日人)
*育苗、植栽、施肥、下刈、除伐、各種工事で、2033年までに約11,400人の雇用計画
●現場ボランティア・視察受け入れ人数 6,400人(うち外国人55ヵ国221人)
うちボランティア参加人数 3,318人(2013年~)
●活動報告会・講演会参加者 23,731人(18県137回実施)
●海岸林HP 活動報告blog更新回数 1,120回
●写真パネル展開催回数 57回(㈱ニコン支援)
●国内メディア掲載回数 193回(新聞・TV・ラジオ等)
海外メディア掲載回数 62回(32ヵ国)
●寄付金・民間助成金総額 405,418,335円(2016年1月末現在)
*2021年~2033年に活用する育林等の費用として、現在126,139,115円の積立を
すでに行っており、目標として最低2億円の積立を計画している。
*上記は、2016年3月8日現在の速報値です。
*ホームページトップ「インフォメーション」にも実績報告を掲載しています。
みなさんこんにちは。
啓発普及部の家老です。
3月7日から3月8日、西日本研修センターの研修生が現場視察及び、
被災地の見学を行いました。目的は、オイスカの海岸林再生プロジェクトを知り、
その意味を理解してもらうためです。
また同時に、被災しても前を向いて復興する、日本人の姿を学ぶためです。
オイスカは、国内外で活動を行っていますが、
環境や貧困などの問題を根本から解決する本質的な取り組みとして、
農業が指導できる人材を育てる人材育成事業が柱のひとつです。
詳しくはこちら→http://www.oisca.org/project/human.html
今回は、その人材育成事業で行っている研修を福岡県にある西日本研修センターで修了した
13名の研修生が現場に来ました。彼らは、10の国と地域から1年間農業を学ぶために日本に来た青年たち。
彼らのほとんどが環境保全型有機農業の指導者育成コースの研修を受けた研修生です。
母国の農業発展を担う人材となるべく日々研修に励んできました。
また、日本の文化を通して、日本人の生き方や考え方も学んできました。
今回はその研修の一環として津波で被災し、復興していく日本人の姿を学びました。
初日は夕方に空港に到着したため、現場には行かずに、担当の吉田が“迎賓館”と呼ぶ
松島の霊泉亭へ直行。あっっつ~~~~い温泉に入り、松島の会員さんとの交流を楽しみました。
そして、次の日の視察、見学に備え、早めの床につきました。
次回の西日本研修センター視察②で詳しい内容をお伝えします。
「道の駅」へのローラー作戦
こんにちは
またまた久しぶりの登場の鈴木です。
プロジェクトでは、海岸林再生プロジェクトのことや日本各地にある海岸林の存在、
海岸林の役割なども含めて、多くの方に知っていただくためにパンフレットを使って広報活動をしています。
ブログでも数回、「パンフレットを設置してください!」というお願いを掲載しましたので、
記憶の片隅の隅の隅辺りに残っている方がいるかもしれません。
パンフレットを設置してください!と呼びかけるのみで、他力本願ではいけないと思い、
まずはオイスカの関わりの深い宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、香川県、福岡県を中心に
「パンフレット設置のお願い」という手紙を公園管理事務所、日帰り温泉施設、
道の駅にテスト的に送らせていただきました。
この手紙で設置していただけると連絡があったのは2%程度・・・悲しい現実です。
そうはいっても、せっかく手紙を送ったのだからと、
次は比較的反応の良かった道の駅に電話かけ作戦をしてみることにしました。
電話をしてみると、「えっ?そんな手紙見てませんねぇ」
「手紙を送っていただいていたんですか?」とがっかりの反応。
でも、プロジェクトの簡単な説明をして、パンフレット設置をお願いしてみると、
「パンフレット置きますよ。どうぞ送ってください」という、
ありがたい対応をしてくれるところが多くありました。
打率は8割くらいです。高打率にびっくりするやら感謝するやら。
そんなこんなで新たに43件に設置していただきました。
【宮城県 11件】
道の駅上品の郷、あ・ら・伊達な道の駅、道の駅三本木やまなみ、道の駅おおさと、道の駅村田、道の駅林林館、道の駅路田里はなやま、「道の駅」津山もくもくランド、道の駅米山、道の駅七ヶ宿、道の駅大谷海岸
【愛知県 10件】
道の駅伊良湖クリスタルポルト、道の駅どんぐりの里いなぶ、道の駅デンパーク安城、道の駅つくで手作り村、道の駅立田ふれあいの里、道の駅あかばねロコステーション、道の駅柿筆の里・幸田、道の駅にしお岡ノ山、道の駅瀬戸しなの、道の駅藤川宿
【香川県 10件】
道の駅瀬戸大橋記念公園、道の駅津田の松原、道の駅ことひき、道の駅ふれあいパークみの、道の駅空の夢もみの木パーク、道の駅滝宮、道の駅ことなみ、道の駅うたづ臨海公園、道の駅たからだの里さいた、道の駅ながお
【福岡県 9件】
道の駅小石原、道の駅しんよしとみ、道の駅うきは、道の駅おおむた、道の駅たちばな、道の木うすい、道の駅くるめ、道の駅みやま、山田緑地
【宮崎県 1件】
道の駅ゆ~ぱるのじり
【熊本県 2件】
日向サンパーク温泉お舟出の湯、四季の里旭志
道の駅の方とお話する中で、
「ウチ(道の駅)は海とはちがって山にあるんですよ。そんなところに置いてもいいんですか?」と
おっしゃる方がいらっしゃいました。「私たちは日本全国の多くの方にまずは知っていただきたいので、
海だろうと山だろうと構わないんです」と。
でも、少し理解をしていただいた上での問いのようで、質問していただいたことがうれしかったです。
快く応じてくださった道の駅のみなさん。本当にありがとうございます。
まだまだ道の駅へのローラー作戦を続けていきます。
道の駅でプロジェクトのパンフレットを見つけたときには写真にとって送ってくださいね!!
復興の現場最前線を伝えて、ブログまもなく1,120回…
2011年10月だったと思います。仲間たちから勧められ。ひどく不承不承だったけど。
並行して個人のFacebookも試しましたが、二兎を追うのはやめました。
読んでもらえないんじゃないか。ブログなんて柄でもないし…
最初は習慣がなく、途切れ途切れ。
「誰か読んでくれるんだろうか」と、移動の電車の中で書きながら。
今でもそう思う時もあるけど、やっぱりそうではない。
書き続ける目的は数多くあります。
仕事としても、自分個人としても。
ですが、多くの人のおかげで存分に仕事させていただいているのですから、
何が何でも続けねばならぬことと考えています。
もし、これを始めていなかったら…
「即アウトプット。説明責任、情報公開を極めよう」なんて思わず、
むしろもっと、それらを軽んじていたでしょう。
記録という面でも、将来は手がかりを随分失ったでしょう。
このブログは、多くの人で書いています。
そして遠くの支援者含めて、みんなのものになっています。
海岸林ビックチームの統率の源にもなっているでしょう。
「最近、オイスカは何をやっているんだろう」と、
時々でも、1年に1回でも、訪ねてくれている人は必ずいると勝手に思い込んでます。
取材する人も、仕事で関わって下さる人も情報源にしてくれています。
もうすぐ5年、もうすぐ1,120回。この面でもよく頑張った。
とにかく何でも続けることは大事ですね。
やってみてわかりました。
あの時始めて本当に良かった。