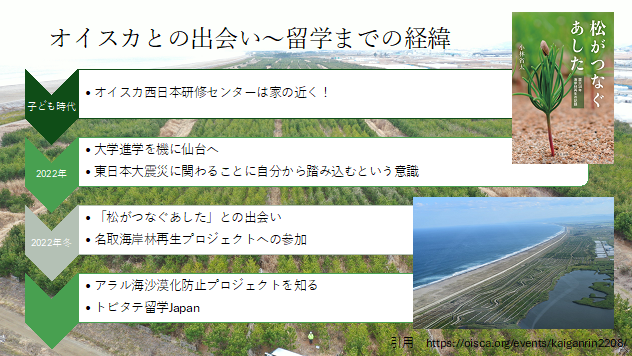![]()
インタビュー
 |
鈴木 英二氏 仙台空港近くに駐車場を経営する傍ら、再生の会の会長も務める。 長年、中学校の化学の教員をしたのち定年後は公民館長を務めるなど地元の名士として地元の方からの信頼も厚い。 津波で何百件と家が流された中、唯一、鈴木氏の家だけが流されなかった。 |
— どうして海岸にクロマツを植えようと思ったのですか? プロジェクトを始めるときのお気持ちは?
2011年3月11日に起きた東日本大震災の津波で自分の家も海岸林もすべて流されてしまった。当時、地域住民は自分の生活が第一で自分のことしか考えていなかった時に、これまで生きてきた自分を振り返り、支えてきてくれた海岸林(潮風から地場農業を守ってくれた存在)を再生しなければならない気持ちになった。また、海岸林は先祖代々、守り続けられてきた、地域にとって大切なものだから、なんとか再生させたい思いがあった。
津波が来る前は強く感じることはなかったが、海岸にマツを植えることにより、潮風、砂、から農作物(チンゲン菜、小松菜)を守る働きがあると、失って初めて気付かされた。あって当たり前のものを失ったという気持ちがある。
— 震災時の状況とその時のお気持ちは?
とにかく、津波の回転に驚いた。津波で流された人も多かったが、中には電信柱につかまって助かった方もいた。その中でも地元の下増田神社の本殿が流れなかったことも驚いた。名取市でも自分の家に帰れない人が多いが、福島の原発で家にも帰れなくて、人体にも心配を抱える人がいることは痛ましいと感じている。
もし、地震がなければ残りの余生をのんびり暮らしたかった。そんな気持ちも流された思いである。
— 子どもの頃、マツとどう接してきたか? マツの歴史は?
松葉拾いをよくしていた。当時、マツの枝や葉は重要な燃料であったからだ。小学校の時は授業の前に必ず、松葉拾いをするのが習慣であった。冬のストーブの焚き付けのために地域住民が松葉を奪い合いするほどであった。昔は農業を守るというよりも生活を守るための「マツ」として存在していた。
電気、ガスが普及していく中で松葉の燃料は廃れていった。それでも、今も昔もマツの恩恵としてキノコの収穫がある。さらに良い木は建築材として切られ、そこに新しい木を植えることにより間伐作業になっていた。特に国有林ということでこの仕事を担ってきたのは営林署(現在の森林局)の人たちであった。国のお金がその森林局、あるいは森林組合に行き届き、保安林としてマツが守られてきた。しかし、近年、それもまた減少してきた。
— 海岸林再生プロジェクトの成功のカギは?
まずは地元の人が海岸林再生のためにひとつにならなければならない。それに加えて多くの支援も必要である。その点において、オイスカには、中長期的な視点で国、県、市、そして地元住民の理解を得て、海岸林を再生に向け、共に活動してくれることに非常に感謝している。特に、プロジェクトをボランティア主体と考えず、地元住民を雇用し、地元住民主体を貫く姿勢を評価している。雇用するからこそ、地元住民も本気になるし、それだけプロジェクトは大きなものになる。
再生の会の内部では実際の現場で働く人と資金調達、宣伝作業を行う人の関係がうまく連携していかなければならない。運営上、その両輪が常に回っていることが成功のカギである。支援の呼びかけ、組織のアレンジメントを仕切る会長であると自分と、現場でクロマツを育てる再生の会のメンバーの人間関係が悪くならないように努めることも大切である。常にお互いの気持ちを大切にすることこそ、プロジェクトの成功のカギである。
— 若い世代への期待は?
いずれ再生の会も募集をかけて、若い人も入れたい。とにかく、地元の若い人を雇用していく。
今後は教育的な観点を考えて、もっと学生も巻き込んでいきたい。
— 復興が進む中でどのようなまちづくりになってほしいですか?
みんなの憩いの場となる森林公園の中に津波の悲惨さを忘れないように教育的に活用できる場所を作りたい。だから、自分自身の壊れた家も残している。口伝えというのは効果がなく、やはり「百聞は一見にしかず」で見た目のインパクトを強調したい。これから、復興が進む中、この悲惨な津波の被害を一目でわかるものを残すことが必要であると感じている。
インタビュー日:2013年5月30日
聞き手:公益財団法人オイスカ 国際協力ボランティア 木村肇
![]()